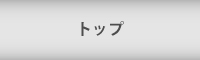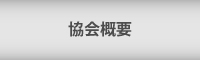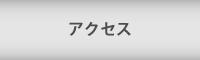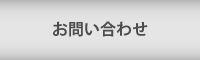2.テーマと講師
| 年度 | テーマ | 講師 | |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | |||
| さつまいもの魅力と可能性 | さつまいもカンパニー株式会社 代表取締役 一般社団法人さつまいもアンバサダー協会 代表理事 |
||
| 橋本 亜友樹 | |||
| 新時代のさつまいも品種 | 農研機構 中日本農業研究センター 上級研究員 | ||
| 田口 和憲 | |||
| 紫サツマイモを利用した機能性表示食品「肝ファイン」の開発 | 株式会社ヤクルト本社 開発部 開発課 担当課長 | ||
| 太田 英樹 | |||
| 株式会社ヤクルト本社 開発部 研究開発管理課 課長 | |||
| 渡邉 治 | |||
| 人と農が輝くさつまいもスィーツ戦略 | 地域特産物マイスター(さつまいも加工品(さつまいもスイーツ) 新潟県小千谷市) 株式会社農プロデュース リッツ 代表取締役/さつまいも農カフェきらら オーナー |
||
| 新谷 梨恵子 | |||
| 北海道産さつまいもを使った商品開発 | 株式会社北海道フード工房 常務取締役ディレクター | ||
| 成田 靖大 | |||
| 令和3年度 | |||
| 知られざるナスの多様性とその可能性 | 農研機構 野菜花き研究部門 主任研究員 | ||
| 宮武 宏治 | |||
| 食品機能性を活用したナスの新展開 | 信州大学大学院 農学研究科 准教授 | ||
| 中村 浩蔵 | |||
| 高知県における機能性表示食品「高知なす」の取り組み | 高知県農業技術センター 技術次長 | ||
| 高橋 昭彦 | |||
| 多様な新潟のナス 今も残る在来品種 | にいがた在来作物研究会 会長 | ||
| 小田切 文朗 | |||
| 地域伝統野菜「吉川ナス」の栽培状況と地域振興の取組について | 地域特産物マイスター(吉川ナス 福井県鯖江市) 鯖江市伝統野菜等栽培研究会会長 |
||
| 福岡 重光 | |||
| 令和2年度 | |||
| トウガラシの世界とその多様性について | 信州大学 農学部 准教授 | ||
| 松島 憲一 | |||
| カプシノイド等の健康機能性について | 城西大学 薬学部 教授 | ||
| 古旗 賢二 | |||
| フルーティで辛味のキレが良いカプシノイド含有トウガラシ香辛子の研究開発と商品化 | 株式会社サイゼリヤ アグリ技術部 マネージャー | ||
| 関 哲也 | |||
| 川崎市経済労働局イノベーション推進室 知的戦略担当係長 | |||
| 加藤 行一郎 | |||
| 津軽伝統トウガラシ「清水森ナンバ」の復活とブランド化 | 在来津軽「清水森ナンバ」ブランド化確立研究会 会長 地域特産物マイスター(清水森ナンバ(トウガラシ) 青森県弘前市) |
||
| 中村 元彦 | |||
| 令和元年度 | |||
| 漬け物の機能性について | 東京家政大学 家政学部 栄養学科 教授 | ||
| 宮尾 茂雄 | |||
| 伝統野菜(カブ)の多様性について | 岩手大学 農学部 名誉教授 | ||
| 高畑 義人 | |||
| 産地振興の取り組み 赤丸かぶ | 地域特産物マイスター(赤丸かぶ 滋賀県米原市) | ||
| 藤本 勇 | |||
| 産地振興の取り組み 赤丸かぶ 山内カブラ | 地域特産物マイスター(山内カブラ 福井県若狭町) | ||
| 飛永 悦子 | |||
| 産地振興の取り組み 焼畑あつみかぶ | 地域特産物マイスター(焼畑あつみかぶ 山形県鶴岡市) | ||
| 忠鉢 孝喜 | |||
| 平成30年度 | |||
| 香酸カンキツ類の機能性について | 農研機構 果樹茶業研究部門 ブドウ・カキ研究領域 | ||
| 小川 一紀 | |||
| 「すだち」と「ゆこう」の機能性について | 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 代謝栄養学分野 講師 | ||
| 堤 理恵 | |||
| 徳島県における香酸かんきつ類の産地新香について | 徳島県 農林水産部 もうかるブランド推進課 課長補佐 | ||
| 德永 忠士 | |||
| 沖縄シークヮーサーのブランド化と地域振興 | 沖縄ハム総合食品(株) 代表取締役社長 | ||
| 長濱 徳勝 | |||
| 木頭ゆずをめぐる『柚冬庵』の取り組み | 地域特産物マイスター(木頭ゆず) (有)柚冬庵 代表取締役 | ||
| 榊野 瑞恵 | |||
| 平成29年度 | |||
| もち麦(高β-グルカン大麦)の健康機能性 | 大妻女子大学 家政学部 学部長 食物学科 教授 | ||
| 青江 誠一郎 | |||
| もち麦(高β-グルカン大麦)新品種の開発状況と普及の展望 | 農研機構 西日本農業研究センター 作物開発利用研究領域 畑作物育種グループ |
||
| 吉岡 藤治 | |||
| もち麦による加工食品開発への取り組み | (株)はくばく 市場戦略本部 開発部 部長 | ||
| 小林 敏樹 | |||
| もち麦の栽培・加工と産地育成への取り組み | 地域特産物マイスター(もち麦(米澤モチ2号)) | ||
| 植岡 朝一 | |||
| 地域特産物マイスター(もち麦(加工)) | |||
| 植岡 洋子 | |||
| 平成28年度 | |||
| 農林水産省等における機能性食品に関する研究開発等の 取組について |
農林水産技術会議事務局研究調整官 | ||
| 池田 英貴 | |||
| ヤマイモ成分による健康増進効果 | 静岡県立大学 食品栄養科学部准 教授 | ||
| 三好 規之 | |||
| ヤマイモ類の生態特性と栽培技術等について | 秋田県立大学生物資源科学部准教授 | ||
| 吉田 康徳 | |||
| 自然薯栽培(北茨城方式)の現状と課題 | 地域特産物マイスター(自然薯) | ||
| 山縣 繁一 | |||
| 平成27年度 | |||
| 地域特産物の生産・流通の現状と課題 | 農林水産省生産局地域対策官 | ||
| 栗原 眞 | |||
| ネギの免疫活性化作用 | 野菜茶業研究所野菜病害虫・品質研究領域主任研究員 | ||
| 上田 浩史 | |||
| 岩津ねぎの栽培の現状と産地振興への取り組み | 地域特産物マイスター(岩津ねぎ) | ||
| 田中 務 | |||
| ヤマブドウの機能性成分と産業利用 | 岩手県工業技術センター理事兼連携推進監 | ||
| 小浜 恵子 | |||
| 岩手県久慈地方のヤマブドウ栽培の現状と課題 | 地域特産物マイスター(ヤマブドウ) | ||
| 下河原 重雄 | |||
| 平成26年度 | |||
| 地域特産物の生産・流通の現状と課題 | 農林水産省 生産局 農産部 地域作物課 地域対策官 | ||
| 白井 正人 | |||
| レンコンの機能性研究とその利用 | 佐賀県工業技術センター 食品工業部 特別研究員 | ||
| 鶴田 裕美 | |||
| いばらきレンコンの新品種開発と栽培の現状 | 地域特産物マイスター(レンコン) | ||
| 上田 稔 | |||
| 薬用植物資源研究センターにおける薬用植物研究の 現状と今後の展望 |
(独)医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター長 | ||
| 川原 信夫 | |||
| 北海道薬用作物の来歴及び栽培の実態と利活用 | 地域特産物マイスター(薬用作物) | ||
| 古木 益夫 | |||
| 平成25年度 | |||
| 地域特産物に係わる研究開発と産地化の現状と課題 | 農研機構作物研究所上席研究員 | ||
| 大潟 直樹 | |||
| 新需要を喚起するソバ新品種の育成 | 農研機構九州沖縄農業研究センター専門員 | ||
| 手塚 隆久 | |||
| 春播ソバ新産地における6次産業化の取り組み | 大分県 豊後高田市 農林振興課 地域特産係長 | ||
| 西原 幹雄 | |||
| 地方伝統野菜の個性の見直しと地域活性化 | 山形大学 農学部 食料生命環境学科 准教授 | ||
| 江頭 宏昌 | |||
| 加賀野菜の産地の現状と課題 | 地域特産物マイスター(加賀野菜) | ||
| 米林 利榮 | |||
| 平成24年度 | |||
| 我が国の特産農産物の生産・流通の現状と課題 | 農林水産省 生産局 農産部 地域作物課 工芸係長 | ||
| 石原 孝司 | |||
| ハトムギの持つ機能性と我が国の栽培の現状 | 九州・沖縄農業研究センター 専門員 | ||
| 手塚 隆久 | |||
| ハトムギの産地育成の現状と課題 | 富山県いなばハトムギ生産組合長 | ||
| 和田 俊信 | |||
| 特産果実等の持つ機能性について | 宮城大学食産業学部教授 | ||
| 津志田 藤二郎 | |||
| ブルーベリーの産地化の現状と課題 | 地域特産物マイスター(ブルーベリー) | ||
| 鈴木 太美雄 | |||
| 平成23年度 | |||
| 地域特産物における病害虫防除対策について | 農林水産省 消費・安全局 植物防疫課 課長補佐 | ||
| 黒谷 博史 | |||
| なたねの持つ機能性と新品種育成の現状 | 東北農業研究センター 上席研究員 | ||
| 本田 裕 | |||
| なたねの生産・流通の現状と課題 | 北海道たきかわナタネ生産組合長 | ||
| 宮井 誠一 | |||
| 茶の持つ機能性と新品種育成の現状 | 野菜茶業研究所 茶品質・機能性研究ブループ長 | ||
| 山本(前田)万里 | |||
| 茶の生産・流通の現状と課題 | 地域特産物マイスター(手もみ茶) | ||
| 中森 慰 | |||
| 平成22年度 | |||
| 地域特産物の生産・流通の現状と生産振興上の課題 | 農林水産省 特産農産物対策室長 | ||
| 春日 健二 | |||
| 生薬・薬用作物の生産・流通の現状と国内生産に望むもの | 日本漢方生薬製剤協会 生薬委員長 | ||
| 浅間 宏志 | |||
| 生薬栽培の現状と課題 | 地域特産物マイスター(高知県) | ||
| 片岡 継雄 | |||
| 新たに育成されたゴマ3品種の機能性と栽培特性 | 農研機構作物研究所 | ||
| 大潟 直樹 | |||
| ゴマの契約栽培の現状と課題 | 地域特産物マイスター(鹿児島県) | ||
| 和田 久輝 | |||
| 平成21年度 | |||
| 紅花の機能性 | 東北公益文科大学 教授 | ||
| 平松 緑 | |||
| 生薬栽培の取組 | (株)ツムラ 生薬本部 生薬研究部長 | ||
| 武田 修己 | |||
| 生薬契約栽培の取組 | 群馬県沼田市 | ||
| 山野 善正 | |||
| 平成20年度 | |||
| おいしさの科学 | おいしさの科学研究所 理事長(元香川大学教授) | ||
| 山野 善正 | |||
| 落花生の機能性 | 女子栄養大学 准教授 | ||
| 根岸 由紀子 | |||
| 落花生の生産・流通等 | 千葉県 富里市農業協同組合長 | ||
| 根本 実 | |||
| えごまの機能性 | 郡山女子大学 准教授 | ||
| 平山 美穂子 | |||
| 平成21年度 | |||
| 紅花の機能性 | 東北公益文科大学 教授 | ||
| 平松 緑 | |||
| 生薬栽培の取組 | (株)ツムラ 生薬本部 生薬研究部長 | ||
| 武田 修己 | |||
| 生薬契約栽培の取組 | 群馬県沼田市 | ||
| 山野 善正 | |||
| 平成19年度 | |||
| 黒大豆の機能性 | (株)菊池マイクロテクノロジー研究所 (元 食品総合研究所室長) |
||
| 菊池 祐二 | |||
| 黒大豆の生産・流通 | (株)菊池食品工業 代表取締役 | ||
| 菊池 幸 | |||
| いぐさ・畳の機能性 | 北九州市立大学 准教授 | ||
| 森田 洋 | |||
| 畳の生活と癒し | 全国畳事業協同組合理事長 | ||
| 増田 勇 | |||
| 平成18年度 | |||
| ウコンの研究と健康機能性 | 琉球大学助教授(バングラデッシュ国出身) | ||
| モハメド アムザド ホサイン | |||
| 有色ばれいしょの研究と健康機能性 | 北海道農業研究センター ばれいしょ栽培技術研究チーム長 |
||
| 森 元幸 | |||
| 有色ばれいしょの生産振興と製品の販売戦略 | 北海道芽室町 武田農場代表 | ||
| 武田 幸夫 | |||
| 平成19年度 | |||
| 黒大豆の機能性 | (株)菊池マイクロテクノロジー研究所 (元 食品総合研究所室長) |
||
| 菊池 祐二 | |||
| 黒大豆の生産・流通 | (株)菊池食品工業 代表取締役 | ||
| 菊池 幸 | |||
| いぐさ・畳の機能性 | 北九州市立大学 准教授 | ||
| 森田 洋 | |||
| 畳の生活と癒し | 全国畳事業協同組合理事長 | ||
| 増田 勇 | |||
| 平成17年度 | |||
| アマランサスの研究と健康機能性 | (独)作物研究所資源作物研究室長 | ||
| 勝田 真澄 | |||
| アマランサスの栽培と製品の販売戦略 | 岩手県軽米町 尾田川農園代表 | ||
| 尾田川 勝雄 | |||
| ゆずを中心とした柑橘の研究機能性 | 高知大学 農学部 教授 | ||
| 沢村 正義 | |||
| ゆずの生産振興と製品の販売戦略 | 高知県 馬路村農業協同組合 代表理事専務 | ||
| 東谷 望史 | |||
| 平成16年度 | |||
| 茶とブルーベリーを中心にした特産農産物の持つ 健康機能性 |
(独)食品総合研究所食品機能部長 | ||
| 津志田 藤二郎 | |||
| 花粉症に朗報「べにふうき」緑茶の開発とその効用 | (独)農業・生研機構野菜茶業研究所 機能解析部 茶機能解析研究室長 |
||
| 山本 万里 | |||
| 抗アレルギー茶「べにふうき」の導入と今後の展望 | 鹿児島県 茶業試験場 加工研究室長 | ||
| 佐藤 昭一 | |||
| ブルーベリーの国内生産振興とその利用 | 日本ブルーベリー協会 副会長 | ||
| 玉田 孝人 | |||
| ブルーベリーによる地域おこしと特産品開発 | <能登半島ふれあいの里柳田村> (財)ふれあいの里公社モデル工場長 |
||
| 田原 義昭 | |||
| 平成15年度 | |||
| ひまわりの持つ健康機能性とその利用 | 北海道東海大学教授 | ||
| 西村 弘行 | |||
| ひまわりの品種開発と新しい用途開発の動向 | (独)農研機構 北海道農業研究センター 畑作研究部 遺伝資源利用研究室長 |
||
| 本田 裕 | |||
| ひまわりによる特産品開発と地域おこし | 兵庫県南光町長 | ||
| 山田 兼三 | |||
| 高機能性成分を含むそば優良品種の育成と国内生産 | 筑波大学農林学系助教授 | ||
| 大澤 良 | |||
| そばの健康機能性とその利用 | 長野県食品工業試験場食品開発部主任研究員 | ||
| 大日向 洋 | |||
| 「蕎麦の里 猪苗代」の実現に向けて | (財)福島県猪苗代町 振興公社総務課長 | ||
| 関澤 好春 | |||
| 平成14年度 | |||
| 有色さつまいもの健康機能性と育種の現状 | (独)農業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター 畑作研究部長 |
||
| 山川 理 | |||
| 有色さつまいもの加工品開発による特産地の形成 | (社)宮崎県JA食品開発研究所長 | ||
| 杉田 浩一 | |||
| 紫いもの導入によるさつまいも産地の振興 | 鹿児島県南さつま農協枕崎支所 経済課 | ||
| 山崎 哲也 | |||
| ハーブの持つアレロパシーの景観管理の利用 | (独)農業環境技術研究所 生物環境安全部 研究リーダー | ||
| 藤井 義晴 | |||
| 水田畦畔にハーブの香りを! <安全と環境にやさしい農業を求めて> |
岩手県大船渡農業改良普及センター 主任 | ||
| 及川 しげ子 | |||
| ハーブを生かした地域の環境づくり | NPO法人ジャパンハーブソサエティー (地域特産物マイスター12年度認定) |
||
| 髙橋 良孝 | |||
| 平成13年度 | |||
| ヤーコンの生産振興と健康機能性について | (独)農業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センター 特産農作物資源研究室長 |
||
| 中西 建夫 | |||
| (コメント) | 陸前高田地域振興(株)常務取締役事業本部長 | ||
| 實吉 義正 | |||
| 健康機能性の角度から見たゴマの国内生産の振興及び用途開発等について | 茨城県笠間地域農業改良普及センター主査兼園芸課長 | ||
| 青木 才生 | |||
| (コメント) | (独)農業技術研究機構作物研究所 畑作物研究部 資源作物育種研究室長 | ||
| 勝田 真澄 | |||
| 国産生薬の生産と国内需給・将来見通しについて | 前国立医薬品食品衛生研究所 生薬部長 | ||
| 佐竹 元吉 | |||
| (コメント) | 国産生薬株式会社 代表取締役 (地域特産物マイスター12年度認定) |
||
| 白井 義数 | |||
注:平成14年度までは、地域特産農業情報交流会議専門部会(特産農作物セミナー)として実施。