�@�@��w�ƒn�� �@���֘A�i�G�b�Z�C���j�����@ �@�s�n�o
�P, ��w�ƒn���̏o� �i�a����w1997�`2001�j�����i�ʃy�[�W�j
�i�P�j�@�n��A�Љ�ɊJ���ꂽ��w�Ƃ́@�@ �@�@
�@�@�@�@�@�|�a����w���������������w������k�x �@1997�N
�i�Q�j�@�n��̐l�Ԕ��B�Ƒ�w�̏o��|�O�̃V���|�W�E���E���
�@�@�@�@�@�@�[�a����w�l�ԊW�w���I�v�E��T���@2001�N
�i�R�j�@��w���J�����Ƃ̈Ӗ��[�c�����j�w��w�g���^���̗��j�I�����x��ʂ���
�@�@�@�@�@�@�[�a����w�l�ԊW�w���I�v�E��T���@2001�N
�i4�j ��w�ƒn��̏o��E�E�E���f���a����w17�@�@�@�@�@
�@�@ �@�@�@�@�[���C�������猤�����w��w�Ƌ���x��31���i2002�N�j
(5)�@����Ƃ̏o��A�����Ĉړ���w�@�a����w�w�G�X�L�X�x�i1998�N�j����
�U,�@���ь������L�^�E�[�~(�v���[�~)�� �i�{�y�[�W�E���f�j �@�@�@�@�@
�i�P�j �����w�|��w�i�P�`10�j�@�@�i�Q�j�@�a����w�i11�`20�j

�������w�|��w�E������u���₫�ʂ�v������i20060524�j
�y�ڎ��z
�������w�|��w��
�P, �������̑ٓ��E�Ԃ��炫�n�߂��I�i�u���₫������v�Ȃǁ@1987�`�j
�Q�C�Љ�猤�����O�j�|�[�~�̋�ԁA�Ȑ܂̂���݂̋L�^ �i�����w�|��w�A1996�j
�R�C��������n��w�E�w���̍ĕҖ��ƎЉ��@���P�`�R �i�u�����ق̕��v�@2002�j
�S�C�ҏ��̎厖�u�K���ӂ肩����|�����w�|��w�Љ��厖�u�K�̎��݁i1984�j
�T�C���A�Q�O�N���}���闷�i�����w�|��w�E�Љ��[�~����K��c�W�A1992�N�j
�U�C���I�ɖʔ���������Ԃ��i�����w�|��w�Љ�猤�����u���₫�ʐM�v1993�N12���j
�V�C�����w�|��w�u�Љ�牉�K�v�[�~�W�E�܂��������i���W�A1991�`1994�N�j
�W�C�����̎������H�P�X�X�Q������}�b�v�����|�Ȃ��߂̊����������i�ʃy�[�W�j�@�@
�@ �@ (�����w�|��w�Љ�猤���� 1992�N�j
�@ �E�����̎������H�|�X�Q�N����X�S�N�ցE��O�������}�b�v������
�@�@(�����w�|��w�Љ�猤�����w�����̎������H�E1994�x�i1995�N�j
�X�C���A�W�A�̎Љ��E���l����@���i���_�j�����i�ʃy�[�W�j
�@�@�@�E�����w�|��w�Љ�猤����
10, �t�̍��ƏH�̟O�Ɓ|�v���o�͂����i�����w�|��w�L�����p�X�ʐM�A1995�N3���j
�@ �@�����J�̗��j���@��I�i�u���J�v�n���R�O�N�p���t�A�P�X�X�Q�j ��z64 �����i�ʃy�[�W�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
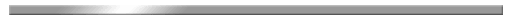
���a����w��
�P�P�C�P�X�X�T�N�x�E�v���[�~�D�u�n��Ɛ��U�w�K�v���ӂ肩����
�@(���уv���[�~�W�A1996�N2��)
�P�Q�C1998�N�̐V���������Ƙa���[�~�̉ۑ�i���у[�~�W�A1999�N1���j
1�R�A1998���уv���[�~���I����ā@�i�[�~�W�E1999�N1���j
�P�S�C ���������傤�ł��i�s����ΌZ��j�a����w�E���уv���[�~
�@�@�@���ꍇ�h�W(�P�X�X9�N1��)
�P�T�C�w�����g�ɂ���̓I�ȃJ���L�������Â���́u�Θb�v�i�a����w�A2000�j
�P�U�C��w�ƒn��ƁA����Ɠ��A�W�A�� �[���̃[�~�i�[��
�@�@�i�a����w�w���� ��253�A1999�N9���j
�P�V�C�n��Ƒ�w�̏o��i���C�������猤�����w��w�Ƌ���x��31��2002�N�j
�P�W�C�a����w�A�킪�g�t�h�i�a����w�l�ԊW�w���I�v��6���A2002�N�j
�P�X�C�Ō�̃v���[�~�u�n�������A�n��ׂ�v
�@�@�i�a����w�E���уv���[�~�W�A�@2002�N�P���j
20�C��w�ƒn��A��w��n��ɊJ�����Ɓi�a����w�E���J�u�����j�����i�ʃy�[�W�j
�Q1�C�a����w�v���[�~�E�t�C�[���h���[�N�L�^�i�ʐ^�A1995�`2002�j�����i�ʃy�[�W�j
���a����w�u�Ō�̃v���[�~�v���i �i��w�v���n�u���h���A2001�N5��10���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
![]()
�������w�|��w��
�P�C�������̑ٓ��E�Ԃ��炫�n�߂��I
�@�@�@�[1980�N��u���₫������v�Ȃ� �i���ъ�e���j
�@�͂��߂��E�E�E�ŋ߁A����܂ł̂����ȋL�����������Ă�������������A�L�^���܂Ƃ߂Ă������Ƃ����w�͂��n�߂Ă��܂��B�u���v�ʐM�E�܁X�̋L�^�i�ԓ����j�������Ă���1998�N�ȍ~�͂܂����v�B����������ȑO�́A���Ƃ��Γ����w�|��w����̋L�\�́i�Ғ����E�_�����͕ʂɂ��āj�A�Ό��̌o�߂̂Ȃ��ŎU��E�����������B�����O�ɓ����̎����Ԃ�̂Ȃ�����A�u���₫������v(1���`10���A1986�`1993�N�j���B���̒��ɁA�Y��Ă��������ȕ��͂R�_������܂����B���̋@��Ɂu���v�ɍĘ^���Ă������Ƃɂ��܂��B�܂��O��̂Ȃ���ɂ��āA�u���₫��v�u�Љ�猤�����j���[�X�v�Ȃǂ̌o�߂��������ꕶ�����^���Ă����܂��B
�i�����F��̕�4193���A2020�N10��20���j
�i�P�j�u�����w�|��w�g���v�h�̂��Ɓv�i�ʐM�u���₫�v��2�� 1987�N8��20���j
�@�N�Ɉ�x�ł��悢����A�w�Z����ȊO�̓��i��Ƃ��ĎЉ��j�ɐi���Ɛ��̏W�܂�����Ƃ��A�Ƃ������ƂɂȂ��āu���₫��v�����������B���ꂩ��O�N�ɂȂ�B�i���F1984�N�Љ��厖�u�K�A85�N�u���₫��v�����j
�@�K����Ȃ���A������Ƃ����g�D������킯�ł��Ȃ��A�����A������荇���i�s�[����?�j���낪���邾���A�Ƃ������ȒP�ȏW���ł��邪�A�Ȃ�Ƃ͂Ȃ��̒��Ԉӎ����萶���Ă��āA���N���W�܂�����Ƃ��Ƃ������ƂɂȂ����B�L����Ƃ��B�Ƃ���ł��̂P�N�A�w�|��w�͊w�Z����ȊO�̓���V�����J�邽�߂́u�V�ے��v�ݒu�̓w�͂��n�߂Ă���B�����{����w�Ƃ��Ă̐��i��傫���u�]���v�����Y�̔N�ł������B�w�i�ɂ͎����E���k���̋}���Ƌ����A�E�����B�����{���̉ے�����A�w��������R���̂P�u�]���v���āA������[���Ɛ��̈�ʉے���V�����ݒu���悤�A�����킯�ł���B������u�����]�����ʈψ���v��ݒu���Ĉȗ��A��������Ȃ���c���d�˂�ꂽ�B�����Ă̕������Ɏ��āA�[��ɋy�ԋc�_�����x�J��Ԃ��ꂽ���Ƃ��낤�B��㔪���N�x�̊T�Z�v���Ɍ����āA�����Ȃɑ��A�l�ԉȊw�ے��A���ە�������ے��Ȃǎl�ے��̐ݒu�Ă��쐬����A��o���ł���B���ꂪ�ǂ̂悤�ɍ��肳��A�u�V�ے��v�ƂȂ邩�͌��i�K�ł͉��Ƃ������Ȃ����A�Љ��E�}���فE�����ق��邢�̓J�E���Z���[�A���{�ꋳ��A������w���u��U�v����V�����R�[�X���݂����錩�ʂ��������Ȃ��Ă���B�V������w���v��w�i�ɂ��āA�u���₫��v�̑��݈Ӌ`���v���������傫���Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃ��������Ă�������ł���B
�i�Q�j�u�Љ�猤�����E�Ԃ��炫�͂��߂��v�i�u���₫������v���S�@1989�N4��20���j
(1) �w�|��w�L�����p�X�ɁA�X�K���Ă̌��������������āu�Љ�猤�����v���@�\���n�߂��̂�1980�N�B���ꂩ��܂�10�N�ɂ݂��Ȃ����A�ӂ肩�����Ă݂�ƁA���̐��N�Ƃ��ɐV�������������܂�Ă���A���������肾�B���̌������Ŋw�K���̂����������l�������������āA�e�n�Ŋ�����n�߂Ă���B���w���̒��Ԃ��ӂ��A�����E�؍��E��p�ɋA�����ďd�v�Ȏd�����n�߂Ă���B�܂��Ƃ���1987�N����i�@�j�Љ��u�����Ɨ��A88�N����w���V�ے��Ƃ��āu���U����v��U�̊w��30�������w�����B89�N�ɂ́u�����فv��C�S���̈ɓ���N�����������i��C�j�Ƃ��Ē��C�����B�V�����ٓ����B
(2) �Љ���������̑̐��Ƃ��Ă͏��сE���l�̗��X�^�b�t�ƂƂ��ɁA���т���E�i�t���}���ْ��A1987�`1991�N�j�ɂ��������Ƃ�����A�O�����瑽���̔��u�t�̏��͂������������B�N�x�͈قȂ邪�A�r�c�O�i�����s�j�A�����v�A�쑺�P��Y�A�����P�v�A�⊪�v�i�����s�j�A�����i�i�������s�����فj�A�i�����v�i�������s����ψ���j�A���{���i������w�j�A�y�c�F�i�����s�j�A�����A��×C�T�i���m��w�j�A�v�c�M���A���ѐ��v�i�����s�����فj�A����ɑk��Ή��c�O�i������w�j�A���R�G�i����c��w�j�Ȃǂ̊e�����炲�w���������������B���ʂȊ�Ԃꂾ�B�@���E�w�������͂��̕��X���瑽���̎h�����������B�i�O�f�E���сu�Љ�猤�����O�j�v�j
�i�R�j�u����܂łɂȂ����₩�ȁv�����w��w�Љ�猤�����u���₫������v�v��9�@1991�N9��
�@�@�x�����Ă����Љ�猤�����u���₫������v���ĊJ����邱�ƂƂȂ�A����I�ł��B�Ȃ��Ȃ獡�N1991�N�قǎЉ�猤�����̈ٓ����傫���N�́A����܂łɂ��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�V�����V�n�����߂Ĕ�ї����Ă������l�����̓��Â�Ԃ�A��܂��́u�ʐM�v���o���ׂ����A�Ǝv���Ă�������ł��B
�@1991�N�ɏC�m�_�����o�����̂́A���c����A�Ӌ��q(�������w���j�A�S�p�i���j�A�X�c�͂�݁A�̂S�l�B���ꂼ��ɗ͍�ł����B�����ĂS�l�Ƃ��i���������ƂɁj�������𑃗����āA�V�����d�����n�߂܂����B�S�p����͂��܃A�����J�ɍݏZ�B
�@�܂����̂S���ɂ́A���A�W�A����̌��������R�l�V�����Q�����Ă��܂����B��������̕������i�����ȁj�A�ьb���i��C�s�j�B�����Ċ؍�����̋����i�i���R�j�A���{�̏��R�r�q�i�H��s�A���ƒ��w�Z���t�j�̊F����ł��B�܂��w�Z�o�c�u�������̑�k����̌������A�����ԁi���E�̏��w�Z�Z���j�͎����I�Ɏ������̌����������ɍ������Ă��܂��B
�@�ɂ��₩�ȐV��ӁB���w�����ʃ[�~���A�W�A�E�t�H�[�������O���ɂ̂�A�ꋴ��w��w�@�̕��F�i�i�؍��j�A�}�C���[�T�i�������S���j���Q�����āA���T��ጤ��������ɊJ�����悤�ɂȂ�܂����B����
�@�w���̐��U�����U�̊w���𒆐S�ɁA(1)�Љ�玩��[�~�[�R�N�����S�A(2)P,�t���C��������[�S�N�����S�A(3)�Љ�����[�~�i1�A2�N�����S�j�������Ɏn�����Ă��܂��B�w�O�̌����҂��Q������u����Љ�猤����v��15�N�ڂ��}���ĒʎZ111��ڂ̒�ጤ����i8��15���j���J����܂����B����܂łɂȂ����₩�Ȍ������̑̐��A�����ĉ���Љ�猤����̌�������[���āA���̐��ʂ́E�E�E����̂��y���݁B
�i�S�j�Љ��E���U�w�K�֘A���ƉȖځi��w�@���܂ށj�J�o�߁i�����j
�@�����w�|��w�E�w���J���L�������Ɂu�Љ��_�v���o�ꂷ��̂�1967�N�A��w�@�i�w�Z�o�c�u���j�u�Љ����u�v�̊J�u��1981�N�B�Љ��厖���i�֘A�Ȗڂ̊J�u��1979�N�[���̎���������u�t�̔�d���傫���Ȃ����B����ɑ�w�@�Ɂu�Љ��v�u�����Ɨ��J�݂��ꂽ�̂�1987�N�̂��ƁB
�@�����ċ����{����w�̑傫�ȉ��v�Ƃ��āi�w�i�ɋ}���Ȏ������k���̌����j�A����n�i�����{���j�Ƌ��{�n�i������[���ƃR�[�X�j���݂����A��҂Ɂu���U����v��U���X�^�[�g�����̂�1988�N�B����U�́A�Љ��E�}���فE�����ق̂R��C���琬��i���30�l�j�A��C�X�^�b�t�ɂ��e���E���i�擾�ɕK�v�Ȋ֘A�Ȗڂ��J�u�����悤�ɂȂ����B�Ƃ��ɔ����يw�E��C������z�u�����͍̂�����w�Ƃ��ď��߂ẴP�[�X�ƂȂ����B
![]()
�Q�C�Љ�猤�����O�j�|�[�~�̋�ԁA�Ȑ܂̂���݂̋L�^�|�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�������w�|��w����w�ȁu����w�����N��v��15���i1996�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�͂��߂Ɂ|�Q�W�N�ƂP�N���܂�
�@���������w�|��w�ɕ��C�����̂�1967�N�S���ł���B��B��������z���ו��������œ����ɂ��ǂ�����Ƃ��A�X�͔��Z���E�v�V�s�m���I���̐^�������ł������B�����̎O�����͌������s�s���A�ߖ����̔g�ɐ���Ă����B���̂Ȃ��ŏZ���i�������Z��͗p�ӂ���Ȃ������j�Ǝq�ǂ��̕ۈ珊�T���ɒǂ��A�I���Ƃ��d�Ȃ��āA�����ƍ����̕��i�ɔ��ʂĂ��o���ł������B��w�͂܂������R���ɂ����Ȃ�c���A�b���قQ�K�̂��܂��������͑������A���ׂ̗�̎��v���̉��ɂ�������w�t���}���قɂ͓�������ׂ��{���Ȃ������B����͍������A�I������������A������B�ɋA�낤�A�Əo�҂��̐S���Ɋׂ������Ƃ��v���o���B���̔N�A�t�Ȃ̂ɍ��̉Ԃ̋L���͂܂������c���Ă��Ȃ��B
�@���������ʓI�ɂ�1995�N�R����N�܂ŁA28�N�Ԃ������w�|��w�ɂ����b�ɂȂ������ƂɂȂ�B�l���Ƃ͕�����Ȃ����̂��B��B�����h�����̂��Ă����̂ɁA�̋��͂邩�ɉ�������A�ً��E���������̂܂ɂ��I�̏Z���ɂȂ����B�Ƃ��ɍ��܁A��Y�A���l�ȂǐD��܂��Ȃ���A�������Y�ꂪ�������т�����A�Ȃɂ����Ⴂ�l�����Ƃ̑����̏o����������B�w��28�N�͎��̑s�N�E���N�̂��ׂāA���̊ԂɎ����̐��U�̃e�|�}�Ɠ����͑�ɂ����Č�����ꂽ�悤�Ȃ��̂��B�U�肩�����Ă݂āA�܂��͓����w�|��w�̊F�l�ɐ[�����ӂ�\�������˂Ȃ�ʁB
�@��N�R���A�ފ��ɂ������čŏI�u�`�̋@���p�ӂ��Ă����������B�u�Љ��ւ̗��|�w�傩�牫��A���A�W�A�ցv�Ƒ肵�āA���̐ق����݂Ƃ������̊��S���q�ׂ邱�Ƃ��ł����B���ꂩ�炷�łɂP�N���܂肪�o�߂��Ă���B���ܘ_�e�����߂��Đ����̂Ƃ���˘f���Ă���B�P�N�o�ƁA���������Ƃɒ�N���^�C���|�̐S���͂ǂ����ɏ����Ă��܂��āA�I��́u�L�O�_�e�v�Ȃǂ��������C���ł͂Ȃ��B������20�`30�����x�炵���B���������邾�낤�B�܂����̌��������͏I�����Ă��Ȃ��A�U��Ԃ�̂łȂ��V����������肠�������A�ŏI�u�`�ł��u���͂��܈�I���A�܂��V�����n�܂�v�Ƃ������߂����肾�A�Ƃ��ɐɕʂ̕K�v���Ȃ��A�ȂǂƎv���߂��炵�ĕM�͂��܂�i�݂������Ȃ��B
�@�ŏI�u�`�̋L�^�͍K���ɉ����P��i1983�N�E��w�@�C���A�ȉ��h�̗��j���e�|�v�N�������āw���A�W�A�Љ�猤���x�i�n�����ATOAFAEC���s�A1996�N�j�Ɏ��^����Ă���B�� �����������瑃�������F�����̋��͂ɂ���ā��ފ��L�O���w�n��ƎЉ��̑n���x�i���{���A���ѕ����A���i�O�ҁA�G�C�f���������A1995�N�j���㈲���ꂽ�B���̂Ԃ�������Ȍ����̋O�ՁA�����₩�ȉۑ�ӎ��ɂ��Ă��A���̖{�̋������M�ҁi20���j�����ɂ���āA���܂��܌`�������Ȃ��狤�L���ꔭ�W����Ă��邱�Ƃ����������B����ɉ��������邱�Ƃ����낤�B
�@���������������̋���w�N��ҏW�ψ���̂��D�ӂ��B����ɂȂ��Ă͂Ȃ�ʁB���̋@����������ē����w�|��w�E�Љ�猤�����E�O�j�̂悤�Ȃ��̂������c���Ă݂����Ǝv���������B�L�����z�����Ό��ƂƂ��ɕ������Ă����A�Z���ŏI�u�`�ł͐G�꓾�Ȃ��������Ƃ�����A�u�������v�ɂ������o�����̊�����L�^���Ă������Ƃő����̃��b�Z�|�W�ɂ͂Ȃ�̂����m��Ȃ��Ɓ|�B�����N���̌���E���Ȃǂ���A���w�E���������A�ʂ̋@��ɏC�������Ă����������Ƃł������������������B���킹�čŏI�u�`�̋L�^����������������K���ł���B
1,�@�����{����w�̂Ȃ��̋�Y
�@1967�N�ɓ����w�|��w������̈���ɂȂ��ď��߂ĉ�c�ɏo���Ƃ��̈�a���i�̈�ق�250�l�O�オ�Ȃɂ��j�͑����Ȃ��̂ł������B�}�C�N�̐��͂悭�����Ƃ�Ȃ��B�قƂ� �ǎ��R�Ȕ����̕��͋C�͂Ȃ��B����ɏے������悤�ȋ����{����w���L�̑̎��A�Ȃ��Ȃ��Ȃ��߂Ȃ��������������B
�@�V�����d�����n�߂��w�̃J���L�������ɂ͂���Ȃ�̊��҂Ƌ�������������̂��B�������������Ă܂��������]�����B���̓����́g���S�h�ɂӂӂƗN�������Ȃ�̖����ӎ���^��͍��ł��N��ɋL�����Ă���B���������ۂɂ͂��̌サ�����ɓݖ����Ă����B���̌��28�N�A�O���͋�������c����Ȃǂł��Ȃ蔭�����������A�㔼�͒��߂Ɏ���������ς���A�܂��Ǘ��E�i�w�������A�t���}���ْ��j�ɑI��Ă��܂��Ƃ���������d�Ȃ��āA�K�v�ȏ�̔����͍T����悤�ɂȂ����B����ƑӑāA�Ǘ��E���Ƒ����ʼn���Ȃǂւ̓����A���̔��Ȃł���B
�@�����w�|��w�̃J���L�������͂��̌�������d�˂Ȃ��玟��ɒE�炵�Ă��Ă���̂ł��낤�B�����������Ă͋��t�͋���̓`���I�ȍ\�����F�Z���c��A�܂����̋����u�Ƌ��@�v���炭��S���A���R�I�𐧂̌����ȂǁA�J���L�������̌Â��A�ł��ə�Ⴕ�Ă����͎̂������ł͂Ȃ����������B
�@���Ƃ��Ύ������C���������A�������鋳��S���ȁi���̌�w�Z����ȁA����������w�Z�����{���ے��j�̃J���L�������ɂ͑��Ƙ_���̐��x���܂��Ȃ��A���K�i�[�~�j�̒P�ʂ��Ȃ��A���ƒP�ʂP30�P�ʂ̂���10�P�ʒ��x�������đ��͂��ׂăN���X�ʂɌŒ肳�ꂽ�K�C���Ƃł������B��w�͕��j�Ƃ��ď��l�������Ƃ��Ă��邽�߁A�����͓����u�`�i���ׂĔ����Q�P�ʁj���א�ŃN���X���ɌJ��Ԃ��A�����Ĕ��͂āA�w���������܂����肵����ŕ����Ă����B
�@���͎���[�~�I�ȓǏ����f���I�Ɏn�߂��B�܂����w�Ȃ̗B��̒S���ȖځE����Љ�w�i�����܂��u�Љ��v�͂Ȃ������j�̃��|�|�g�𑲘_�Ɍ����āA���������������Ō����w�����n�߂��肵���B���������������K�̃[�~�̏W�c���ł��Ȃ��B�w���������[�~�̖ʔ�����m��Ȃ��ő��Ƃ���B���������Ȃ��b���B���ƈ�̓�_�́A�[�~�������Ȃ����������Ȃ����Ƃ��B�J���L�������̂������\�����[�~�̎��R����邳���A�܂��[�~���\�ɂ����Ԃ��Ȃ������B
�@���̎����͒��x�u��w�����v�u�w�������v�̎����Əd�Ȃ�B�����Ɗw���̊W���P���ł͂Ȃ������B�w���̐L�т₩�Ȏ���[�~���A�������Q�����āA�������ƊJ�����悤�ȕ��͋C����͉������̂��������B���������̌������ɂ͎���ɂ����Ȋw�����o���肷��悤�ɂȂ��Ă����B���Ȍn�T�|�N���̊w���������A���̂���1972�N�O�ォ��A�������������E�l�`���T�|�N���u���J�v�A���q�ǂ���T�|�N���u���̎q�v�̌ږ⋳�t�ƂȂ�B�܂��w���̂Ȃ��ɂ͓���E���c�u���ɂ��Ă����������҂�����A�Ή��r������Ċ؍���g�قɔ݁A�ߕ߂��ꂽ���q�w���������B�w�����b�g�g�����ł͂Ȃ��A����ƑR���鎩����n�̊����Ƃ����āA�������Ŕ����킹�����đ吺�Ř_�����邱�Ƃ��������B�K���Ɋw���Ԃ̂�������Q�o�͂Ȃ������B�ߌ��h�w���Ƃ̖Y�ꂪ�����G�s�\�|�h�����������邪�A����͂܂��ʂ̋@��ɂ��悤�B
�@���܂��������Ōp���I�Ɏ���[�~���s�Ȃ���悤�ɂȂ�̂́A�����������̂��낤�B�悤�₭��w�@�́u����Љ�w�v��S���i������������w�ɓ]�o��A�����́u�w�Z�o�c�v�u���j����悤�ɂȂ�1974�N�ȍ~�A���邢�͉���Љ�猤������n��������1976�N�����肾�낤���B���̍��ɂ͎Љ����e�|�}�ɑ��Ƙ_���i�P�ʂ͂��łɔF�߂��Ă����j���������Ƃ���w���w���������W�܂�悤�ɂȂ�A���_�[�~���J�����悤�ɂȂ��Ă����B�w�N�ɂ���Ă͋���w��U�̑唼�̊w�����W�܂��ď��X���S�I�|�o�|�̔N���������B�Ȃ��������ւ̓������狑�ۂ���w�����������������B
�@���Ȃ݂Ɋw���ŏ��߂đ��Ƙ_���炵�����̂��������͔̂_���Γ��A�i�ː����Ȃ�1970�N���Ƃ̊w�������A��w�@�ŏ��߂ĎЉ����e�|�}�ɏC�m�_�����܂Ƃ߂��̂͐��i�����͊w�Z�o�c�u���A1979�N�C���j�A�܂��u�Љ��v�u���������ɊJ�݂����̂͂������1987�N�A���̍ŏ��̏C�����͊؍�����̗��w���A���c�i�i1989�N�A����N�͑��ƔN�A�ȉ������j�ł������B���܂���l����Ɗu���̊������邪�A�����Ƌ��K�C�A��������Ƌ����`�������Ƃ��鋳���{���J���L�������̂Ȃ��ɎЉ��W�Ȗڂ�����̂͗\�z�ȏ�ɂ����ւ�Ȃ��Ƃł������B�悤�₭�w���J���L�������̂Ȃ��ɎЉ��厖���i�̎��ƉȖڂ��J�u�ł���̂�1979�N����ł������B�Ȑ܂����ǂ����o�߂����邾���ɁA���̂Ȃ��ŎЉ��̃e�|�}��I�����h�̊w�������̂��Ƃ͂��܂ł��Y����Ȃ��B
�@�Ƃ���łb���قQ�K�̌������͑������ł������B�Ƃ��Ɋw���A�@���炪������苒���邩�����ƂȂ�A�����̐쐣�M�b���ɂ͂��������f���������B���̕s���R����E���āA�����������ɂȂ�̂�1980�N�A�X�K������������V�c���ꂽ�Ƃ�����ł���B�������ʂɓƗ������Љ�猤�������^����ꂽ�B���ɂƂ��đҖ]�̃[�~��ԁA28�N�Ԃ̊w�吶���̂Ȃ��ł����Ƃ�����I�Ȃ��Ƃ������B���̕����̎����ɂ́u�Љ��v�u���̎����u���������ɂ������߃t�H�|�}���ɂ͎Љ��u�������v�Ə̂��ꂽ���A���́u�������v�ƌĂ�ł����B�ق�̏����ȋ�Ԃ����A���̌�̃[�~���������̕����ʂ苒�_�ƂȂ����B
�Q�C���������Ђ炭�x�N�g��
�@���m�̂悤�ɎЉ��{�݁i���Ƃ��Ό����فj�_�̂Ȃ��Ɂu���܂��v�u���ړI��ԁv�_������B�s���̎��R�ŁA�C�y�ȁA����I�ȏo��ƌ𗬁A�����ĎQ���I�Ȋ�����Ԃ��ǂ��n�肾�����A�Ƃ������z�̂Ȃ������N����Ă����B���́u�s���v���u�w���v�ɒu�������Ă݂�Ƃǂ��Ȃ邩�B
�@�s���Ɠ����悤�Ɋw�������ɂ��A���R�ȓ���I�ȏo��ƌ𗬁A�����I�ȁu���܂��v���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�܂�ނ���L�����p�X�̂Ȃ��ňĊO�ƌǓƂł���A���������̎��R�ȋ�Ԃ��������A�u�`��[�~����P�Ȃ�q�̂Ɏ~�܂肪�����B�w�������̐ϋɓI�ȎQ�����l���Ă�����ŁA�����Ɗw�K�́u���܂��v�u���ړI��ԁv����̓I�ɍl���Ă݂����A�������͖{�����̂悤�ȋ@�\�𑽖ʓI�ɂ��ׂ��ł͂Ȃ����A����Ȃ��Ƃ�_���������L��������B
�@���ƈ�A�n��ɂ������ĕ��I�ȁi�����j��w���ǂ��s���ɊJ���Ă������Ƃ����ۑ肪����B�Ƃ��Ɂu�Љ�猤�����v�Ƃ��ẮA���̌������ȏ�ɓƎ����_��ɊO���ɊJ���Ă����H�v�������Ă悢�B�Љ��̌����E����@�\�̂Ȃ��Ɉʒu�Â��āA�w���Ǝs�����A�������ƒn�悪�A�����ƌ𗬂��������Ă����悤�ȏ�n�肾���Ă������Ƃ͂ł��Ȃ����B�S�̂Ȃ��ł������܂��Ȃ���ٓ����Ă������ݓI�Ȏv�����A�V�����������ŏ�����̉����邩������Ȃ��A����Ȋ��҂��������B
�@���̎����ɂ���ɐV�����ω����������B���w���̓o��ł���B�����w�|��w�͋����{����w�ł��邪�̂ɁA���w���̎���͂����Ƃ��x�ꂽ�i�����j��w�ł������B�w�������֘A�̉�c�ő���w�Ƃ̔�r�������݂����A�p���������v�����������Ƃ�����B���w���̂��߂̓��ʑI�l���x�������Ȃ������w���ł͍ŋ߂Ɏ���܂łقƂ�Ǘ��w�������Ȃ��������A����ł���w�@�ƌ������ł�1980�N�ォ�痯�w��������Ɋ��������悤�ɂȂ����B�Љ�猤�����ւ̐��K�̗��w���͖p�p�i�i�؍��E�\�E���A1984�N�j���ŏ��ł���B
�@�����������I�ɂ͊ؖ��i�k���A1983�N�j�Ɨ������i��C�A1984�N�j�̓�l�̒����l���������������B��l�Ƃ������ɂ͑���U�̏����ł��������A�Љ�猤�����ɂ悭�o���肵�A���̎���ɂ��p�ɂɗV�тɂ���悤�ɂȂ�A���N�𒆐S�ɂ���������w�K��������ŊJ�����悤�ɂȂ����B����������v����̏����̍���w���͗D�G�Ȑl�����������A���������̂Ȃ��o��ƂȂ����B��p����͏���������Ē����i��k�A1987�N�j���ŏ��̗��w���ł���B���w���͂��̌㑽�l������O�����邪�A�����̐l�����̍D��ۂ��傫���A���ꂪ���݂ł����w���Ƃ����������ƂȂ��Ă���B�G�W�v�g����̗��w���A�~���E�A�|�f���i�J�C����w���A1989�N�j���Y�ꂪ�����B
�@�U�肩����ƐV�����������ɂ́A������J�������ŁA(1)�w���̓����A(2)�n��E�s���̊��ҁA(3)���w���i���A�W�A�j�̎Q���A�̎O�̃x�N�g���������Ă����Ƃ������悤�B�����Ȍ��������B�l��������قǑ����킯�ł͂Ȃ��B���������ʓI�ɂ́u���������Ђ炭�v�Ƃ����\����Nj�����15�N�O��ɂ킽�钧������݂����ƂɂȂ�B
�@�����������̍��̕ǂ����ς��ɔ����{�|�h���f�����Ă����B���܂ł��]���ɂ����₩�����A�}�W�b�N�Łu�Љ�猤�����ł���I�v�̈ē��B����m�q�i�@���A1985�N�H�j�̎����B�����炭10�N�قǂ͏�����邱�ƂȂ��A�L����ʂ�l�����ɂ�������ł��銴���������B���̔��{�|�h�́A1980�N�㖖����90�N��ɂ����āA�����������������ɓ����������ɂ́A���̂悤�Ȉē��i�����A���e�Ȃǁj�����T���邢�͖����Ə����p����A�]�����Ȃ���Ԃł������B
�@�܂��{�|�h�w��Ȃ̘g�ŁA(1)������w�K��i���E�Ηj����A1984�N����95�N�܂Ōp�����ꂽ�j�A(2)�A�W�A�E�t�H�|�����i���w�����ʃ[�~����o���A�Ηj���ߌ�A1989�`95�N�j�����A(3)�u�����Љ��v�ǂމ�i������Q�ؗj���A1992�`95�N�j�A(4)�Љ�����[�~�i�P�`�Q�N�����S�A�Ȃ��Ȃ��O���ɂ̂�Ȃ������j�A(5)�Љ�玩��[�~�i�R�`�S�N�����S�A1991�N�A�̂������Љ��ǂމ�ɍ����j�A(6)�n���O���w�K��i�؍����w�������S�A���N�ŏ��Łj�A����ɗՎ��̂������ŁA���Ƃ���(7)�o�C�t���C����ǂމ�A�u�����^���Ƃ́v�Ǐ���A��Ԓ��w������A���邢�͉f���u���E�v�u�T���|���E�{���x�C�v�u�͟n�v�ȂǁA�Ƃ���������[�~�⏔���̈ē��ȂǁB
�@�ȏ�͊w���A�@�������ė��w���ɊJ���ꂽ�����������ł��邪�A����ɉ����āA(8)����Љ�猤����i1976�N�H��P��A1995�N�܂ŒʎZ128��J�Áj�����A(9)�Љ�痝�_������ �i�������n�a�E�n�f�̊w�K��A1984�`95�N�j�A(10)�O�����Љ��̌Q���i�Վ��J�ÁA�i�����v�A���i���A�����Ύq���Ȃǂ������j�ȂǁA�n��ɊJ���ꂽ������̈ē����������B�������A�����A������Ȃǂ̎s���������Q�������W�����������B�Ő����ɔ����{�|�h�́A�y�����`�����b�Z�|�W���܂߂āA�������肢���ς��ɖ��܂����B���������̃��b�J�|�ɂ͂Ђ����ɕR�������邳��Ă����B
�@�Љ�猤�����ł͂������J���L��������̏��u�`�E�[�~���s�Ȃ���B�܂���c���J���ꂽ�B���w�I�l�̍ۂɂ͖ʐځi���w���Ȃǁj���ɂ��Ȃ�A�_���̌��q����������ōs�Ȃ�ꂽ�B��w�E�������Ƃ��Ă̂���ΐ��K�̋@�\�ł���B
�@���������ꂾ���ł͂Ȃ��A�Ƃ��ɃR���p���A���w���̏t�߂̏j�����A���ꌤ����Ƃ��ẴE�`�i���`�����}����A�܂����u�t���}�⑁�t�̌��������ʂ̏W���ȂǁA�܂��ɑ��ړI�Ɋ��p����Ă����B��������̉̂������������A����̃T���V���������Ƃ�������A�܂��������������B���Ƃ��Ή��������ŏo�������{�сA�������w���ɂ���L�q��A�����S���̓���́A���ꂩ�玝�Q�����G���u�E�~�w�r��q�؊ۏĂ��ȂǁA�v���������肪�Ȃ��B�S�K�������������闿���̍��肪�X�K���������ɂЂ낪��A���X�������Ƃ�������B�����ĈӐ}�I�ɂ�����킯�ł͂Ȃ����A�n�������w���������Ƃ��ɎQ���ł���𗬂̏W�����l����ƁA���R�ɂ�����������̊��ɂȂ�̂��B�Ƃ��Ɏ��R�����ė��G�ɂ��Ȃ肪���Ȍ��������������e�ɋ����Ă������������������ɂ��̋@��ɂ����\�����������B�����ԈႢ�Ȃ��������̓[�~�W�c�́u���܂��v�ƂȂ�A�����̐�����ԂƂȂ��Ă����B
�R�C�Ό��̕����ɍR���ā|�����������̋O��
�@28�N�̕��݂́A�����Ƃ��Č����A�삯���Œʂ蔲�����悤�Ȃ��̂��B�Ƃ���1980�N�ȍ~�̌�����������15�N�́A�����̂��Ƃ�����߂��A�����Z���߂��ŁA�������藎���������d���ɂȂ������ǂ������Ȃ�����B�ŋ߂�10�N�͓��{�l�w�������ނ��뗯�w���ɂ������G�l���M�|�̕��������A�����w�������łȂ��A������̎G���ɒǂ�ꂽ�N���������B
�@���̊ԁA1984�N�͉Ăɕ����ȈϏ��E�Љ��厖�u�K�i�É��A�_�ސ�A���������100 ���Q���j���J����A�܂��H�ɂ͓��{�Љ��w���31�������J�Â����B���ꂼ��L�^���c����Ă��邪�A�������̊w���E�@���̃[�~�W�c�����i�͂ƂȂ����B
�@�������̑̐��Ƃ��Ă͏��сE���l�̗��X�^�b�t�ƂƂ��ɁA�O�����瑽���̔��u�t�̏��͂������������B�N�x�͈قȂ邪�A�r�c�O�A�����v�A�쑺�P��Y�A�����P�v�A�⊪�v�A�����i�A�i�����v�A���{���A�́E�y�c�F�A�����A��×C�T�A�v�c�M���A���ѐ��v�A����ɑk��Ή��c�O�A���R�G�Ȃǂ̊e���i���s���j���炲�w���������������B���ʂȊ�Ԃꂾ�B�@���E�w�������͂��̕��X���瑽���̎h�����������B
�@�ق��ɑ�w�����ꂽ�����́u�������v�Ƃ��ĂP�N�i�Ȃ������N�j���x�A�������ɍݐЂ��ꂽ���X������B�X�R����i�����w�A�����j�A���ѕ����i��������w�j�A�i�A��i�k���t�͑�w�j�A�͈�́i��C�s�Ɨ]��w�j�A����Q�i�����E���Ƌ���ψ���j�A�����@�i�k���t�͑�w�A������������Ĉꎞ���̂݁j�Ȃǂ̏����ł������B�܂����N�u��Ԓ��w�v���e�|�}�Ƃ��Č���c�a���i1985�N���`1994�N�j�A�̂��Ɋ֖{�ۍF���i1991�N�`1994�N�j�ɉ�����Ă��������āA����l�̏o�u�����肢���Ă����B���̊ԁA�����ȍ݊O�����i1986�`1987�N�j�ɂ�艢�Đ��l���璲���ɂł������ہA�p���ɑ؍݂��Ĉȗ��̗F�l�ł���h,Neary���m�i�j���|�E�J�b�X����w�j�������A�������ʼnp���̑�w�G�N�X�e���V�����ɂ��ču�`�����肢���A���e�̋@������������Ƃ�����i1987�N�U���j�B
�@�ȉ��A�����͈̔͂ŁA�������E�O�j�Ƃ��āA�����炭�Ό��̌o�߂ƂƂ��Ɍ�N�Y�ꋎ����ł��낤���Ƃ�����L�^���Ă������Ƃɂ���B�L�����s�m���ȂƂ��������A�C�����ׂ��_������ɈႢ�Ȃ��B�����̌����������o�|�ɂ��w�E����������K���ł���B
�@(1)�̂łÂ錤�����j
�@�������̎Љ�猤���������ɂ��Ă͂���܂łT�x�قǐV�����Ƃ肠���Ă��ꂽ�B�܂��u�����旧�����ي����|����j�Â������{�u���v�ɂ��Ă̒��������i�����A1980�1�26�j�A�����āu��㉫��Љ�猤����v�i�����V��A1983�7�20�j�A�u�[�~�̂͊쐣�����v�i�����A1983�1�4�j�A�u�t�H�|�N�ʼn��ꌤ���v�i�����A1985�12�28�j�A����Ɂu���{ ��w�тƂ萶���̕��L�������|�����w����������v�i�����A1993�1�24�j�ł���B�ق��� ���ьl�̋L���i�u�����ȁ|�E�܂���ԁv�����V��A1995�6�3�A�Ȃǁj�̂Ȃ��Ɍ������̂��Ƃ��G����Ă���B�Ƃ���ŁA���̂����Q�_�͌������E�[�~�̉̂Ɋւ�����̂��B���Ƃ���1983�N�P���S���̒����L���͎��̂悤�ɏ����o���Ă���B
�@�u�����w�|��̏��ѕ��l�����i�Љ��w�j�̌������ɂ̓[�~�́H������B����̃t�H�|�N�̎�A�C�����i���݂��ǁj�L����̊쐣�����i�������j�A�ČR��n�ւ̓������琶�܂ꂽ ����̂ł���B�g���܂̊w���ɂ͎����̉̂��Ȃ��i���j�h�ƒQ���������́A�R���p�ɏo��Ɗw�������Ɂg�����̉̂��������h�Ɣ���B���͗����������|�|�i���j�B����Ɏh������Ă��A���ꌤ���𑱂��Ă��铯�����̌������ɏo���肷��w�������͊쐣�����ɖ������Ă��܂����B�g�쐣�����@�z�͗����ā@�������邱��@�N�͂ǂ��ɂ���̂��@�p���������@���������Ă���@�R�������Ă���@�F�������Ă���@�ꂪ�����Ă���A���Ă�����ł��A�����̂ł���h�Ɠ������B�v
�@�����́A�����Ă̎Љ����H�̂Ȃ��ł��������ꂽ�̂��Љ�猤�����u���Ⴂ�l�����ɂ��`�������A����ȓ��@����A�R���p�̐ȂȂǂʼn���ȉ̂��I���邩�����Ŏn�܂����Ǝv���B�Ƃ��ɂ́u�܂����v�����E��������ʂ����������A���������̊Ԃɂ��A�y�����W��������Ή̂����������Ƃ�������ɂȂ����B�u�t�̐i�����v����̉̏����܂���i�ŁA�����Ō���������Ă����������B�悭���������̂��v���������ƁA�قڎl�̌n���ɐ����ł���悤���B�i�쎌�E��ȎҖ��|���j
�@�@�u�̂����^���v�ɏے������悤�ȎЉ��̌����w�����������������́i�u�Ƃ����сv�u�������v�u�S���킮�t�̉́v�Ȃǂ̃��V�����w�A�u�d���̉́v�u�g���R�̖��v�u����ۂہv�u�Ԃ��Ԕ����ԁv�u�Ȃ����v�u�C���^�|�i�V���i���v�u���ۊw�A�́v�u�����w�|��w�w���́E�ᑐ�����v�Ȃǁj�B�ق��ɂ������������B
�@�A�n�敶���^����ʂ��Č𗬂�����A������ɖ{���������A�܂��������n�a�̔���F��i�U�N�݊w����1980�N���Ɓj���Q�����Ă��錀�c�u�ӂ邳�ƁE������v�̉́i�f��u���E�v�̎��́u�ӂ邳�Ɓv�A�u�����ǂ����Ɂv�u�Ƃ�ɑ���Ȃ��l�������ǁv�u�����͔����ԁv�u�̂Ă�킯�ɂ͂����Ȃ����v�u���t�̉́v�Ȃǁj�B���䌒��i1982�N�j�A����m�q�i�O�o�j�̃R���r���������u�����ǂ����Ɂv�ȂǍ��ł����Ɏc���Ă���B
�@�B����̉́i�u�Ă����ʉԁv�u�m�ԕz�v�u�䂤�Ȃ̉ԁv�u�\��̏t�v�u�������|����܁|�܁|�������v�u�����߁v�u���Ƃ����є��|����킴���v�ȂǁA�C�����L�̉́u�쐣�����v�u�C�̎q��́v�u�����i�����Ƃ�)�v�u�����]�́v�u���Ƃ����т̉ԁv�Ȃǁj�B���c ���q�i�@���A1981�N�j�͈ꎞ���T���V����܈����Ă����B
�@�C�A�W�A�̉́i�����u������́v�u��C�|��̋��v�u���ԍ]��v�u���R���v�u�~�ԁv�ق��A�؍��u�A�`�~�X���i���̘I�j�v�u�{���\���A�i�P��ԁj�v�A�G�W�v�g�u�u���f�B�v�Ȃǁj�B��ɗ��w���ƈꏏ�ɂ��������B
�@���ꂼ�ꂻ�̔N�̎��́A����Ό������̗��s�̂̂悤�Ȃ��̂��������B1990�N��ɓ���ƃJ���I�P�S���ƂȂ�A�������R���p�ł��̂������R�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă������B���͂��̎�������J���I�P���Ή^�����n�߂��B
�@(2)���������h
�@�w���̐��U�����U�V�����̌�x�R���h�͂Ƃ��Ɍ������̎�Âł͂Ȃ��������A��w�@���A�������ɂ�閈�N�P��̌��������h���s�Ȃ�ꂽ�B��Ƃ��đ�w�@�C���҂������ލ��h�����A�n�a�E�n�f���Q������悤�ɂȂ����B����ɑ�w�@�V�������}�̎�|�������悤�ɂȂ��āA1980�N��㔼����͌����������̗��w���i�������j���Q���҂̑唼�����߂�悤�ɂȂ����B��P��́A���߂ĎЉ����e�|�}�ɏC�m�_�����o��������������ōs�Ȃ�ꂽ (1)1979�N�|�����E�����i���ё��A�V�l�Q���j�̍��h�ł���B���N�T���O��Ɋ�悳�ꂽ�B�ȉ��A�N�����̌o�߂̂L���B
�@(2)1980�N�|�ɓ��E�ɓ��i�W�l�|���ʎQ���E���엘�v���j�A(3)1981�N�|�ɓ��E�M��(5�l�j�A(4)1982�N�|�����i10�l�j�A(5)1983�N�|�ɓ��E��ށi�W�l�j�A(6)1984�N�|�����i11�l�j�A(7)1985�N�|�������E���n�i�W�l�j�A(8)1986�N�|�ɓ��E�V��i13�l�j�A(9)1987�N�|�\�����i11�l�j�A(10)1988�N�|������E���q�i13�l)�A(11)1989�N�|�R���E�����i14�l�j�A(12)1990�N�|�O�Y�C�݁i17�l�|���ʎQ���E�X�R���ꎁ�j�A(13)1991�N�|�����i16�l�j�A(14)1992�N�|�R���E�����i18�l�j�A(15)1993�N�|�Q�n�E�n�ǐ�(22�l�|�ē��E�����v��)�A(16)1994�N�|�R���E�����i22�l�j�A(17)1995�N�|�\�����E�x�m���i10�l�j�A���Q�l(18)1996�N�|���{�E���쑺�i12�l�j�B
�@�Ȃ��������̗��s�́A���̍��h�̂ق��ɁA�_�ˎs�u�w�Z�����v�����i1975�N�j�A�R�`���߉��s�����فE���������g���K��i1980�N�j�A��q���鎭���������i1984�N�j�A���쒬�����i1984�N�j�A�Q�n���u�ӂ邳�ƁE������v�����Q���i1987�N�j�Ȃǂ��낢�날�邪�A�����Ƃ����x�Z���ʂ��Â����͉̂���ł������B�u��㉫��Љ�猤����v�̋L�^�ɂ��A1976�N�����J�n����1995�N�R���܂łɉ��꒲���E�K��͂T�R��ɋy�Ԃ��A���̂����唼�͌������Ƃ��Ă̎��g�݂ł���A���̊Ԃɉ@���E�w���i���w�����܂ށj�����ב������̋K�͂ŊԒf�Ȃ�����̒n�B�����̊W�ŏڍׂ͗�����B���ꌤ������ѐ�㉫��Љ�猤����̌o�߂ɂ��ẮA��q�́u����Љ��j���v�S�V�W�i1977�N�`1988�N�j�ɂقږ��炩�ł��邪�A����ȍ~�̓������L�^�Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă����K�v������B
�@(3) �������E�N���s��
�@��N�ފ��ɂ������Ċw�����u�L�����p�X�ʐM�v��157�i1995�3�10�j�ɏ��������Ƃ����A�����������͔N�����d�˂Ă����ߒ��ł��̊Ԃɂ������̔N���s����n�肾�����ƂɂȂ����B�K���Ȃ��ƂɊw��L�����p�X�͎�s����w�̂Ȃ��ł��䂽���A�ԍ炫�ق���A���R�̈ڂ肩���̂����₩�ȑ�w�ł���B�O�̕�����݂�[���͂��Ƃ��悤���Ȃ��������A�܂���̌�����������ăL�����p�X���A�钆�V�ɖ����ł��o�Ă���A�������܂ƈꏏ�ɎႢ���ԂƐl������肽���Ȃ�B����Ȍ��т��̂Ȃ��Ō������i�߂Ă��������A�����ɂȂ肪���Ȍ���������������Ȃ�̖ʔ����A�L�����������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă����B
�@�������̔N���s���Ƃ͎��̂悤�Ȃ��Ƃł������B�S�����{�E�Ԍ��A�T�����{�E���������h�A�U�����{�E���u�t���͂މ�A�V�����{�E���[�̉�A�X���E��ꔪ�i����j�̏W���A10���E�����̉�i�T�|�N���u���J�v�y�сu���̎q�v�ƍ����j�A11���E���ꌤ�����s�A12�����{�E�Y�N��A�P�����{�E���_�����j���A�Q���E�t�߁i���w�����L�q��j�A�R�����{�E���������ʉ�A�ȂǁB
�@�������N�ɂ���ĈႢ������A�܂��\�肵�Ă��Ă��J����Ȃ������s��������B�u�ጩ�̉�v�����͗\���ł��Ȃ��̂ŁA���Ɉ�x���������Ȃ������B
�S�C����������̔��M�|�u�ʐM�v�Ɓu�v
�@(4)���₫��Ɓu���₫�ʐM�v
�@�v�������������Ȃ��w����������i1980�`1984�N�j�A�d���̎�v�����͊Ǘ��I�����I�A����ێ��I�Ȑ��i�̂��̂������������A����ł������V�����d���������L��������B���̈�͎Љ��厖���i�擾�̃J���L���������O���ɂ̂��A���łɊJ�݂���Ă����}���َi�����i�Ƃ��킹�āA�����يw�|�����i�ɕK�v�ȉȖڊJ�݂��n���i�S���u�t�E�̈ɓ����Y���j���������Ƃł���B���̎��{�̂��ߊw������ψ���u�w�|�������i�擾�Ɋւ��錟���ψ���v���g�D���ꂽ�B�ψ���̖����́A�V�������������u�w�|���v�ɂ��Ă͂������A�����{���ȊO�̑��̐��E���i�擾�̂��߂̎��Ƃ���K�A�����Ă��̐i�H��A�E�ɂ��ď������߁A�w���ւ̎w���A�T�|�r�X���J�n���悤�Ƃ����̂ł���B���̎�����w���Ɣ�ׂĂ��̗̈�ɂ��ẮA�����{����w�ł��邪�̂ɑ傫���x����Ƃ��Ă����B
�@�����w�|��w�̓�����g�D���݂�ƁA�����A�E�g�͂�������Ƒg�D���ł��Ă��邪�A����ȊO�̕���ɐi���Ɛ��͓������ɂ��L�ڂ���Ă��Ȃ��B�w��̑��Ɛ��͋��t�̓��ɐi�ނ��̂����|�I�ɑ����������A���̂Ȃ��ŏ����҂ł͂��邪�A�Љ��A�}���َi���A�����يW�A�Љ�̈�A�����فA���̑������{�݂ȂNj����ȊO�̕���Ŏd�������Ă���l����������B��w�Ƃ��Ă͂��߂Ă��̐l�����̒������s���A�ψ���Ƃ��āu�����فE�Љ�瓙�ւ̏A�E�҈ꗗ�v�i��P�������E1984�N�A��Q���E1986�N�j���쐬�����B���̖���u�ꗗ�v�ɂ��ƂÂ��ĊJ�Â����̂��u���₫��v�ł���B
�@���Ɛ��ւ̌Ăт����́A�{���͑�w�S�̂̉ۑ�Ƃ��Ċw���������ۂ����肪�A�E���ƌ��т��Ď��{���Ă��悳���������A�ȒP�ɂ͂����܂Ȃ��B�����ŎЉ�猤�����̃{�����e�B�A�����Ƃ��āA�@���L�u���u�ꗗ�v�L�ڂ̑��Ɛ��Ɉē����o���A�ĂW���A�r�|�������݂��킵�Ȃ��瑊�݂̌𗬂Ə��̌����A���Ɛ��Ɗw���Ƃ̏o��̏W�����������̂ł���B�\�߂��ꂼ��̕���̒��S�I�Ȑl�����ɑ��k���A������܂肵���K�͂ł��������A������ƂȂ����B�܂����N����낤�Ƃ������ƂɂȂ��āA1985�N����1987�N�ɂ����āA�R�N�قǑ������B�������������G���������Ĉӗ~���Ȃ������~���ꂽ�B�����u���y�Y����������B�Љ�猤�����j���|�X�u���₫�ʐM�v�̔��s�ł���B
�@���₫��͐����ɂ́u�����䂯�₫��v�Ə̂����B��P��̔��N�l�́A���ѕ��l�A�y�c�F�A�r�J�O�A���ѐ��v�A�R���^���q�A���c��V�A�����F���̂V�l�A�w����\�̐����F���������A�݂ȎЉ��s���E�{�݁A�}���ٓ��Ŋ��Ă��鑲�Ɛ��ł���B���̏W�����̂ɔ��s���ꂽ�u���₫�v�ʐM�́A��P���i1986�N�W���j�A��Q���i1987�N�W���j�Ƃ��ɓ��c��V�i���͌��s����ψ���Ζ��j���ҏW�E���s�̘J���Ƃ����B�����āA����Ɏh�����ꂽ���̂悤�ɁA���s���āu�Љ�猤�����j���|�X�v���P�i1987�N�S���j�����s����Ă���B������͎O�Y��t�i�@���j�����S�ƂȂ��Ĕ��s�����ƋL�����Ă���B�L�O���ׂ��n����P�ł̋L���̈ꕔ���Ę^���Ă������B1987�N�͌������ɂƂ��Ă������̓_�ŏd�v�ȔN�ł��������Ƃ��킩��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�u�j�I���l�搶�������C�|���̓x�A�S���P���������܂��ĎЉ�猤�����E���l���搶�������ɏ��C����܂����B�������ł͏��ѐ搶�̐}���ْ��A�C�ƕ����ē�d�̊�тł���܂��B���N�x���Ɨ������Љ��u���̒��Ƃ��ĉ@���E�w�������w���������܂��悤���肢�\�������܂��B�i���j����̑�V�W�̔��s�ɂ���āw����Љ��j���x���ꉞ�̊����ƂȂ�܂��B�|���ѕ�������̘J���˂��炤�ƂƂ��Ɂ|�i���j�v�ȂǂȂǁB
�@���̗��j���|�X�͍��̂��邩�����ő�S���i1989�N�S���j���u���₫������i�Љ�猤�����j���|�X�j�v�ƂȂ�A�������w�@�̓��c����A�n�����Y�����ҏW��S�������B���̌�u���₫������v�͇�10�i1993�N12���j�܂Ŕ��s����A���̊ԁA������M��]���W�q�����ҏW�ɂ��������B1980�N��㔼�́u���₫��v�A�u���₫�v�ʐM�͎p���������܂܂ƂȂ��Ă���B
�@�Ȃ��A���N�U�����{�Ɍ��������J���P��̔��u�t���}�̉�ɂ́A�@���E�w�����������ăp���t�u�Љ��W���搶���͂މ�v�i���ԁj���쐬���Ă����B1988�N���1993�N�܂łU���q���c����Ă���B����1990�N�O��ɂ͎Љ�猤����i����[�~�j�u�v���̋L�^���o���ꂽ�B
�@(5)�����ƃ[�~�E���|�|�g�W
�@1990�N��̎Љ�猤�����ɂ́A1988�N�x����w���g�ɂ��V�ے��u���U����v��U�̊w���w��30���i����j�����N���w�i�������Љ��A�}���فA�����ق̂R��C�ɕ�����A�Љ���10�`15���O��j����悤�ɂȂ����B�܂���w�@��87�N�ɎЉ��u���������ɓƗ����A�܂�1992�E93���N�x�́u���U����v�u���ƂQ�{���āi������94�N�x��藼�u���͍��́j�ƂȂ��āA�w���E�@���̐��������A���w�����܂��܂������Ȃ�A���Ȃ�ߖ��Ȑ��������ƂȂ����B�������ʂ͎���n�肾���B90�N��̎Љ�猤�����[�~�����͑��ʂȓW�J���݂����B�O�q�u���₫������v��10�Ɏ��́u���I�ɂ������낢������Ԃ��v�Ƒ肵�Ă��������Ă���B�u�Љ��W�̑�w�E�������Ƃ��ẮA���m�ے��������Ă����w���ӂ��߂āA���F�̂Ȃ����������Ɏ��g��ł��銈���Ȍ������A�Ƃ����Ă悢�̂ł͂Ȃ����낤���B�v
�@�ʌf�́u�Ɛсv�ꗗ�����̂Ȃ��ɋL�ڂ��Ă��铌���w�|��w�Љ�猤�������s�̏������i�u����Љ��j���v�S�V�W�A1977�`1988�N�A�u�����̎������H�E92�v�u�����̎������H�E94�v�A�u���A�W�A�̎Љ��E���l����@���v1993�N�����j�ȊO�ɁA���̂悤�ȃ[�~�W������B�����͏�L�E�������ƈ���āA�������ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�R�s�|�ł�50���O��쐬���āA�W�҂ɔz�z�������̂ł���B����Ό������̎��Ɣłł��邪�A�Љ��[�~�̃����o�|���G�l���M�|���X�������J��ł���A���̎���f���������ꂽ�����W�ƂȂ��Ă��镔�������Ȃ��Ȃ��A�L�^�ɂƂǂ߂Ă������Ƃɂ���B�N�x�ɂ���đ��ق��邪�A�a�T�ŁA150�`200�Œ��x�̓��e�ł���B
�@�ꗗ�ɂ��Ă݂�ƁA���ʓI�ɂ́A1980�`84�N�w�������A1987�`91�N�t���}���ْ��̎d���ɒǂ�ꂽ�N�x�́A�[�~�����܂Ƃ߂�ɂ͎����Ă��Ȃ��B
�@1985�N�u�x���`�̂��钬�[��錧�������Љ�璲���v(1)(2)
�@1986�N�u���ɐ��͋P���Ă��邩�|��Ԓ��w�E�����Ԓ��w�^���̋L�^�v
�@1992�N�u���ւ̒���|1991�N�x�Љ�牉�K���v
�@1993�N�u�����̂Ȃ��Ł|1992�N�x�Љ�牉�K���v
�@1994�N�u�Љ��Ɍ�����|1993�N�Љ�牉�K���v
�@1995�N�u���ѐ搶�ƒ��Ԃ����|1994�N�Љ�牉�K���v
�@���Ƃ���1992�N�������Ă݂�ƁA���̍\���́A���U�w�K�A���U�X�|�|�c�A��Q�ҕ����A������A�O���l�J���҂Ǝ������H�A�q�ǂ��̒n�抈���ƌ������A�T�x�Q�����Ɗw�Z�T�ܓ����A�����T�C�N���^���A�����̎Љ��v��A�N�c�^���A����ƕ��a���A�Ȃǂ̍��ڂ��Ȃ��ł���B���̔N�x�̓����͂��ꂼ�����邪�A��{�Ƃ��Ă͓������i�Ŗ��E���ڂ�ݒ肵�A20�`30�l�O��̃[�~�Q���҂ŕ��S���āA�N�����ɂ��̉ۑ��Nj����A�W�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ���̂ł���B
�@�����̍�ƂɎQ�������F����́A���܂��Ȃ����C���낤���B
�m�NjL1�n
�@���̋@��ɁA(1)�u��㉫��Љ�猤����v�i1976�`95�N�A������128��A����K��E ����53��A�w��\12��A�j�����s�V�W�A�w���O�ƎЉ��x�P���A�����_�������j������A(2)���w�����ʃ[�~�E�Љ��u�A�W�A�E�t�H�|�����v�i1989�`95�N�A�����161��A�����E�؍��E��p���K��13��j�����A(3)�������n�a�E�n�f�ɂ��u�Љ�痝�_������v�ȂǁA�̊����j�N�\���L�^���Ă��������������A�����̊W�ŏȗ������B�܂�����E�����������͂��߁A�e��W��̃r�f�I�A�e�|�v�ȂNjL�^���X�g���ꗗ�ɂ��Ă��������������A������ʂ����Ȃ������B�����͘a����w�Љ�猤�����ɕۑ����Ă���B
�@��L�̎O�̌�����́A1995�N�T���ɍ������A�V������u�����E����E���A�W�A�Љ��t�H�|�����v�iTOAFAEC�FTokyo-Okinawa-east Asia Forum on Adult Edudation and Cultures�j�̂������Ōp�����ĐV�����������n�߂Ă��������B�����L�^�ɂ��ẮA��������ETOAFAEC �ҁw���A�W�A�Љ�猤���x�n�����i�a����w�Љ�猤�����A1996�N�j���Q�Ƃ��ꂽ���B(1996�N�U��20���L)
�m�NjL2�n
![]()
�R�C��������n��w�E�w���̍ĕҖ��ƎЉ��
�@�@�@�@�@�@�@�����сu�����ق̕��v256���`260���A2002�N1��31���`2��12��
�@��������n��w�E�w���̍ĕҖ��ƎЉ��i�P�j�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ق̕�256���@2002�N1��31��
�@���܍�����w���u�\�����v�v�u�Ɨ��s���@�l���v�u���R�v�����v���ő�h��B�����u���v�v�ɂ��Ă���w����̓����I�ȓ����łȂ��A�O���ɑg�ݕ������邩�����Ŏ��Ԃ��i�s���Ă���Ƃ��낪�c�O�I
�@�Ȃ��ł�����ƘA�����ċ���n��w�E����w���̍ĕғ�����肪�}�����Ă���B�u���v�����o�[�̂Ȃ��ɂ��W�҂����Ȃ��Ȃ��A���ܘA���̉�c�E������Ƃɒǂ��đ�ς炵���i�E�E�Ƒ��l���݂����Ő\���킯�Ȃ��A���������Ă͂���������w�ɐg�������Ă����j�B�ނ��덑����w�ĕҖ��́u����w�����ݕ��G���v�i�����V���A�P���Q�X���j�Ȃ̂��B
�@���̊Ԃ̌o�߂ł́A�����Ȋw�Ȃɂ����ꂽ�u�����̋����{����w�E�w���݂̍���Ɋւ��鍧�k��v����N11��24���Ɍ������ʂ����\���A���ȏȂ͋����p���Ŗ{�P�����܂łɉ��炩�́u���g�v�u�����v�u�ĕҁv�̕��������߂Ă���B
�@���ً̋}���Ԃ��āA���{����w��ł́A�N���̂P�Q���Q�S���A�����Łu�����{���n��w�E�w���̍ĕғ������l����v�V���|�W�E���i���}�����Y�E�݂�����ψ��A���{��O�E�{�鋳���w���A�Ȃǁj���J�����B�S���e�n���瑽���̊W�҂��W�܂�A���i�̊w��V���|�W�E���Ɍ����Ȃ��ٔ�������������Ă����B
�@�㏬�����{���w���̍ĕҁE���p���A������������X�N���b�v�E�A���h�E�r���h�̓����A����܂łɂȂ��K�͂ŏ�͐��ڂ�����B��w���݂̌��_���o�Ȃ��ꍇ�́A���ȏȂ��i��w�Ƌ����Łj�Q�O�O�Q�N�x���ɑg�ݍ��킹���m�肳����Ƃ����B�Ƃ��ɋK�͂̏����ȑ�w�̋����{���w���i�n��ƌ��т��ēƎ��̖��������Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��j�̖��^���J������Ă���B
�@�Ƃ���ŁA���̂悤�ȑ�w�u���v�v�̓����́A�����̂̎Љ�������قƂ͒��ڂ̊֘A�͂Ȃ��悤�Ɍ�����B�������낤���H
�@�u�����ق̕��v�ł͐É���w�E�Έ�R���������x��������w�E����w���̉��g����i���Ă����i202��2001�N8��26���A227����11��6���j�B���̖�肪�Ȃ������ق�Љ��Ɗ֘A������̂��A����ȋ^����������̕��������Ƃ������ɈႢ�Ȃ��B���ꂪ�傠��Ȃ̂��B
�@��������n��w�E�w���̍ĕҖ��ƎЉ��i�Q�j
�@�@�@�|�����{���w���ւ̎Љ��̈ʒu�Â� �@�@�@�@�@�����ق̕�257���@2002�N2��4��
�@�����{���w���̃J���L�������ɎЉ��֘A�̎��ƉȖڂ��o�ꂷ��悤�ɂȂ�̂́A�����Â����Ƃł͂Ȃ��B��㔼���I�̂Ȃ��̌㔼�����H�ɂ悤�₭�p�������Ă���B
�@�Ȃ����낤�B�u�����{���v�Ƃ͂������w�Z�́u�����v�{���ł���A����ȊO�́i���Ƃ��ΎЉ��́j������E�͊܂�ł��Ȃ��B���������ƈ���āA�l�����E���q���̎���ł���A�Ƃ��Ɏ�s���Ȃǂł͐V�K�����̊m�ۂ͋}���̉ۑ�ł������B���t�͊w�Z����̑̎����c��A���������{����w�E�w���́A�����́u�v��{���v�{��ɂ����āA�����Ƌ��擾��K�{�Ƃ����J���L��������g�݁A���Ɛ��͂��ׂċ����̓��ɐi�ނ����������R�ƍl�����Ă����B�����Ĕ��ʁA�����{���w���ɂ����鋳��E���Ƌ��@����Ƃ����J���L�������Ґ��́A���w��́u��w�̎����v��傫���鑤�ʂ��������Ƃ�������B
�@���������w�|��w�ɍ̗p�i�P�X�U�V�N�j���ꂽ�̂��A�Љ���U�Ƃ��ĂłȂ��A����Љ�w�̒S���Ƃ��Ăł���A�����ɎЉ��ɂ��Ă��u�`���o����A�Ƃ������R�ł������B���ƒP�ʂP�R�O�P�ʑO��i�Ƌ��@�Ƃ̊W�ŕK�C�Ȗڂ̔�d������߂đ����j�̂Ȃ��́A�Љ��͎��R�I���Ȗځi�킸���Q�P�ʁj�̈�ɉ߂��Ȃ������B����ł����ƉȖڂƂ��Čf����ꂽ���Ǝ��̂͂ނ��뒍�ڂ��ׂ����Ƃł����āA���̎����A�����̋����{���w���ł͂܂��Љ��̉Ȗڂ͈ʒu�Â��Ă��Ȃ��ꍇ�����������Ǝv���B
�@���������āA�Љ��S���҂������{���w���ɂ͂܂��قƂ�ǔz�u����Ă��Ȃ������B���{�Љ��w��̉���Ƃ��ẮA��t��w�ɕ������F�A��㋳���w�ɉF���얞�A�Ȃǂ̐�y���悤�₭�g�U���h�������x�ł������B�������A���̍��ɋ����n�̍�������w���ɎЉ��̍u�����ݒu�i����w�͓��a���炪��݁E�E�E�j�����悤�ɂȂ�A���̔g�y�������āA����ɋ����{���w���ɂ��Љ��̍u�`���J�����悤�ɂȂ����B�P�X�V�O�N�O��̂��Ƃł���B
�@��s���̐l�����E�������k���̋}����w�i�Ƃ��鋳���{���w���̊w��������E�����萔���ɂ���āA�����w�|��w�E����w�������̑̐����g�[����A���͂����ɎЉ��W�̎��ƉȖڂɐ�O���邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ����B�����āA�S���ɐ悪���ĎЉ���S�����鋳�����Q���̐��ƂȂ����i�P�X�V�S�N�j�B�ނ����㋳���w���u���a����v�S����ݒu���邱�Ƃ̊֘A�ŁA�����w�|��w�̎Љ��S�������̂P�����i�Q���̐��j�����������ƋL�����Ă���B��w�J���L�������Ɂu�������E���a������I�v�Ƃ����^�����Љ��̉Ȗځi����j���݂ɂ����ʂ������炵���̂ł���B
�@�P�X�V�O�N��ɁA�����{���w���ɎЉ���U�̌����҂��̗p���铮���������Â����Ȃ�̂́A��q�̂悤�ȗ���ƂƂ��ɁA������E�\�Z�ώZ��u�Љ��v�Ȗڂ������u���ƈʒu�Â��������Ȃ̑[�u���傫�������B����������Љ�w�̎����u�������P�N���������B����ɂ͓����A�����ɂ킽���ē��{�Љ��w��X�������ꂽ�g�c�����i�����̐���w�����A����̎Љ�琄�i�S�����c��ψ����A�����ɕ����ȎЉ��R�c��̈ψ��j�̂Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʓw�͂����������Ƃ���L���Ă��������B
�@�u�Љ��̌����҂́A���낢�늈���ɋ�̂悤�Ș_��͂��邪�A�n���v���ł������H�ʂ��邱�Ƃ����Ȃ��v�Ə��Ȃ���q������Ă������Ƃ�z���o���B���͓����̑呠�ȁE��v���ɗF�l���������Ƃ�����A�ᑢ�Ȃ���u���т���A�ǂ��v���H�v�Ƒ��k�����肵�����Ƃ��������B
�@�����āA�P�X�W�O�N��ɂȂ�ƁA���q���Ǝ������k�����̒��͂�����Ƃ�����A����ɂƂ��Ȃ������̗p�̌����Ƌ����{���w���̍ĕҁE�k���A�[���ƂƁu�V�ے��v�ݒu�̓������n�܂邱�ƂɂȂ�B
�@���̎����A���͍K���s�K���A��w�̒����̖�E�i�w�������A�t���}���ْ��j�����ׂS���ɂ킽���Ė��߂邱�ƂɂȂ����B�����{���̒[�����������Љ��́A�����{�����傽��ړI�Ƃ��Ȃ��u�V�ے��v�̒��S�Ɉʒu���邱�ƂɂȂ����B���ʂƂ��ē����w�|��w�̒��Ɂu���U����v��U�𗧂��グ�A�����ɎЉ��E�}���يw�E�����يw�̂R�R�[�X��ݒu���A���ꂼ��Q���A�P���A�P���̐�C�����萔���m�ۂ��āA�Q���̐�����S���i�]���̊w�Z�}���يw�P����������T���j�̐��ւƁg���i�h�����̂��B
�@�W�O�N�ォ��X�O�N��Ɍ����āA�e��w�ł́u���U�w�K�Z���^�[�v�I�{�݂̐ݒu��������B����Ɂu�V�ے��v�̒����������āA����n��w�̂Ȃ��ł̎Љ��֘A�̃J���L�������Ƌ����̔�d�́A�傫�����債�Ă����B�Љ����U����Ⴂ�����҂����Ȃ��炸�|�X�g���m�ۂł���悤�ɂȂ����B
�@���̌��������A���n�܂��Ă���̂ł���B
�@��������n��w�E�w���̍ĕҖ��ƎЉ��i�R�j
�@�@�@�|�傫�ȓ]���_�A�Ȃɂ������邩�@�@�@�@�@�@�@�����ق̕�260���@2002�N2��12��
�@��N���獡�N�����ɂ����āA��������n��w�E�����{���w���͍���̕��������߂Ă������߂̋��c�E�����ɒǂ��A�Ȃ��ɂ͏��ՓI�ȋc�_���d�Ȃ�A�����ւ����悤���B�Ȃɂ��땶�ȏȂ͋����p���Łu���g�v�u�����v�u�ĕҁv�ɂ��ĉ��炩�̕������P�����܂łɂ܂Ƃ߂�悤���߂Ă��Ă���̂��B�����ق̕��E�����o�[�̂Ȃ��ł��A�É���w�͂��߁A�k�C������A�������A����ȂǁA�܂����̑�w�ł��A��a�̂Ȃ��ŁA���łɉ��炩�̑Ή����Ƃ��Ă���̂ł��낤�B
�@�����{���w���̌��������́A�u�����ق̕��v�Q�T�V���ɂ��L�����悤�ɁA������u�V�ے��v�̈ʒu�Â����傫�ȏœ_���B�u�݂�����v�i���ȏȍ�������ǒ��ْ�u�����̋����{���n��w�E�w���݂̍���Ɋւ��鍧�k��v�j�Ɏ��^����Ă��鎑���ɂ��ƁA�����{���ے��̓��w����E9,750�ɂ������ĐV�ے��̒����6,180�i38.8���j�ɒB����i���v15,930�j�B����̏��Ȃ����K�͋����{���w���łƂ��ɐV�ے��̔�d���������B
�@���Ȃ݂ɐV�ے��̐�U����ʂ̓���ł́A���U����E�Љ��i���w���1,411�j�������Ƃ������i22.8���j�A���ō��ۗ����E���ە����i872�j�A����E���i824�j�A�|�p�E�����i819�j�A���U�X�|�[�c�E���N�Ȋw�i787�j�A������i780�j�A���ŎЉ���E�Տ��S���i415�j�A�����Ȋw�E���R�Ȋw�i272�j�̏��ɂȂ��Ă���B�����{���w���̋��Ȏ�`�i����A�Љ�A���ȂȂǁj�̘g�g����E�炵�A����̏��ۑ�ɒ��킵�悤�Ƃ���ʔ�����U������ł���B
�@�V�ے����o�ꂵ�͂��߂��w�i�ɂ́A�����{���w�����̎��I�Ɏc���Ă������t�͊w�Z�ȗ��̓`���I�Ȋw�ȍ\���ƃJ���L�������\����傫���]���E���v���Ă������Ƃ��銈���Ș_�c���������B���݂̊O���I�ȁu���v�v�����ƈ���āA����n��w���̓����I�ȓw�͂��V�����ے����u��������v�ݏo���Ă����̂͊m���ł��낤�B
�@���̕��݂�1980�N��㔼����90�N��ȍ~�̂��ƁA�܂�10�N�]��̖͍��ɉ߂��Ȃ��B�������A����܂łɂȂ��V�������������낢��Ƃ�����n�߂Ă����g10�N�]�h�ł������B��������{���w���̌ʂ̎���ɂ���Ĉ�l�ł͂Ȃ����A�Ⴂ����̌����҂��}���āA�V�������_����̓]�����A�Â��ɑٓ����Ă���Ƃ�������������B�ǂ̂悤�ȕω��������Ă����̂��B
�@���Ƃ��Ύ��̂悤�Ȃ��Ƃ��������悤�B
�P�C�w�Z����E���Ȏ�`���S�̘g�g�ɂ�鋳���{�����x���A�L�����삩��u������E�v�i���̒��ɎЉ��֘A���E���܂ށj�{���։��v���Ă������Ƃ���V�������_�̓o��B
�Q�C����w�A����S���w�A���ȋ���w���Ɉˋ����Ă�������܂ł̃J���L����������A�֘A���Ȋw�̊w�ۓI�Ȍ������ʂ�ϋɓI�Ɋ��p���Ă������Ƃ���A�J�f�~�b�N�Ȑ����̌���Ɗg�[�B
�R�A����Љ�̐؎��ȏ����ƒn��̎s�������ւ̂܂Ȃ����B
�S�C���U�w�K�Z���^�[�̐ݒu�Ƃ��A�����āA��w��n��֊J�������̊������B������A��w����n��ւ̈�����̃G�N�X�e���V�����łȂ��A�n��Ƒ�w�̑o�������̃G�N�X�e���V�����̎n���B�����đ�w�ƒn��Ƃ̏o��B���{�ł��悤�₭�����������オ�{�i�I�Ɏn�܂����A�ƌ����邩������Ȃ��B
�T�C�Љ��E���U�w�K���w�Ԋw���̑����B��L�̂悤�ɐV�ے��u���U����E�Љ��i���w���1,411�j�v�̃R�[�X�����Ȃ��Ƃ�10�N�̒~�ς����������Ƃ��l����A���ׂP���S��l�̎Ⴂ�l�X���Љ��E���U�w�K��V�����w���ƂɂȂ�B�Љ��厖���i�̎擾�͂���܂Ŏ�Ƃ��Ď�����w�����S�ł��������i�Љ��E�A�E���w�i�ɂ��ܑޒ��C���j�A������w�ł̂��̂悤�ȓ����͏��߂Ă̂��Ƃł������B�w������̑��͓��R�Ȃ��狳�������������A������w���ł̎Љ�猤���҃|�X�g������܂łɂȂ��g�債���B
�@���̂悤�ȁu�V�ے��v������10�N�]�Â��ɓW�J���Ă����̂ł���B��������̉ۑ�E����������A��J�̑���10�N�]�ł��������B
�@�����{����w�͊e�s���{�����ɐݒu����Ă����B���̈Ӗ��Œn���`�ɗ��r���ăR�~���j�e�C�E�J���b�W�̐��i�������Ă���B���̊ԁA���U�w�K�̐�������������A�J���ꂽ��w�Ƃ��Ă̓���������Ɋ����ɂȂ�A�悤�₭��w�ƒn��́A�����đ�w�ƎЉ��E�����قƂ̏o����n�܂����i�K�ɂ����āA���̌����������߂��鎖�ԂɂȂ������ƂɂȂ�B���ꂩ��P�N�A����ɓƗ��@�l�����܂߂Ă̐��N�A�ǂ̂悤�ɐ��ڂ���̂ł��낤���B
�@�Ƃ��ɋ���w���E�ĕҐ��̓������J�������B�n��E�����̂̎Љ��E�����ق̊ϓ_����A�傢�ɊS�������Ă����K�v������B
�������{���w���ĕҖ��ƎЉ��(4�`6)�@���ȉ��E��
�@�E�k�C�������w�i���c�a�_�j�@�����ق̕��E263���@2002�N2��19��
�@�E�R����E���l������E�����{���A�������p�~��
�@�E�É���w�i�Έ�R�����j�@�����ق̕�265���i2002�N2��23���j�E�����ق̕�267���i2002�N2��27���j
![]()
�S�C�ҏ��̎厖�u�K���ӂ肩����
�@�@�@�|�P�X�W�S�N�E�����w�|��w�Љ��厖�u�K�̎��݁i���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ѕ��l�u�ҏ��̎厖�u�K���ӂ肩����v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����w�|��w�Љ��厖�u�K�W�^�A1984�N�A2�`6�ŁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏��^�͎Љ�琄�i�S�����c��� �w�Љ��E���U�w�K�n���h�u�b�N�x
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i1989�N�A�G�C�f���������j�Ɏ��^���ꂽ�B
�@�c�i���j�c�@�u�K�̍��i�ƃv���O�����̑�g���m�肵�Ă����ߒ��ŁA��C�u�t�Ƃ��čl��������
�͎��̂悤�Ȃ��Ƃł������B
�P�C��w�ɂ����ĎЉ��厖�u�K���J�Â���Ƃ������Ƃ̈Ӌ`��ϋɓI�ɍl�������B�����
�@��͂�A�w��T���̌����I���_�A���R�̐��_�A�����I�ȏW�c�̌`���A�Ƃ�������w�I�ȗ�
�@�O���A�厖�u�K�̉^�c�ɂ����Ă��A�ł��邾�����d���邱�Ƃł��낤�B
�Q�C�u�t�w�́A���̕���ɂ���������̌����ҁE���Ƃ��˗����A���������̍u�K�v���O��
�@����Ґ��������B�w���X�^�b�t�����łȂ��A�ϋɓI�ɓs���E�s�O�̑�w�E�����@�ւ���u�t��
�@�����B
�R�C�u���K�v���d������B�u���K�v��ʂ��Ď��R舒B�Ȍ����W�c���`������B��u�����݂̂ł���
�@�����莩��I�Ȍ𗬂��[�܂�悤��������B
�S�C��u���ɂ�鎩���I�ȉ^�c�d����B��w�����u���֗^���邩�����̎�g�̍u�K�ł�
�@���A�ϋɓI�ȎQ���Ǝ����ɂ��u�K�ɂ������B
�T�C�{�w���ʒu���铌���E�O�����̎Љ��@�ցi�����فA�}���ٓ��j�����w���A����ƌ𗬂�
�@��@���݂��āA��w�����łȂ��A�n��̎��H�̋�̓I�ȓW�J��ʂ��Ċw�K�ł���悤�ȍu�K
�@�ɂł��Ȃ����̂��B
�@�c�i��u���A�u�K�v���O�����A���K�Ǝ{���w�|�����j�c�@�@
�@��u���̎����g�D
�@�Љ��̖{���́A����I�Ȏ��ȋ��犈���ł���A�����I�ȎQ���Ǝ��������d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��炷��A�Љ��ɂ������厖�u�K���̂��̂��A����I�A�����I�ɁA�u�Q���Ǝ����v��厖�Ȍ����Ƃ��ĉ^�c����邱�Ƃ́A����߂ďd�v�ȉۑ�łȂ���Ȃ�Ȃ������B���̓_�́A�u�K�̑�P���ڂɎ�C�u�t�������N���A�ϋɓI�Ȏ��g�݂���u���ɋ��߂����Ƃł������B
�@��u���̊F����́A����ɐ^���ʂ��牞���Ă����������Ǝv���B�܂��A�����ɂ��āA�����ψ���g�D���ꂽ�B�͂��߂Ă̑����ψ���ňψ��ɑI�ꂽ�e�ʂ��A�厖�Ȗ��ɂ��Ď����I���ϋɓI�ɔ������n�߂�ꂽ�Ƃ��A�u�����A���̍u�K�͔��ΐ��������悤�Ȃ��̂��v�Ǝv�����B
�@�����ψ���̘b�������Ɋ�Â��āA����ɐ�����A�����E���N�E�L��E�L�^�A�}���E�����A�ҏW�̊e�ψ�����������B�����̈ψ���͂��ꂼ��Ɉψ����i���ψ����j��I�сA�厖�u�K�̑S���Ԃ�ʂ��āA�n�ӂ��ӂ�銈���Ɏ��g��ł����������B���́u�����v�����́A�{�u�K�̂Ȃ��ł��ł����������A�Ђ낭���p���ׂ��_�ł͂Ȃ��낤���B�L��E�L�^�ψ���ɂ��u����Ղ����v�̔��s�A�����E���N�ψ���̖����̃��N�����A�}���E�����ψ���ɂ��}����������A�̔������A�����ĕҏW�ψ���ɂ��{�u�W�^�v�̎���ҏW�A�Ȃǂ��̓T�^�I�Ȋ����ł���B
�@�Ȃ��ł��A�u����Ղ����v�͊w�O�ɂ��������܂��������A�Q�n��w��M�B��w�̎厖�u�K�ɔg�y���A����Ɏ����~�j�E�R�~�̔��s���s��ꂽ�ƕ����B�u����Ղ����v�͍ŏI���U�V���𐔂����B�����i�����Ƃ��͂P���ɂW���j�̔��s�ɓw�͂��ꂽ�ψ���̊F����ƁA���C�悭���̈����S�����Ă��ꂽ��w�����ۂ��͂��߂Ƃ���W�̊F����ɁA�E�X�������B�i�ȉ��A���j
![]()
�T�C����E���A�Q�O�N���}���Ă̗�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�����w�|��w�E�Љ��[�~�E����K��c�u���f�̓y�n�E����ցv�i1992�N�j
�@�P�X�X�P�N�͂悭����ɒʂ����N�������B�P���A�S���A�����ĂP�O���̋v�Βn���ɂP�T���N�A�����Ă܂��|�x���E��q��Ձi�P�P���j�ȂǁA����ɋ������������������o�|�Ƃ̊y���������������i������ꂽ���|�|�j�B�P�P���̒|�x�E���d�R���܂�闷����̔g�y�������āA�P�X�X�Q�N�P���̐������X�ɑ������ʼn����K�₷�邱�ƂƂȂ����B
�@���������U���o�����Ƃ������̂ɁA����͂����ł͂Ȃ��A���s�̊w�����N�̕�����U���o���ꂽ���������B���̔M�ӂɂ͉��Ƃ��Ă������˂Ȃ�Ȃ��Ǝv�����B�����Ė{�W�̍쐬�i�w�����̖Z�������ɂ��S�炸�j���撣���Ă��ꂽ�B���U�����U�E�O�N�E�Љ��[�~�i���у[�~�j�L�u�̎�X�����G�l���M�|�ɂ܂��h�ӂ�\���Ă��������B
�@�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�P�X�X�Q�N�́A����̖{�y���A���璚�x�Q�O�N�̋L�O���ׂ��N�ɂ�����B���̂Q�O�N�Ƃ����Ό��͈�̂ǂ�Ȍo�߂ł������̂��낤���B�����������ꌤ���ɂ��������悤�ɂȂ��ĂP�T�N�o���A���������ׂĂ��A����͐����ς�����B�����ĉ������芪�����ۓI�ȏ���傫���������B
�@�Ƃ��ɍŋߐ��N�̓������߂��鐭���̌����ɂ͖ڂ�D����B�\�A�M�̉�̂Ɏ��������\���̕ω��́A���R�ɋɓ��́g�L�C�E�X�g�|���h�ł��鉫��̐����I���R���I�ʒu�ɂ��傫�ȕω��������炵�����ł���B���A�����̏����r���āA����͂ǂ�Ȃ������ł��܋�̓I�Ɍ���Ă���̂ł��낤���B����𗷂��Ă��A���̎����͂Ȃ��Ȃ��p�������Ă���Ȃ��B�Ƃ�킯�P���Ȋό����s�̋C���ł͉��������͂��Ȃ��B
�@�����̗��̍\�}������Ă��āA����̌R����n�͎���ɏk���E�Ԋ҂̕��������ǂ邾�낤�Ƃ����̂���ʓI�Ȍ����ł��낤�B���������x�̗��ł́A�ނ���t�̈�ۂ����B��`�ɗאڂ���ߔe�`�̌R�p�n�͖��ɑ��������B�t�C���b�s���̕ČR��n����^��Ă����炵����Ԃ�C�Ԃ��������肾�B�؍������̕ČR����������Ɉړ����Ă��Ă���Ƃ���������B����͈�̂ǂ��������Ƃ��B
�@�����I�ɂ͂ǂ����B��N�����炳����ɉ��ꂪ�b��ɂȂ�B�}�X�R�~�ł��Ȃ��Ȃ��̎�舵�����B���Ƃ��A�͂��߂Ẳ��ꂩ��̑�b�i����J���������j�ANHK�g���o��� ��[���g�A���������ق́u�C��̓��v���ʓW�i���A�Q�O���N�L�O�j�A�����ė��N��NHK���
�h���}�Ɂu�����v�̓o��A�Ȃǂł���B
�@���ꂪ�b��ɂȂ邱�Ƃ͂������Ƃ��B����ɂ́A����̗��j�Ɛ������A���ƂƖ��O���A���邢�͐푈�ƕ��a�A�Ȃǂ̖�肪��������ƋÏk����Ă���B�������ꂪ�ǂ̂悤�Ɏ�肠�����邩������Ȃ���Ȃ�܂��B����ׂ����ł͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��������A�����̐[�݂ɂ���āA��������ƌ��߂�w�͂�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@����̗��ŁA��҂����͉���̉����������낤���B�ނ�́u�Ђ߂�蕽�a�L�O�����فv�́g��蕔�h�̂��b�ɗ܂𗬂����i���̘b�ŋ��������Ƃ͈�x���Ȃ��j�B���݂̂��݂����������������Ă���A�����Ɖ���̐[�������ďd�����������߂��ɈႢ�Ȃ��B
![]()
�U�C���I�ɂ������낢������Ԃ�
�@�@�@�@�@�@�����w�|��w�Љ�猤�����u���₫�ʐM�v12���i1993�N�j
�@���N�̌������͂ɂ��₩���B�����炭�Љ�猤�����͂��܂��Ĉȗ��̂ɂ��₩�����낤�B����܂ł̑�w�@�u�Љ��v�u�����A�V�����n�܂������{�n�̊w�N�i�s�ɂƂ��Ȃ��āA�X�Q�E�X�R�N�x�́u���U����v�u���Ɠ�{���ĂɂȂ����B�@���E���w���Ƃ��ɒ�����������킯�ł���i�������X�S�N�x����͗��u���͈�{�ɂȂ�j�B����ɉ����Ċw���̎Љ���U�̏��N�����Ȃ茳�C���B
�@�U��Ԃ��Ă݂�ƁA���Љ��w���БS���^���Ȃǂ̑����Ŋ��Ă��鏬�ѕ����i��������w�j����i�O�i�����w�j�Ȃǂ��@�����������́A�Љ��u�����̂��̂��Ȃ������B��������͋���j�u���A�i�O����͊w�Z�o�c�w�u���ɏ������Ă����B���܂̎Љ��u�������v���Ȃ������B���w���͈�l�����Ȃ������B�ʂ̐搶�Ƒ������̏��ь��������ʂ�g�苒�h���Č�����������Ă����B����ł��Ȃ��Ȃ��M�C���ӂ��_�c�����킵�Ă����B�������A���c�i���E����j���q�����āA���܂������Łu�Љ��n���h�u�b�N�v���ł̕ҏW�E�����Â���Ɏ��g���Ƃ��v���o���i�P�X�V�X�N�~�j�B
�@�������łɉ��ꌤ����͎n�܂��Ă����B����E�����ǒ��͖��{���i�_�ˑ�w�j�A�Q��ڂ͖쑺����q�i��c�拳�ρj�B�W�O�N��ɓ����āA���܂̌��������V�z���ꂽ�B���сE���l�̌����������ɂȂ�A�u�������v�Ƃ������̂ŐV���������̌��������ł����B���̍����班�������w��������݂���悤�ɂȂ����B�L���ł͂W2�N�ɒ�����w�K��A�����ĂW�W�N������Ɂu�A�W�A�E�t�H�|�����v�����������B
�@���܌������͂ɂ��₩���B���w�����ӂ��߂đ��ʂȐw�e���B�������Ղɍ�N�͋��������̐��ʂ��u�����̎������H�E�P�X�X�Q�v�Ƃ��Ċ��s�����B���̂Ƃ��͓��c����i�����s�����猤�����j�⊁����M�i�����s���璡�j�����S�������B���N�͌������o�|�̑��͂������āA���������u���A�W�A�̎Љ��E���l����@���v����������B���������Ƃ��B�Љ��W�̑�w�E�������Ƃ��ẮA���m�ے��������Ă����w���ӂ��߂āA���F�̂Ȃ������E���������Ɏ��g��ł��銈���Ȍ������A�Ƃ����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�������ۑ������B���̗ʓI�Ȃɂ��₩�����A���ʂȐw�e���A���ƈ���I�Ȃɂ��₩���ɁA���ꂼ��̓��ʓI�ȏ[���ɁA�ǂ����т��Ă������B���݂��̌X�̌����e�|�}��ϋɓI�ɏo�������āA�����̌����_�c���ǂ��R�����点�Ă������B���܂��A�����Đ����ł͂Ȃ������������A���������_�ɂ��āA���݂��̋M�d�Ȍ����I�g�t�h�i�������܂߂āj��n�肾���Ă����������̂ł���B���j�́A�ĊO�Ƃ��܂��āA�����ł͂Ȃ��Ƃ��납��A�������S���悹���������̋�ԁE���܂�ꂩ��n�܂���̂��B
![]()
�V�C�����w�|��w�u�Љ�牉�K�v�[�~���|�܂������E�܂Ƃߓ�
���P�X�X�P�N�x�u�͂��߂Ɂ|�����̎���ɐ����āv�i1992�N�P���j
�@�P�X�X�P�`�Q�N�ɂ����Ă̎Љ�牉�K�i���R�E�S�j�́A����܂ł̓`���H�����ă[�~�̋L�^�W���܂Ƃ߂邱�ƂɂȂ����B�[�~�����̌ܓ��a������A��Ƃɂ��������L�u�A�����Ď��M�ɓw�͂����[�~�̊F����A����J���܂ł����B
�@���N�x�̃[�~�͂ǂ̂悤�Ȏ���I�w�i�̂��Ƃɂ����߂�ꂽ�̂��B�w�⌤���Ƃ������̂́A�ڂ�ς�鎞�ォ�璴�z���ė��O�E���_�̐��E�𒊏ۓI�ɓ����Ă���悤�ɂ��݂��邪�A�����Ă����ł͂Ȃ��̂��B�����N�x�̎Љ�牉�K���܂��O���|�o���ȋK�͂ł̌������̕ω���w�i�ɂ��āA���t��������A���E�̌�����̂ɂ����āA�[�~�͂����߂�ꂽ�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�����܂ł��Ȃ�����̊w���̊F����́A����܂ł̐��E�j���o���������Ƃ̂Ȃ����̌��ς̎���Ɋw�������𑗂����B�P�X�W�X�N�ȍ~�̒����E�V����̎�������n�܂��āA�����E�x�������̕ǂ̕���A�p�ݐ푈�A�����ă\�A�M�̉�̂ɂ����邱�����N�̗��j�͌�܂ŋL�������g����h�ł��낤�B�������̂悤�Ȏ���Ɋw���Ƃ��ĕq���ɐ����������ǂ����̈Ⴂ�͂��邾�낤���A���Ȍ����������A����Ӗ��ł͂������Ɂg�w���h�ł������킯�ł���B�@�@�@
�@�Љ������R���̎���́g�Љ�h�Ɓg���j�h�ɕq���Ɋ֘A���ē����Ă����B�P�X�S�T�N�ȍ~�̐�㋳����v���炷�łɂS�O�N���܂�A�������N�̓������ӂ肩�����Ă݂�ƁA���܂܂��ɎЉ��g�����h�̎���Ƃ����Ă������낤�B���̎�v�Ȃ��̂�������A��͂P�X�X�O�N�ɐ��肳�ꂽ�u���U�w�K�U�������@�v�ɂƂ��Ȃ������A����ɂƂ��Ȃ��Љ��@���̌������H���A��ɂ͊w�Z�ܓ����E�T�x������ɂ��������A�����ĎO�ɂ͍��ێ����N���_�@�Ƃ���V�����������H�̎��g�݁A�l�ɂ͊O���l�J���҂Ȃǂɂ݂�����{�Љ�́g���Ȃ鍑�ۉ��h���A�܂ɂ͂����ɘA�����鍑���̊��E�����E�n��E�����E�J���E���ʂȂǂ̐V���ȏ����Ƃ���炪�Љ��E���U�w�K�ɒ�N������A�Ȃǂł���B�@
�@���N�x�̎Љ��[�~�́A�����̌���I���ۑ�́g���h�̂Ȃ��ŁA��͂Ȃ��炻�̗��ɒ��킷�邩�����ł����߂�ꂽ�B�܂�?�e�L�X�g�u���U�w�K�v��ƎЉ����������v�i���сE�����ҁj���Ƃ肠���A?��L�̌���I�ۑ�ւ̔F����[�߂A?������O��̎������H�ɂ��Ē������i�L�u�ɂ��|���{�Љ��w��N��u���ێ����\�N�Ɠ��{�̎������v�Ɏ��^�j�A�����Ă��ꂪ�_�@�ƂȂ���?�㔼�͖{�W�ɐ��荞�܂�Ă���e�|�}��ݒ肵�A���ꂼ��S����ۑ�ɂ��ăO���|�v�ŕ��S���A?�����E�E�������d�˂Ȃ��烌�|�|�g���܂Ƃ߂�A�Ƃ����o�߂ł������B�o���h���͌��Ă̂��y���݁I
�@���̃[�~��ʂ��Ċw���̊F���������B��l�ЂƂ�ɍׂ��������@������ĂȂ��̂��c�O�ł��邪�A����Ɨ��j�ɂ�������q���Ȋ����i�m�������łȂ��j�ƁA�ۑ�ו��͂������Ē��킷�鐸�_�����������Ăق����A�Ɗ���Ă���B�u�������g�̐��E��ǂݎ��A���j���Â錠���v�i���l�X�R�E�w�K���錾�j�������̂��̂ɂ��Ăق����B
���P�X�X�R�N�x�[�~�E�W�u�͂��߂Ɂ|�����̎���ɐ����āv�@�i1994�N�P���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�P�X�X�R�N�x�u�Љ�牉�K�v�i���E�S�E�T���j�Q���҂́A�Љ��E��U�̊w���ł͂Ȃ��A���w�ȁE����U�̊w�������ł���B�݂Ȃ��ꂼ��́A�Љ��ȊO�̃e�|�}���邢�͑��Ƙ_���̉ۑ���������Ă���B
�@���������ꂼ��̗���ŎЉ��ɂ��Ă̊S�������Ă���B���N�x�́A��N�x�̌o�߂��l���Ȃ���A�[�~�J�n�̒i�K�ŁA���̂悤�ȁq�ۑ�|�P�O�̃L���|�h�r���N�����B�@���U�w�K�E������߂��铮���A�A���U�X�|�|�A�B��Q�ҁE����ҁE�Љ���A�C��ƃ��Z�i�A�D�O���l�J���ҁA��A�ݓ��؍��E���N�l�A�E���{�ꋳ���A�F�T�x������A�w�Z�T�ܓ����A�w�Z�J���A�G�q�����̌������A�H�n�敶���^���A�I�����̎Љ��E�{�݁A�̂P�O�_�ł������B
�@���̒����N�_�ɁA�V�����ۑ�������i���Ƃ��u�������A���a����v�Ȃǁj�Q���҂��ۑ�����L�������S���邩���ŁA���ꂼ��̃e�|�}��ݒ肵���B�[�~�͊e�e�|�}�E�O���|�v�̕��d�˂邩�����Ői�߂�ꂽ���A�ŏI�I�ȃ��|�|�g�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ���̂��A�ڎ��ɂ��߂����悤�Ɍ��������̂ł���B
�@���̃[�~�̐i�s�A�����ă��|�|�g�W�̍쐬�ɂ���������u���̊F����A�Ƃ��Ɋ����i�ҏW���j�╛�����A�R���p�S���̘J�𑽂Ƃ������B
�@���̋@��ɂ��̃[�~�̔w�i�ł����������̐����A�����ĎЉ��E���U�w�K���߂��鐭��̓�����U��Ԃ��Ă������Ƃɂ��悤�B
�@�P�X�X�R�N�͐����I�ɂ͌����̂P�N�ł������B���̔N�̉āA�����͌�サ�A�א�A�����t�����������B���̘A�����t�́A�Љ��Ȃ������U�w�K�ɂ��Ăǂ̂悤�Ȑ���E���j�������Ă���̂��낤���B���j�I�ɂ݂āA�ǂ�Ȗ������ʂ����̂��낤�B
�@���m�̂悤�ɁA�P�X�X�O�N�V���ɐ����������U�w�K�U�������@���炷�łɂR�N���܂肪�o�߂��Ă���B���̊Ԃɂ́A�@�i��P�O���j�Ɋ�Â��Đݒu���ꂽ���U�w�K�R�c����\���܂Ƃ߁i�P�X�X�Q�N�V���j�A�܂��ʎY�ȁE�Y�ƍ\���R�c��E���U�w�K�U��������u���U�w�K�̐U������ɂ��āv�̒��ԓ��\�i���N�X���j�������Ă���B���ꂩ���P�N���o�߂����Ƃ���ł̐V���t�̔����ł������B
�@����Ȃ��ƂɐV���t�́A�O�������̂�����o�u���o�ς��݂��Ƃɕ��A�o�ϕs���̒��������[�������邻�̐^�����Œa�������B���U�w�K�U�������@�ݗ��Ƃ����o�ϓI�w�i�Ɛ����v���͑傫���ϓ����Ă���B��s���s�����Ȍo�Ϗ̂��ƂŁA���̖@�̖ڋʏ��i�ł���u�n�搶�U�w�K�U����{�\�z�v�u��v�i����T�A�U���j�́A�@��������R�N�����o�߂������݂ł��܂����肳�Ă��Ȃ��ł���B
�@�����炱�̐��U�w�K�̐���ɂ��ẮA���镶���ȁE�^�S�����ɂ��u�������H�͂��������A�Ԃ������Ă���Ȃ��v�̂������ł���B�������ނ��덂�����H�̊�Ղ��̂��̂��傫����炬�A�������H���̂��������̎��ԂȂ̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����ŁA�s���{�����x���̐��U�w�K���i�̐��́A���̂P�X�X�O�N�E�@�{�s�ȍ~�ɋ}���ɐi�s���Ă���B�s���g�D��́u�Љ��v���������āu���U�w�K�v�֍ĕ҂��铮���������ł���A���邢�͐��U�w�K�W�̐R�c��E���i��c�����݂����A�u�v��v�����肳���ȂǁA���ۂɂ͖��炩�ȓ]�����n�܂��Ă���i�����Ȑ��U�w�K�ǒ��ׁA1993�N10���j�B
�@�����čא���t�́A���̔��N�A���I���搧�E�������v�ƋK���ɘa�̑升����W�J���Ă����B�̎��I����@�ւł���o�ω��v������i����E�o�c�A�E��j�́u���������ł͂Ȃ��v�Ƃ��ĎЉ��@�E�}���ٖ@�E�����ٖ@���ӂ��ދ���W�@�̌��������w�����A�܂����U�w�K�R�c��Љ�番�ȐR�c��͎Љ��厖�E�i���E�w�|�����̎��i�A�{���A���C���ɂ��Ắu�K���ɘa�v�ɂ�����ψ�����������i94�N1��27���j�B�א쥌F�{���m�����ォ��b��ɂȂ����i���ɕ⏕�j�����}���ْ��Ɏi�����i�����߂Ă��錻�s�}���ٖ@�̋K�����ɘa��������_�@�Ƃ��āA�u�}���ٖ@�{�I�Ɍ��Ȃ����v(�w�n���s���x�93�N8��30�����j�������������Ȃ��B�P�X�X�S�N�ͤ���܂܂Ŏ�荹������Ă����Љ��W�@���́g�����h��肪�V�����}���シ�邨������łĂ��Ă���B
�@���܂�U�w�K����͒P���ȋ��琭��̈ʒu�ɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ��B���̐������v�⎩���̐���ƕ��G�ɗ��ݍ����i���Ƃ��Ώ��I���搧�Ɛ��U�w�K����Ƃ̏d�Ȃ�j�A�o�ϐ헪��K���ɘa�̐���Ɛ[���֘A���Ă���B�傫�����Ɛ���̂Ȃ��Ɉʒu�Â��Ȃ���A���U�w�K�̖��̍\�}����������Ɠǂ݂Ƃ�K�v������B�@����ɂ�������炸�A���̊Ԓ��ڂ����̂́A�Ƃ��Ɏs�������x���ɂ�����n�悩��̐��U�w�K�v��Â���A�����̐���Â���̓����������Ȃ��Ƃł���B���Ȃ��Ȃ������̂ɂ����āA�Z����̂̃G�l���M�|���������A����ɂ�������ĐE�����i�����A�܂������҂��Q�����āA���e�̂��鐶�U�w�K�̌v��Ȃǂ����肳��Ă���B�����ɂ͋��ʂ��Ď匠�҂���Z���̊w�K���ۏ�̗��ꂪ���ɂ���A��炵�A���A���N�A�����Ȃǂ̐��������ۑ�Ɛ茋��ŁA�L�����삩��̎����́u���U�w�K�v��v��n�肠���悤�Ƃ����w�͂��g������݂��Ă���B
�@���̂悤�ȐV��������������ɂ���āA���{�̐��U�w�K�E�Љ��̂��ꂩ��̖]�܂����W�J�ɊS�����������Ă��炢�������̂��B
![]()
�W�C�������̎������H�E�P�X�X�Q������}�b�v�����|�Ȃ��߂̊����������i�ʃy�[�W�j�@
�@ �@ (�����w�|��w�Љ�猤���� 1992�N�j
�@ �������̎������H�|�X�Q�N����X�S�N�ցE��O�������}�b�v������
�@�@�@(�����w�|��w�Љ�猤�����w�����̎������H�E1994�x�i1995�N�j
![]()
�X�C���A�W�A�̎Љ��E���l����@���i���_�j���� �i�ʃy�[�W�j�@
�@�@�@�E�����w�|��w�Љ�猤����
![]()
10�C�t�̍��ƏH�̟O�Ɓ|�v���o�͂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����w�|��w�L�����p�X�ʐM�i1995�N3���j
�@���̑�w�ɕ��C�����̂͂P�X�U�V�N�B�����́A�t�̍����H�̟O�̍g�t�����ł�]�T�͂Ȃ��A������������E�o�������A�Ȃǂƍl���Ă������Ƃ�z���o���܂��B�Ȃ������������̂��A���̗��R�������ɏ����]�T�͂���܂���B���̌�A�����g�����]�Ȑ܂�����A�Ό����o�߂��Ă���ƁA���̊Ԃɂ���w�̏t�̍����҉������A�܂��g���F�Â����O����ʂ邽�тɁA������w���Ȃ��A�Ƃ��݂��ݎv���悤�ɂȂ�܂����B�����Ă��ɒ�N���}����܂Ŗ{�w�ɂ����b�ɂȂ����킯�ł��B���낢��ƗL��������܂����B
�@��s���̑�w�Ƃ��Ă͎��R�L���ȃL�����p�X�A�X�K���Ă̐V���������I�|�v�����������i�P�X�W�O�N�j�����肩��A�ϋɓI�Ɍ������Â���ƔN���s������Ă��܂����B�S���E�Ԍ��A�T���E�t���h�i���}��j�A�U���E�i��j�u�t���͂މ�A�V���E���[�̉�A�X���E��ꔪ�̏W���A10���E�����̉�A11���E����ւ̌������s�A12���E�Y�N��A�P���E���_�j���A�Q���E�t�߁A�R���E���ʉ�A�Ȃǂł��B�@�������J����Ȃ������s��������i�u�ጩ�̉�v�͗\���ł��Ȃ��̂ł��Ɉ�x���������Ȃ������j�A�܂��N�ɂ���ĈႢ������܂����A���̂P�O���N�قڌ������s���Ƃ��Ď��{����Ă��܂����B����ɗ��w�����S�̃A�W�A�E�t�H�|�����⒆����w�K��A����ɉ��ꌤ����d�Ȃ��āA�܂��Ƃɓ��₩�Ȍ������ƂȂ�܂����B���N�O�܂ł͌������ł悭�̂��������܂����i�J���I�P�E�u�|���ȍ~�͉̂�Ȃ��Ȃ����j�B���܂ł��Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��v���o�ƂȂ�܂��傤�B
�@�ꂵ�����Ƃ�����܂����B�Ȃɂ����V�O�N�O��̑�w�����̂��ƁA���̓��������Ă��������o����������܂��B���ꂩ��w�������̂S�N�ԁi�P�X�W�O�`�W�S�N�j�A�����ĐV�ے�������ۂ̐��݂̋ꂵ�݁A�Ȃǂł��B����́A�v���o������������܂���B���̊ԁA���͂Ƃ��ɐS���鎖�����̕��X�Ɏx���Ă��������܂����B���炽�߂Č���\�������܂��B
�@�����J�̗��j���@��A�����ɐN��
�@�@�@�i�l�`���T�[�N���u���J�v�n���R�O�N�L�O�A�P�X�X�Q�j�@�ʃy�[�W�����i��z�@�U�S�j
![]()
�@���a����w���@
���a����w�E�Ԃ�[�~�A�č��h�i�͌��A2001�N8���j

11�C�P�X�X�T�N�x�E�v���[�~�D�u�n��Ɛ��U�w�K�v���ӂ肩����@�i���тԂ�j
�@�v���[�~�̏o��
�@���ɂƂ��Ă̏��߂Ă̘a����w�E�v���[�~�A�o��͂P�X�X�T�N�S���Ɏn�܂����B���҂͑傫���B��w���t�R�O�N�]�̌o���̂Ȃ��ł��A�s�J�s�J�i�����ł��Ȃ���?�j�̐V�����u�[�~�v�Ƃ����̂͏��̌��A�Q�����Ă���w�����N�ɂƂ��Ă���w���Ƃ��Ă̏��߂Ẵ[�~�A�o���g���߂āh�Â������B
�@���܃v���[�~�̕W���܂Ƃ߂���ɂ������āA�ǂ�Ȍo�߂ł��̃[�~���i�s�������A�S���҂Ƃ��āA�v���o���܂܂ɐU��Ԃ��Ă������Ƃɂ��悤�B
�@�ŏ��̂S���P�Q���A�P�X���̂Q��̃I���G���e�B�V�����ł́A��Ɏ��̂悤�Ȃ��Ƃ�b�����Ǝv���B
�@�u�n��v�ɂ͋���E�����E�����Ȃǂ��߂��邳�܂��܂̊���������A���邢�͏Z���̉^�������낤�A����܂ł̎��ł͂����炭���邱�Ƃ��Ȃ������u�n��v�A���̐����������ɏo����Ă݂����A���S�̃e�|�}�́u���U�w�K�v�A�{���ǂ݂Ȃ���A�{�������ăt�B�|���h�ɏo�悤�i���̐́A�S��������ɂ́g�{���̂ĂĊX�ɏo�悤�h�Ƃ����咣���������j�A���������̂Ȃ��t�ɂ������ԂƂ��o����Ăق����A�y��������Ă��������A�ȂǂȂǁB
�@���̌��ʁA�T�v���[�~�̂Ȃ����炱�̃[�~��I�����ďW�܂��Ă����Q���҂�34���B�G���g���|�������Ԃ̍ŏ��̖���͔��V����������Ă��ꂽ�B�V���̍��h���܂߂ĉ�v�͐Γc���q�i�⏕�͑��V���q���j�A�S�̂̑�\�́A�Ȃ����x��ĎQ�������`�X�\���������Ă��ꂽ�B�~�j�R�~�̒S���́u�{�������v�i�{�����q�A�����A�c�������j�B�݂Ȏ���I���ϋɓI�Ȏp�����_�Ԍ����Ċ������B
�@�������A�R�S���̂�����������Q���̌��Ȃ������i�P�l�͕a�C�A�P�l�͉ƒ�̎���j�A���ʓI�ɂ͂R�Q���̏W�c�ƂȂ����B�a����w�Ɠ��̃v���[�~���x�i�V�w���E�V�J���L�������ł͕K�C�j���n�肾�������ԏW�c�A���Ă��̃[�~���ǂ̂悤�ɓ����Ă����̂��B
�@�l�̔ǂÂ���Ɓu�n��v�Ƃ̏o�
�@�l�Ԕ��B�w�ȂP�N�̐l������l����ƁA�T�v���[�~�̕��ϐl���͂Q�O���]��ƂȂ锤������A�������̃v���[�~�D�͂P�O���]�葽���Ƃ������ƂɂȂ�B�������w���̈ӎu�d���Đl���̒����͂����ɁA��]�ʂ�ɂ��̂܂���邱�ƂɂȂ����B�������[�~�W�c�Ƃ��ẮA�R�Q���͂�͂肷���������B
�@�S������T���ɂ����āA�S���ҁE���т͂���܂ł̌����҂Ƃ��Ă̎��ȏЉ���܂߂āA�u�n��Ɛ��U�w�K�v�̌���I�ȓ�����ۑ�ȂǂɊւ��āA�������̖���N�������B�������ȂǁA���邢�́u�����̎������H�v�i�P�X�X�T�N�j�Ȃǂ̋�̓I�Ȓn��̓������Љ���B���̏�ŁA�Q���Ҋe���������ꂼ��̌����ۑ���o���������ƂɂȂ����B�Q���҂̖��S�͂��Ȃ葽�l�ȂЂ낪�肪����A��������āA���̒i�K�ł��e���̋����A�����S�d���邩�����Ŏl�̃O���|�v���Ґ����ꂽ�B�l�̔ǂ̃e�|�}�y�у[�~�����͎��̒ʂ�ł���B�@
�P�A����ǁ@�V���i�����E�R�{�M�`�j
2�A�����ǁ@�V���i�����E�X�{���q�j
�R�C���U�w�K�ǁ@�W���i�����E�����v���j
�S�C�����E�l���ǁ@10���i�����E���{�����j�|�����E���a����ւ̊S���܂�
�@���Ȃ̃e�|�}�͎���̈ӎu�Őݒ肷�邱�ƁA���̏�Ŏl�i�Ȃ��������E���a������܂߂Ό܁j�̃O���|�v���Ƃ̋��������Ƀ`�������W���邱�ƁA�����ĉۑ�ɂ������Ċ֘A���邢���ꂩ�́u�n��v(�t�B�|���h)�����邱�ƁA���т́u���߂ɉ����āv(�Љ��@)�������A�����ɑ����āu�n��v���Љ��A�Ȃǂ��b������ꂽ�B
�@�ŏ��ɑ��k�ɗ����̂́A�����ǂ̑]�����D�A�n�ӈ���q�ȂǁB���c�s�����ق̏�Q�ҐN�w���i��Ηm�q���S���j�ւ��肢���A�Z���ȏo����n�܂����B�e�ǂƂ��Ɏ����w����n��̊����ւ̃A�v���|�`�������Âi��ł������B
�@�v���[�~�̓W�J����u�܂Ƃ߁v��
�@�U���ȍ~�ɂȂ�ƁA�e�ǂɂ���Ă��̊����ƃ��|�|�g���J�n���ꂽ�B�v���[�~�S�̂̓W�J�̂Ȃ��ł́A���̂悤�ȃe�|�}�E�������Ƃ��Ɏv���o�����B
�@�T��17���@�@�v���[�~�����R���p
�@�T��31���@�@�u�|��s�̐��U�w�K�v�i�ҁE���c�q�V�j
�@�U���V�� �@����P�t�B�|�g�^���ɂ��f���u�����ւ̏،��v
�@�V��17�`19�� �v���[�~�E���h�i�������j
�@�W��26�`28�� ��35��Љ�猤���S���W��i�R�`�������A�Q���E���V�����j
�@10��11�`17�� ���ꌤ�����s�i����ǁA���ɋ{�����q�A�ѓc����A���Ð^��A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������A�H�ԏˎq���Q���j
�@11���W���@�@���s�ӂꂠ���ق̌��w�A�I���㍧�e��i���U�w�K�ǂق��j
�@12��13���@�@�[�~�u�܂Ƃ߁v�Ɍ����āi���у��N�`���|�j�A�ҏW�ψ���̕Ґ��@�P�X�X�U�N�P���ɓ����āA�e�ǂ̃��|�|�g���܂Ƃ߂��A�ҏW�ψ���ɂ��W�̊��s�̓w�͂��d�˂�ꂽ�B�݂Ȃ���A����J���܁B
�@���̃v���[�~�������A�Q���҂��ꂼ��̘a����w�S�N�Ԃ̏[���̂��߂ɁA���̂����o���ɂȂ邱�Ƃ��F���Ă���B�ȉ��A����̋L�^�Ƃ��āA�@�T���[�~�����A�A�V�����h�A�B�u�܂Ƃ߁v�ɂ��Ă̏��у��N�`���|�̃��W�������^���Ă����B�i���j
![]()
12�C�P�X�X�W�N�̐V���������Ɛ��U�w�K�_�[�~�̉ۑ�
�@
�@�@�@�a������w�l�ԊW�w���E���U�w�K�_�i���ђS���j�[�~�W�i1999�N2���j
�@���ƂЂƂ̏[�������ق����ȂƎv���Ȃ���A���N�̃[�~���I������B
�U��Ԃ��Ă݂�ƁA1998�N�͐��U�w�K�E�Љ����߂����āA���ۓI�ɁA�܂������I�ɂ��A�傫�ȓ������������N���B
�@��ȏo�������f���Ă݂悤�B
(1)1997�N�V���ɊJ�Â��ꂽ��T�E���l�����c�̍ŏI�������m�肵�A���{���������
�@���i������u�n���u���O�錾�v�j�B
(2)�����c���������i�@�i�m�o�n�@�j���R������Ő������A���̂Ȃ��Łu�Љ��̐��i��}��
�@�����v�����荞�܂ꂽ�i��Q��ʕ\�j�B
(3)�����ȁE���U�w�K�R�c��X���ŏI���\���o���A�n���������i�ψ����Q�������̋K���ɘa
�@��ɂ����āA�Љ��@�E�}���ٖ@�E�����ٖ@�̑啝�ȉ��@���Ă������ꂽ�B�߂��@�����Ă���
�@��ɏ������錩���݁B����͊�Ȃ��I
(4)�o�u�������̌o�ϕs���̉e���ɂ��A�����̍����̊�@���[�܂�A�Љ��s�����̐���
�@�͑傫����Ȃ����ᗎ�����B������c�O�I
�@
�@�Љ��E���U�w�K���߂��鍑���̐���E�s���̓����������C���Ȃ̂ɑ��āA���ۓI�Ȓ����͊����ȓW�J���݂��Ă���B�܂��A���I�Z�N�^�[�̐���������Ă���̂ɑ��āA���Ԃ̎s����������H�͂���܂łɂȂ��傫�ȑٓ����n�܂��Ă���A�ƌ����邾�낤�B
�@���N�̃[�~�́A���̂悤�ȏ̂Ȃ��ŁA�����Ă����̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA����܂Ń[�~�^�c�͊�{�I�Ɋw������̓I�ɒS���A����E�����E���R�̐��_�ł������ƍl���Ă����B�Ȃɂ����A�w�����ꂼ��̉ۑ�ӎ��A�����e�[�}�i���Ƙ_���e�[�}�Ɍ��т��j�d���A�������Đ[�߂邱�Ƃ�厖�ɂ��Ă�������B���_�[�~�����g�B�ʂ����Ă��܂����������낤���B
�@�[�~�S�������Ƃ��Ă̔Y�݂�����B��ɂ́A�w�����N�̂��ꂼ��ʂ̖��ӎ��E�e�[�}����{�ɂ��A��ɂ́A�܂��œ����Ă���傫�ȏɂ��Ă̔F�����ǂ��[�߂邩�B���N�́A���Ȃ��Ƃ���҂ɂ��ẮA�[���Ȏ��g�݂ɂȂ�Ȃ������B�܂��A���⒬�c���t�B�[���h�ɂ��āA�[�~�Ƃ��Čp���I�Ȓ����������d�˂Ă��������ƍl���Ă������A���N�͂��̗������̂̃t�B�[���h���[�N�͑O�i���Ȃ������B���N�ȍ~�̉ۑ�ɂ��悤�B
�@�������A�[�~�̂Ȃ��ŁA�u�n���u���O�錾�v��m�o�n�@����肠������A���{���h�ł́A�����ɃN�C�Y�ɏo�肵�Ă��ꂽ�B�[�~�Ƃ��āA���E���c�͕����Ȃ��������A�ʂɁu�ӂꂠ���فv�����ɎQ�����������o�[���������A�u�䂤�����v�ɍs�������A���{�ɂ͂Q����s�����B�Ȃɂ����l���ǂ�����[�~���ɘa�̎R�A�O�d�Ȃǂɏo�����A�퍷�ʕ������ɂ��ăt�B�[���h���[�N�����݁A�Q���̃��|�[�g�W��n�����̂ɂ͋������B�a���[�~�炵���G�l���M�[���B
�@�[�~�����i�O�E����A��⌳�C�̂Ȃ��т�����܂߂āj�̏��N�A���h�A��v�A�~�j�R�~�A���̃��|�[�g�W�쐬�Ȃǂ̊e�S���A�����I�ɘJ��ɂ��܂Ȃ��������ׂĂ̊F����A����J���܂ł����B�@
�@�����܂���
�@1998�N�́A�t���牫��E���A�W�A�Љ��̌����ʐM�y��̕��z�M���Ă����B���̈Ӗ��ł���܂łɂȂ��N�ƂȂ����B99�N�Q�����݁A180���𐔂���B�قڂQ���ɂP��B�e�������ɁA���L�����̋Y��̂��ڂ���K�킵�i���܂�̐ق��ɊF�����čŌ�܂œǂށH�j������A���̒��ɂ͘a���[�~�����Ɋւ��Ă��r�̂�����B�����ʂ�̐ى̂����A�L�^�Ƃ��āA�����������Ɏ��^���Ă������Ƃɂ��悤�B�Ȃ�����Ƃ����сi�s�n�`�e�`�d�b�j�ɃA�N�Z�X���B
�@�d���[���Ffumito.kobayashi@ma2.justnet.ne.jp
�@�z�[���y�[�W�Fhttp://www2.justnet.ne.jp/ ~fumito.kobayashi/
�@==============================================
�@�Y��̃V���[�Y�i1998�`1999�N�j
�@�@ �@�@�@�@�@�\�쉈���̓��A�w�����������琺�����Ă����\
�������ߌ��̗���Ɍ�Ђ��ݐ��������ь�ĂԐ����� (5/7)
���������a���̍�ɂ��ǂ����܂����Ƃ��^�̍��� (6/4)
�����̒|�͎��[��|�����R�ɂ������Ȃ����ƒ��莆�̂��� (���[�̉�A7/7)�@
�������S���̎�l�ӂ���ނ�Ń`���M�X�E�n�[�������z�ŏ��� �i7/12�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�S���w���́u���z�v�i��M�j�\�@�@�@�@�@�@�@
�����̃[�~�Łu�����v�ɂ͂��߂ďo������ƈ₹�������ɐ����̂��� (9/12)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�a����w�L�����p�X�̋��؍ҁA10/7�\
���Ԉ֎q�̃X���[�v�����ɉԂ�����u������v�u�������v�Ƃ����Ȃ��@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�ߌ���̂قƂ�A�`����\
���䂪���͊`�̎��F�Â��������ї���̕��Ɍ�Q��Ђ��� (10/3)
���g���`�̎��ЂƂ�i���j�݊������ɔG��H�̃J���X�Ⴍ��т䂭 (11/27)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�[�~�E�R���p�A�A���R���E�g���\
���|���|�g�ɕv�D��ꂵ�������̂��闿���͌������h�� (10/21)
�����Q�������Ă₳���������l�͓V���̔@���w���������� (�Z�^����,�@10/21)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\���{���h�A��ԉ���\
���[�X�̏h�̍L�Ԃɂ݂ȗx��_���X�E�Z���s�[�̗U���Ɏ䂩�� (10/25)
�����߂��K���̑����S�n�悭�q��̂ɂ����H�������� (10/25)
�����炶��Ɩ�͖������߂���ԏh���ӂ�邨�����������y���� (10/25)
���Ԃ���Љ����Ⴋ��̃N�C�Y�̑f�ނɂ��Ƃ��߂�ꂵ (���₫�̗��A10/25)�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\���{�E�ړ���w�A���n���H��Ձ\
������̉��O���߈Í��̊�ǂ̕����M��������� �i11/29�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\���i���A�O�����E���[���\
���N�̐��̃[�~�̃R���p�̃r�[���悵��炢�����~��X���䂭 (12/21)
�@�@�@�@�@�@�@�@�\�Q���T���A���_���\��A�R���p�E�̂ނ��\
���̂�т�ƗV�ѕ�点���w�������_�����Ί�Ђ����܂� (2/5)
���M�B�̎����݂��킷�ʂꉃ�u�ԁv�̂������v������܂� (�̂ނ��E���ʉ�A2/5)
�@�@(�����N�̑��Ɛ������́u�Ԃ�v�ƈꏏ�ɘa����ɓ��w����1995������)
![]()
13�C���������傤�ł��i�s����ΌZ��)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a����w�E���ѕ��l�v���[�~���ꍇ�h�W�i1998�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@��������Əo��A�����e�[�}��̈��l�̂悤�Ɉӎ����n�߂āA����ɒʂ��n�߂��̂�1976�N�A����20�N���z���܂����B����Ljꏏ�ɉ���𗷂����a����w�P�N�v���[�~�̊F�����܂��O�̂��Ƃł��B�@
�@����܂ʼn��x����ɍs�������Ƃł��傤�B�����邱�Ƃ��o���܂���B����N�Ȃǂ͖�������ɏo�����܂����B������P�l�ł͂Ȃ��A�����N����U���ē��₩�ɖK�����Ă��܂����B�قƂ�ǎႢ�l�����ƈꏏ�ł��B
�@����̗F�l�������A���̂��Ƃ��悭�m���Ă��āA�u�Ԃ�v�搶��������A�W�܂��ĂƂ��Ɍ�肩���݉̂����p�ӂ��Ă���܂��B����������ł����B�ߔe�ŁA�Ƃ��ɖ���̔����ْ���ł́A���}��ȂǖY��邱�Ƃ��ł��܂���B�u���������傤�ł��v�Ƃ�������̐S�̉������A�D���������炽�߂Ď����������܂����B�L�����Ƃł��B
�@����̉���̗��́A�ЂƂ��ƂŌ����A�y�������ł����B�y���������Ƃ������Ƃ́A���e�I�ɂ��[���������ł������ƌ�����ł��傤�B�]�C���c��A�z���o����݂�����܂��B�v���[�~�̊F������悭�������A�����ɓ����A���܂艓�������A�a����炵�����R�ɗ������Ă��܂����B���̂��Ȃ��i�������P�_�̂݁j�������ł����B�v�����܂܂ɁA����ǂ̗��ň�ۓI�Ȃ��ƁA����܂łɂ��Ȃ��������ƁA���������Ȃ�ɏ����Ă����܂��傤�B
�P�C�䕗18���P���ɂ��P�������������B�䕗�ŋA��Ȃ����Ƃ͂��������A�s�@���Ȃ��������Ƃ͏��߂āB�i���ꂾ�����O�w�K���[�������A����A�K���������@���ł͂Ȃ��H�j�@�@
�Q�C�S�J���[�̕\���i��������j�E�p���t�Q�������ꂽ�B
�R�C�암��Ղ߂���̂P���A�Ȃ�ǂ��܁A��̊��}��ł��������l�������B
�S�C�C�����H���z���āA�Ɍv���̓��[�ցB�F���j���ł���ԁA���]�[�g�z�e���́@�T�����Œ��Q�����B
�T�C���C�݂Ɛ��C�݂ŁA��x���j�����B
�U�C�ǒJ�ł́A�W�c�����̃`�r�`���K�}�A�~�����A�̃V���N�K�}�ցB
�V�C�d�́u�g�x��v���͂��߂Ċӏ܂����B�i�u�Ђ�Ղ���܂�v�̍L��j
�W�C����̊��}��A�����ق̒���A�H�̌��A�u����D�v�̊��}�G�C�T�[�B
�X�C���a�́u�����Ł[���v�A�����ł��H�̖����B
10�A�ŏI���A�ߔe�E�p�s���I���͘a���v���[�~�Ő苒���ꂽ�������B�u�Ɂ[�ȁv�@����������̉̂�⏥�B�u�V�����̎�̒a���v�ƊC�����L�͑��۔��A�ȂǂȂǁB
�@�@
�@�����m�邱�Ƃ́A�A�W�A��m�邱�Ƃł���A�A�����J�i�ɓ��헪�j��m�邱�Ƃł��B����������ƌ��Ă���ƁA���E�������Ă��܂��B����Ȏ��_�ŁA���{�𑨂��������A����̓��{��I�Ɍ��߂Ȃ����A���������ڂ����ꂩ��b���Ă����Ăق����B����̐l�����̐S�Ɗ��҂ɉ����Ă����������̂ł��ˁB
�@�������̒Ҍ��A�����i�G�j�A����A����ɋ��͂����F����A����J���܂ł����B�@
2000�N�����āA�V�������݂����҂��B�@�@�@ 99�c�v���[�~�A�S���@���ѕ��l
14�C1998���уv���[�~���I����ā@�i�[�~�W�E1999�N1���j
�@���Ƃ��̃v���[�~�̃e�[�}�́A�u�n��Ɛ��U�w�K�|���Œ��ׂ�v�Ɛݒ肵���B����܂ł̎����̕��ł́A�݂ȓ��ōl����w�K���������Ă����B�������A�{�̂Ȃ������łȂ��A�܂��̐�����Ԃ̂Ȃ��ɁA�����Ēn��E�Љ�̂Ȃ��ɁA���܂��܂̋����[���u�l�Ԕ��B�v�̐���������������B����ɐG��Ă݂悤�A�n�������Ă݂悤�A�����Ȃ���l���悤�A�ł���Ή���̒n�ɂ������Ă݂悤�A���������Ăт����Ŏn�܂����i�u�`�v��p152�j�B
�@�W�܂��Ă����v���[�~�A�̊F����́A�{�W�E���|�[�g�ɋÏk����Ă���悤�ɁA�Ȃ��Ȃ���̓I���ϋɓI�Ȏp���ŎQ�����Ă��ꂽ�悤�Ɏv���B��������w���w����̏��߂Ẵ[�~������A�˘f��������A�܂��͍���Ȑ܂��������킯�����A�[�~�̕��͋C�Ƃ��Ă͐��������Ɗ����ȃX�^�[�g�����邱�Ƃ��ł����B�ŏ��̎��Ԃ̎��ȏЉ�A�����ă[�~�̊����A���h��R���p��~�j�R�~�Ȃǂ̒S�������߂�o�߂̂Ȃ��ŁA�݂ȗ����Ɍ��A�܂����炷����Ŏ�������Ă��ꂽ�Ƃ��ɁA�u�������A���̃[�~�͂��܂��������v�Ƃ����\�����������B
�@���܃[�~�̏I�����}���āA���̂P�N�������A�قڊ��Ғʂ�̓W�J���݂邱�Ƃ��o�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�[�~�����̒��S��S���Ă��ꂽ�k���A�쓇�̗������͂��߁A�e�S���̊F����A�[�~���ׂẴ����o�[�Ɋ��ӂ������B
�@���ꂼ��̊S���o�������������ŁA�[�~�͎n�܂������A���ʓI�ɂ́A�����镟���ǁA����ǁA�����ĉ���ǁi�����Ɛ푈�̃T�u�O���[�v�ɕ������j�̂R�Ȃ����S�O���[�v�̕Ґ��ƂȂ����B���̊ԂɁu�[�~�̐i�ߕ��v�u�R�O���[�v�̉ۑ�Ɋւ��邢�����̒�āv�u�[�~�㔼�̐i�ߕ��v�i�ʎ��P�C�Q�C�R�j���N�������A��ȗ���Ƃ��ẮA��{�I�Ɋw�����̎���I�ȉ^�c�ɂ䂾�˂��B�R���p�E���h����悳��A���ꗷ�s�i���h�[�~�j�̌v�悪�i�߂�ꂽ�B
�@�������A�ŋ߂̃[�~�ɂ͒������o�������������B���Ƃ��ŏ��̃R���p�Ő̂̊w���̂������������ƁA���h�ł͒j�q�w���i�Q�l�j�̎Q�����Ȃ��A���q�w�������Ɉ͂܂�Ȣf�������ƁA���ꍇ�h�̃X�P�W���[���ɍ��킹��悤�ɑ䕗18
�����P�����A�P�����̉�����������ꂽ���ƁA�ȂǂȂǁB���������ʓI�ɂ́A���v��͂قڏ����ɐi�s�����B
�@����O���[�v�́A���̕��Ƃ͕ʂɁu���ꍇ�h�W�v�i�S58�Łj��ҏW�E���s���Ă���B���O�̂Q���̃p���t�ƂƂ��ɁA���̋L�^�E���z�𗦒��ɋL�^�������͖ʔ����o�����ł������B�ʎ��S�͂����Ɋ�e�����ꕶ�ł���B
�@�@�@
�@������ׂĂ����܂��^�킯�ł͂Ȃ��B�������ۑ���c���Ȃ�����A�����Ƀ[�~���i�s�����̂́A�w���̎�̐��ɂ�鎩��I�ȉ^�c�A�ϋɓI�Ȕ����E��āA�~�j�R�~�̔��s�A�R���p�ƍ��h�A���ԂÂ���A�Ȃǂɂ����̂ł��낤�B����̃[�~�����Ɋ������ق������̂ł���B�Ō�ɁA���̕W�̕ҏW�ɂ��������ҏW�ψ���A�Ƃ��ɖؓc�A�H����A�k��̂R��\�A����J���܂ł����B
![]()
15�C�w�����g�ɂ���̓I�ȃJ���L�������Â���ɂނ��Ắu�Θb�v
�@�@�@�@�@�@�a������w�l�ԊW�w���E�T�N�Ԃ��ӂ肩�����āi2000�N4���j
�@�@
�@�͂��߂Ɂ[�l�Ԕ��B�w�Ȃ̂T�N
�@���̂T�N���ǂ��������邩�B�U�肩�����Ă݂�ƁA�V�w���̑n�݁i1995�N�j�Ɠ����ɘa����w�ֈڂ��Ă����킯������A�n�݊��̐l�Ԕ��B�w�Ȃ̈���Ƃ��Ă̑����Ɠ����ɁA�Ȃ�����w���t�����̂Ȃ��̍ŋ߂T�N�́A�������g�̑����Ƃ����Ӗ������������Ă���B
�@�O�ɋΖ�������w�ł́A�i�����{����w�A����E���Ƌ��@�̘g�g��O��Ƃ��Ă����W����j���ΓI�ɃJ���L�������̍\�����ł��A�K�C�Ȗڂ̔�d���傫���A�w���ɉۂ��ׂ����ƉȖځE�P�ʂ���������Ɗm�肵�Ă����B���ꂾ���ɁA�a����w���Ǝ��Ɍ`�Â����Ă����������̓����A���Ƃ��ΐL�т₩�ȃJ���L�������̍\���A���R�ȑI�𐧁A�w�����g�ɂ���̓I�ȃJ���L�������Â���̔��z�A�����ăJ���L�������̏_��ȏC���i�̉\���j�A�ȂǑΏƓI�ɂ���߂ĐV�N�Ȃ��̂��������B�u���R�Ȋw�K�ƌ����̋����́v�Ƃ����L�[���[�h�����ɐS�n�悭�������B�ŏ��̂P�N�́A�V�����w���E�w�Ȃ̈���Ƃ��Ă̈ӗ~�ƁA���ʁA����܂łƂ͂��Ȃ菟�肪�Ⴄ���Ƃ��炭�鎄���g�̍��f���������B
�@��R���E���\���鋳��w�ҁAP.�t���C���i�u���W���A1921�`1997�j�̊w�����Љ���̂Ȃ��Ɂw�`�B���Θb���x�i���I���[�A1982�j�Ƃ������������B�w�K�҂��J���b�p�̊�ƍl������ɋ��t���m���߂���ł�����s�^����̔ᔻ�ƁA����ɑ������N�^�̋���A�l�ԉ��E�ӎ����Ƃ��Ă̎����E�w�K�ȂǁA��������Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��B���͘a����w�̃J���L�������Ɗw�������ɏo����āA���炽�߂āu�Θb�v�̈Ӗ����l���������Ă����B����܂ł̑�w�ł̍u�`�E�[�~������߂āu�`�B�v�I�Ȏp���ł͂Ȃ��������Ɣ��Ȃ�����ꂽ�B
�@�����ɁA�T�N�̍Ό��̌o�߂̂Ȃ��ŁA�a����w�E�J���L���������߂������O�ƌ����Ƃ̂���A�����Ǝ����̃M���b�v�̂悤�Ȃ��́A�ɂ��Ă��l���������Ă����B��������̓I�ȂƂ��납��A���ܑ����Ƃ��Ď����₤��Ƃ��L���Ă��������B
�@�v���[�~�ł̎���
�@���̑�w�ł͂��܂�Ⴊ�Ȃ��P�N���́u�v���[�~�v�́A�����ʂ菉�߂Ă̌o���ł������B�R�C�S�N�����w�@���̐��I�ȃ[�~�̃C���[�W����E�炵�āA�܂��w��Ƃ������Ƃ��̐��E��m��Ȃ��A���ꂾ���t���b�V���Ȏ�҂����ƃ[�~�̏W�c������Ƃ����̂͐����y���݂ł������B1995�N�A97�N�A99�N�̂R��A��������e�[�}�́u�n��Ɛ��U�w�K�v�Ɛݒ肵�A���L�����̊g����̂Ȃ��ŁA�Q���w�������ꂼ�ꎩ�Ȃ̌����e�[�}�i�����A�l���A��Q�Җ��A�s�������A�����فA�w���ۈ�Ȃǁj�����Ă����A�ʂ̃e�[�}�����т����Ă������̃T�u�E�O���[�v������A����ɉ����Ċe�N�x�Ƃ��ɉ�����ɊS�����O���[�v��݂��A����ւ̌������s�i��P�T�ԁj�����{����A�R��Ƃ�����ȗ���Ńv���[�~���^�c���Ă����B
�@�S���҂Ƃ��Ă̎v���́A�O�́u�o��v�������������Ƃ������ƁB���Ȃ킿(1)���ꂼ��ʂ̌����e�[�}�Ƃ̏o��A(2)�n��Ƃ̏o��A�t�B�[���h���[�N�̎��݁A(3)���ԂƂ̏o��A���݂̕��S�ɂ��[�~����^�c�A�ł���B���̊ԂɁA�~�j�R�~�i�[�~�V���j�A�R���p�A���h�A���d�������B�R��Ƃ��ɂQ�O�O�y�[�W�O��́A������Əd���[�~�W�s���邱�Ƃ��o�����B
�@�ŏ���95�[�~�́A����ŕĕ������\�s�������N�����N�ł���A��⋻���C���ɉ��ꗷ�s���������Ƃ��z�N����邪�A�܂��܂��̐����A�Q��ڂ�97�[�~�͂������q�Ői�s���Ȃ���A�Ȃ����㔼�Ɏ����A���N�x99�[�~�͎Q���w���̎��R舒B�Ȏ��g�݂ɂ���đ听���A�Ƃ����o�߂ł������B�v���[�~�̌o���̂Ȃ��ŁA�Ⴂ�w�������Ƃ́u�Θb�v�̈Ӗ���
��䍂��A�u�`�B�v�I�p���������Ȃ߂��Ă�����������B
�@�Љ��_�E���U�w�K�_�Ȃ�
�@�l�Ԕ��B�w�Ȃ͑n�ݎ���肱�̓�̉Ȗڂ���ȖڂƂ��Ĉʒu�Â��Ă����B�����ɕ����ȁu�Љ��厖�u�K���K���v�ɂ��u�Љ��_�v�́A�Љ��厖�E�}���َi���E�����يw�|���̂��ꂼ��̎��i�擾��̕K�C�Ȗڂł������B�����1996�N�W���̓��ȗ߉����ɂ��A1997�N�x�ȍ~�́u���U�w�K�_�v���K�C�Ȗځi�u�Љ��_�v�͑I���Ȗځj�ƂȂ����B�a����w�J���L�������̂Ȃ��Łu�K�C�v�ȖڂƂ����̂͂ނ����O�ŁA��r�I�Ɏ�u�����������i��100���j�A�l�Ԕ��B�w�Ȃ̊w���ɂƂǂ܂炸�A���w���E�w�Ȃ̑��l�Ȑ�U�̊w�������܂��܁i���i�擾��̕K�v����j��u���Ă����B���̂��ߕs�{�ӂȂ���T�_�E��b�_�I�ɍu�`�`���Ői�߂�Ƃ����X���ɂȂ肪���ł���B�����ʂ�u�`�B�v�I�Ȏ��Ƃ̂������ł���B���l����ɂ�����Ƃ̒��łǂ̂悤�Ɂu�Θb�v�����݂Ă����������N�̔Y�݂ł���A�ۑ�ƂȂ��Ă����B
�@�Ƃ��ɃQ�X�g�u�t�������A���⒬�c�Ȃǎ��ӎ����̂̎Љ��E���U�w�K�̂Ȃ܂̘b����ꂽ��A�r�f�I�f�������p���Ċ��z���o����������A�܂��ċx�݂̉ۑ背�|�[�g�i�����̌��w�E�����j�ɂ��ƂÂ��w������̕����߂��肵�Ă����B���̂悤�Ȓ��K�͂̍u�`�`���̎��Ƃ��ǂ̂悤�Ɂu�Θb�v�I�Ɋ��������Ă������A����ɒ�������݂����Ƃ���ł���B
�@�u�Љ��_�v�i1997�N�x�ȍ~�j�́u�������Ƌ�����H�v���e�[�}�Ɍf���āA�ނ�����_�I���[�~�I�ɉ^�c���Ă����B����i�\�Ȃ�����j�������E�����Ɋ�Â��w���̃��|�[�g�A���̃~�j���N�`���[�A�֘A����r�f�I�f���A�̂R�҂�g�ݍ��킹����Ƃ���悵���B�����炭�w�����x���̎��ƂŎ����iLiteracy�j����^���ʂ����肠���Ă����́A���{�̑�w�ɂ��܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���邪�A��u�w���͐V�������Ƃ̏o��i��Ԓ��w�A�퍷�ʕ����̎������H�A�����̂̓��{�ꋳ���A���ۓI�����Ȃǁj�ɋ����������ĎQ�����Ă��ꂽ�l���������������悤�Ɏv���B
�@���ƈ�A�֘A���Ă��̂T�N�ԁu���C�t�X�^�C���Ɗw�K�v�i���ʋ��{�E����̉ۑ�j��
�S�����Ă����B�傫����̒��ŁA�܂�O���͒n��̕��������^���E�s�������ɂ��āA�㔼�͎����j�̐��E��������Ƃ����e�[�}�ŁA��͂��̓I�Ȓn�掖�����H�I����������Ƃɂ����āA�ł��邩����[�~�I�ɐi�߂Ă����B
�@���ȖڂƂ��ɕK���Q�X�g�u�t�������Ȃǂ��āA���p�I�Ɏ��Ƃ������߂�w�͂����Ă�������ł��邪�A��u�w���������ǂ�قǂ̏[�����������Ƃ��ł��Ă��邩�A�������ۑ�͎c����Ă��邾�낤�B
�@
�@���U�w�K�_���K�i�R�E�S�N�[�~�j�Ƒ��Ƙ_���쐬��
�@��L�̂悤�Ȏ��ƉȖڂɏd�˂āA�R�E�S�N�[�~�i���U�w�K�_���K�j�Ƒ��Ƙ_���w���ւƐi��ł����킯�ł��邪�A�������̔Y�݂��������Ă���B
�@�u���U�w�K�_�v�u�Љ��_�v�����āu���C�t�X�^�C���Ɗw�K�v�̂悤�ȊW�Ȗڂ̗��C���i�������s�I�ɂł��j�ςݏグ�Ȃ���A�R�E�S�N���U�w�K�_�[�~�ɎQ������A�[�~�ł̘_�c�⒲������b�ɂ��đ��_�e�[�}��ݒ肵�A���ꂼ��̉ۑ�ɒ��킵�Ă����_���Ɏd�グ��A�Ƃ����\���I�Ȑςݏd�˂̗�����Ȃ��Ȃ��n��o�����Ȃ��̂ł���B
�@�w�������́A���ʂɕҐ����ꂽ�a����w�J���L���������A�����炭�ő���Ɋg����ꂽ�I���̎��R�����p���āA����₱���ƁA���邢�͂����������ƁA���C����B�M�S�Ȋw�������͂���ɋ����Ƌ��⎑�i�擾�̂��߂ɕK�v�ȒP�ʁi�����ɂ͕K�C�����邩��S�������j�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����w�ɔ�r����ƁA��������ƕʘg�ł̕K�C�P�ʂ��p�ӂ���Ă���i�ǂݑւ��K�肪���Ȃ��j����A�Ȃ��ɂ͖Ƌ��E���i�擾�̎��Ԋ��Ґ��ƒP�ʎ擾�ɒǂ��Ĕ�J���ނ̗l�q��������B
�@���Ȃ̃e�[�}���[���Ɋm���ł��Ȃ��܂܁A���_�E��ڂ̒�o�������}���A�Y�ފw�������Ȃ��Ȃ��B����܂ł̒P�ʗ��C���A���l�ɉ��ɍL�����Ă͂��邪�A�����Ӗ��ŏc�ɒ~�ς���Ă��Ȃ��̂ł���B�I�𐧂̎��R�̊y�����Ɍ��f����ė��C�͑��ʂł��邪�A���Ƃ��Ɗ��҂���Ă���u�w�����g�ɂ���̓I�ȃJ���L�������Â���v����������o���Ȃ������Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�����ĂR�D�S�N�[�~���}���A���ӎ��������\�͂��[���ɒb�����Ȃ��܂܁A���_����ɓ˓����Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̖��ɂ��ẮA�����炭�w���Ƌ������Ƃ̑o���̎��o�ƐӔC�������K�v������Ƃ͎v�����A��v�ɂ͂�͂苳��������̊w���ɂނ��Ă̐ϋɓI�ȁu�Θb�v�̎p���Ɠ����������ア���ƁA�w�ȂƂ��čH�v���ׂ��u�Θb�V�X�e���v���s�[���ȂƂ���ɉۑ肪����悤�Ɏv���B�w���̎�̐��Ɩ��ӎ��̗c���͓��R�̂��Ƃł����āA���́u���B�v�\���Ɋm�M�������A����������Ɖ������Ȃ��Ŏh�������N���u�Θb�v�I�ɓ��������Ă����K�v�����ܒɊ����Ă���B
�@�{���́A�w�Ȑ��Ȗڂ̃J���L�������ƖƋ��E���i�J���L�������̑��݊W�ɂ��āA
�܂��J���L���������̃[�~�����Ɗw�O�E�n��ł̃[�~�����A���邢�̓t�B�[���h���[�N�̖��ɂ��āA�_��i�߂����Ƃ���ł��邪�A���łɗ^�����Ď����������Ă��܂����B
![]()
16�C��w�ƒn��ƁA����Ɠ��A�W�A�� �[���̃[�~�i�[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a����w�w���� ��253�i1999�N9���j
�@
�@��w�̂Ȃ��́A����u�������E�[�~�i�[���v�i�Љ��_�E���U�w�K�_�[�~�A�v���[�~�j����������{�I�ɏd�v�ł��邪�A���ꂾ���łȂ��A��w�̂��Ƃ́u�n��E�[�~�i�[���v�Ƃ������������厖���A�ƍl�������Ă����B
�@�����āA���̓�̃[�~�����݂ɋ��������A�A���������������悤�ȊW��͍����Ă����B���������ۂɂ́A�Ȃ��Ȃ����܂��s���Ȃ����̂��B
�@���ƊO�̓�̃[�~�̔��z�́A�������ƒn��A���_�Ǝ��H�A�v���ƃt�B���[�h���[�N�A�����т��悤�Ƃ������݂ł���B�K���ɘa���̊w�������́A�������̂Ȃ��ɕ�������̂łȂ��A�t�B���[�h�ɏo�邱�Ƃɋ������������o�[�����Ȃ��Ȃ��B����͊��������Ƃ��B
�@
�@��w�̊O�́u�n��E�[�~�i�[���v�Ƃ́A���̏ꍇ�A��w�̎��ӂ̒n��i���A���c�Ȃǁj�A����A���A�W�A�A�ɂ��Ă̌��������ł���B�O�ɋΖ����Ă�����w�܂ők��A���ꌤ���͂�����\�N�̍Ό����d�˂Ă���B
�@���݂́A�������̌����T�[�N�������̂��āu�����E����E���A�W�A�Љ�猤���t�H�[�����v�i�s�n�`�e�`�d�b�A��\�E���сj�Ƃ����A�����ɂ��~�������̂̌���������Ă���B�����҂�����A�����̐E���A�s���A����w�̉@���A���w���Ȃǂ��Q�����Ă���B��ጤ����͖������A�����Ă̏��у[�~�̐�y������A��ʂ̎s���̎Q��������B
�@����Z�N����͔N��w���A�W�A�Љ�猤���x�����A�����E���ꂾ���łȂ��A�؍��E�����A��k������̊�e�����^���Ă���i���݁A��l����ҏW���j�B��w�̊O�̂��̂悤�Ȍ��������ƁA��w�̓��́u�������E�[�~�i�[���v���Ȃ�Ƃ����т������Ɗ���Ă����B
�@�����N�̕��݂�U�肩�����Ă݂悤�B�����̒�ጤ����i���T��O���j���E��j�̂��Ƃ͕ʂɂ��āA���N�͏�������A�C���z���āA�������U�����������B�����͏t���牏�N���������A�Ƃ����������ō��N�̗�͎n�܂����B
�@�܂�������a���i�O�A�l�N�j�[�~�̗L�u�Ɗ؍��ցi�O�E����͂���ň�T�ԁA���N�̍P��s���j�A�O�����{�ɂ͗^�ߍ��i���������A�������w���̎Q���͋��߂��j�ցA�l������܌��ɂ����āA�Ăъ؍������Ē�������̏��ق��A�\�E���[��C�[���K�[�L�B�ւƗ��������B�\�E���܂ł́A�����Ẵ[�~���i�n�f�j�����s���Ă��ꂽ�B
�@�؍�����̏��قł́A�u�؍��������狦��v�N���i��\��j���ŁA���{�̎������Ɠ��A�W�A�Ԃ̍��ۓI���͂ɂ��Ă̍u�������߂�ꂽ�B�u�����v�Ƃ́u�����v�̂��Ƃł���B�؍��ł́A���{�̐A���n�����̐[�����Ƃ��āA�������[���Ȏ��������������Ă����B�؍��̎Љ��E���U���猤���̌n���ł́u�����v������ɂ��Ă͌��Ȃ��B�؍��̌����ҁi���@���Ȃǁj�����ɐG������āA���{�̎�����蒲���ɑ��ݓ��ꂽ�����A�t���i�̊؍��������狦��̖ʁX��O�ɂ��Ęb������Ƃ������Ƃ́A�Ȃ�Ƃ����h�Ȃ��Ƃł������B
��C�ł͉ؓ��t�͑�w�Ƃ̌����𗬁A�}�k��Ɨ]��w�Ƃ̍���w�@�Â���̋��c�A���K����эL�B�ł́A���ꂼ��̑�w�⋳��ψ���ł̍u������Ȏd���ł������B
�@�̂Ɣ�r����ƁA�z�����ł��Ȃ��g����ŁA�C���z���āA�����𗬂��\�ɂȂ����B���́u�Љ��_�v�ł͋�̓I�Ɂu�������H�ɂ��āv�����Ƒ�ڂɌf���Ă��邪�A�؍��́u��������̎��H�v�ɐG��邱�Ƃ��\�ɂȂ����B���N�O���̊؍��K��ł́A���ۂɑ�緎s�̐V�⋳��u���������v���w���L�u�ŖK�₵���B
�@�u�v���[�~�v�ł͋㌎���{�̉��ꗷ�s���v�撆�ł���B�u���U�w�K�_�[�~�v�ł͐��E���c�Ȃǂ̃t�B���[�h�T�[�x�C�Ɉӗ~�I�Ȋw�������g��ł���B�������Ă݂�ƁA��w�̓��ƊO�Ƃ̃[�~�i�[���̌����́A�������Ân�܂��Ă���悤�ɂ��v����B
�@�������������ۑ�͏��Ȃ��Ȃ��B�Ȃɂ����A�̐S�̓��Ȃ�[�~�i�[���̋ÏW�͂�����Ɏキ�Ȃ���邱�Ƃ��C�ɂȂ�B�����Čo��̖�������A�O�Ȃ�[�~�i�[���ւ̎Q���͂��ׂāu�w���L�u�v�̊����ɂƂǂ܂�B���ꂩ��ǂ̂悤�ȓW�J�ɂȂ邩�A����ɖ͍��ƒ���͑����̂ł��낤�B
![]()
17�C�n��Ƒ�w�̏o�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���C�������猤�����w��w�Ƌ���x��31���i2002�N�j
�@���Ƃ��Ɠ��{�̑�w�́A�n��Ȃ����͎Љ�E�s���̂Ȃ�����G�肵���W���Ă����Ƃ������j�������Ă��Ȃ��B��Ƃ��č��Ƃɂ���đn�݂���A�����⎄���̑�w�ƌ����ǂ��A���Ƃ���߂��ɍS������ĉ^�c����Ă����Ƃ����̂���v�ȗ���ł��낤�B�n���s���̑����A����̎Љ�I���u�Ƃ��āu��w�v��n��o���Ƃ����ӎ���^���ɂ����āA����܂Ŏ��o�I�ȔF���������Ƃ��ł��Ȃ������B
�@���̂悤�ȓ��{�E��w�j�̓������A������тȑ̎��Ƃ��đ�����悤�ɂȂ�_�@�����ɂ͓�������B��́A�\�㐢�I�㔼�́i���Ƃ��C�M���X�́j��w�g���^���̗��j��m�����Ƃ��ł���B�����ɂ͑�w���g�J���g���v�w�͂Ɩ��O����^���̑ٓ����������B��w���J���Ƃ����w�͂́i�P�Ɍ��J�u����݂���ɂƂǂ܂炸�j��w�̕��������������E�炵�悤�Ƃ���ߑ㉻�ւ̉��v�ƘA�����Ă������A�܂���������߂閯�O����^�����ĂыN�����A�J���ҋ��狦��i�v�d�`�j���̑g�D���ɂȂ����Ă������̂ł���B
�@���ƈ�́A��O���{�ɂ����Ă��ގ��̑�w�J���̓w�͂��݂�ꂽ���ƁA�܂��n��̂Ȃ��ɂ����O��w��n�낤�Ƃ���͍��������������ł���B���Ƃ��Ζ������̓������w�Z�i���E����c��w�j�Z�O����^���Ɍ�����u�w�̓Ɨ��v�u�Љ�I�ȑ����v�u�J���ꂽ��w�v�ւ̎��g�݂��������i�c�����j�w��w�g���^���̗��j�I�����x��㎵���N�j�B���邢�͑吳�f���N���V�[���́u�M�Z���R��w�v�̎��݂́A�܂��ɒn�悩��̖��O�ɂ���w�Â���^���̋M�d�ȑ��Ղł���B�������A�������炪���{�̑�w�j�̎嗬�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ������B
�@�M�Z���R��w�ɂ��āw�͂ꂽ��}�x�i���Ⓖ��A���Z���N�j�������ꂽ�悤�ɁA�����͐�O�̍��Ǝ�`�I����̐��̂Ȃ��ɖ��v���A�����Č͂�Ă������̂ł���B
�@��㋳����v���ɂ����āA��w���v�͂ǂ̂悤�ɐi�W�����̂��B�{�_�̎��ɑ����āA��w���Љ�ɊJ���A��w�ƒn�悪�o��A���̋����A�Ƃ������_�ɂ����Ă݂��ꍇ�A��㋳����v�͎c�O�Ȃ��琬�������Ƃ͌�����B���{�̑�w�͈�ʂŐ��I�ȒE����Ƃ��A�������A�Ȃ����I�Ȑ��x�̂Ȃ��Ɉ��Z���Ă��łɔ����I���o�߂������ƂɂȂ�B�����Ă��܁A�s�����v�H���̊O���ɂ��u��w�̍\�����v�v�̗��ɋꂵ��ł���Ƃ����̂�����ł��낤�B
�@���ꂾ���ɁA���܂��炽�߂āu�n��Ƒ�w�̏o��v���ۑ�Ƃ��Ė���邱�ƂɂȂ�B���̓_�ł͈���Z�N��ɂ͐V����������Ă����悤�Ɏv����B��͐��U�w�K�̒����ł���B���U�w�K�U�������@�i����Z�N�j���̂́i�c�O�Ȃ���j�ꌾ���u��w�v�ɂӂ�Ă��Ȃ����A��Z�N��̒�������R�c����w�R�c��̓��\�́u���U�w�K�@�ւƂ��Ă̑�w�v�̖�������A���U�w�K�R�c������J�����g����ɂ��Č��y���Ă���B���܍ĕҐ������߂��Ă���S���e�n�̋���n��w�E�w�����ł͐��U�w�K�Z���^�[�ݒu���吨�ƂȂ鎞��ƂȂ����B
�@���܈�́A�n��̐V���������ł���B����܂łɂȂ��W�J�������Ďn�߂Ă���n��E�����̂�����B�e��̎Q���^�s�������A�m�o�n�I�g�D�A�{�����e�B�A�E�l�b�g���[�N�A���������E�w�K�����^�����̐V�����W�J�B�����ł͌���I�ۑ�Ɏ��g�ލ��x�����H�I�Ȓm���E�Z�\�E�v�z�E�^���ւ̊w�т����߂��Ă���B�n��Ƒ�w�̏o��̐V���Ȍ_�@�A���̉\���͖��炩�ɑ��債�Ă���B
�@���̂悤�ȏ���l����ƁA��w��n��ɊJ���A�Ƃ�������܂ł̓`���I�ȁu��w�g���v�u���J�u���v�̕����͂��ܑ傫���C���𔗂��Ă���̂ł͂Ȃ����B�n��Ƒ�w�̏o��̍\�}�́A�V��������I�ȕ�����͍����Ă����K�v������B
�@�������̉ۑ���v�����܂ܗ��Ă݂悤�B
��A��w���u�d�I�����b�I�ɒn��Ɂu���J�v����̂ł͂Ȃ��A�ނ���n������A�n��̊���
�@�ɏo��p���������ƁB
��A����͂Ƃ���Ȃ������A��w����n��ւ̈�����I�ȗ���ł͂Ȃ��A�n�悩���w�ւ̗����A
�@�n��ւ̑�w�̎Q����A�n��Ƒ�w�̋����ȂǁA�o�������̉�H�𑽌��I�ɂ����Ă������Ƃ�
�@���낤�B
�O�A�u�n��Ƒ�w�̋����v�ւ̎s���̍s���I�ȎQ���ƁA�����Ɂi�����݂̂łȂ��j�w���̐ϋɓI��
�@�Q�������҂����B
�l�A��̓I�ɑ�w���̃[�~���ɂ��n�抈���ւ̎Q����t�B�[���h���[�N�A����ւ̎s���̎Q���E
�@���́A�s���ɂ��Q�X�g�u�t���x�A�n��̊e��{�݁E�@�ւ́i���w�A���K���j���̓l�b�g���[�N���A
�@�����̌p���I�ȓW�J�̂��߂̏��������A�ȂǁB
�܁A�����E�s���̎��H�I���g�݂Ƃ��̎����I���x���̉ۑ�B
�@�M�҂��Ζ�����a����w�ł́A���̂悤�ȉۑ���ӎ����A�u�n��Ƒ�w�̏o��v���e�[�}�Ƃ���A���E���J�V���|�W�E�������{���Ă����B����N�Ƃ͂Ȃ����Ǝv�����A���������̋�̓I�ȓW�J�͗e�Ղł͂Ȃ��B���͉����B�������E�E�E�B
![]()
18�C�a����w�A�킪�g�t�h
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a����w�l�ԊW�w���I�v��U���i2002�N�j
�@�a����w�̐����͂킸���V�N�A�Z���Ό��������A����Ȏ����ł���B�����A����ƓX�d�������A�Ƃ����C�����ƁA����A�����I���̂��A�Ƃ����C���������G�Ɍ������Ă���B�U��Ԃ��āA����܂łɒʊw���A�܂��ʋ����������̑�w�Ƃ́A���Ȃ������ʔ����L�����p�X�������o�������Ă����������B�����Ȃ�ɏ[�������V�N�������ƌ�����B�܂��͘a����w�ɐS���犴�ӂ������B
�@�����a����w�ɒ��C�����̂�1995�N�A���̔N�͑�w�n��30�N�ځA�����ĐV�����l�ԊW�w�����a�������L�O�̔N�B�A���̌��J�V���|�ȂNjL�O�̍s�����������J����A�Ȃɂ��₢�����͋C�������B�����ȑ�w�̊��C���������B�����̌������͂f���R�K�A�Ă̍����ɋ��������A�w�����悭�o���肵�A���������Ƃ̎��R�C�܂܂Ȋ���������A�������݂ɂ����e�̐��_�̂悤�Ȃ��̂������āA���ɂ͐S�n�悢��Ԃł������B�������v���[�~���͂��߂Ƃ��鑽�l�Ȋw���Ƃ̌𗬂��y����ł����B���̂V�N�ԁA�����̊w�������Ƃ̏o��͂��������̂Ȃ����̂ƂȂ����B
�@�������A���낢��Ɠ��f�������Ƃ�����B���Ƃ��A��������̔��ʂȂ̂���c�̎��Ԃ��������ƁA�w���ɂ��Č����A���̎���E���R�d�H���邠�܂藐�G�Ȏ�u�E���C�̏�ԉ��A�܂��u�w�K�ƌ����̋����́v�u�����Ȏ�����w�v�u�J���ꂽ��w�v�Ȃǂ̗��O�ƌ����̂���A���̋����Ǝ����̖��ȂǁA�l���������Ă����V�N�ł��������B�P�N�ɐ���͑�w���t�𑁂����߂����Ǝv�����Ƃ��������B����������ȏ�ɁA�Ⴂ�l�����ƂƂ��Ɋw�т�����т���������x�������͂邩�ɑ��������B�V�N�Ԃ��قڌ��N�ɉ߂������Ƃ��o�����̂��K���ł������B
�@�K���Ƃ����A���̂V�N�ԁA����̌����������f�����邱�ƂȂ��A�������̔��W�����������Ƃł���B��͉���֒ʂ������邱�Ƃ��o�����B��ɂ́A����ɓ��A�W�A�ւ̌������p���g���邱�Ƃ��ł����B�O�ɂ́A���̌����g�D�Ƃ��āu�����E����E���A�W�A�Љ�猤����v�iTOAFAEC�A�ʏ́E�����Љ�猤����A1995�N�j���������A�����N��w���A�W�A�Љ�猤���x�����s����A�O���ɏ����2001�N���݁A��U�W�܂Ŋ��s�ł����B�l�ɂ́A�����̋��������̐����n�����͂��߁A��C�ɋ�̓I�Ȍ������_���a�������i��C�}�k��Ћ��w�u���э��ی𗬉{�����v�A�ʏ́E�������l�}�����j�B�����Č܂ɂ́A�����ƘA�����ăp�\�R�������ʐM�u��̕��v�i���݁A800���]�j�A�u�����ق̕��v�i���݁A250���]�j�������ɐ��������Ă����B����܂ł�45�N�]�̌��������̂Ȃ��ł��A���̂V�N�Ԃ́A��ڂ��́g�킪�t�h�������̂�������Ȃ��B
�@�������̖{���㈲���邱�Ƃ��o�������A�ق��Ȃ���_���������@��𐔑����^����ꂽ�B�����ɋL�^�Ƃ��Ă��̎�Ȃ��̂̈ꗗ���f�������Ē������B���ӂ����߂āB���i�ꗗ�E���j�S���X�g����
�@�\���킯�Ȃ����Ƃł��邪�A���͍Z���Ɋւ��ψ���⏔��c�ɂ��Ă͂����Εׂł͂Ȃ������B������C�ւ̌������s�ȂǂƓ������_�u�����肷��ƁA�悭��c���x�B
���i�̉�c�ł����܂蔭�����Ȃ������B�O�C�̑�w�ł͌��E�̊Ǘ��E�ɉ��x���I�o���ꂽ�o�߂�����A�Z���ɒǂ��āA�Ƃ��ɒn���̋ꂵ�݂𖡂�������Ƃ�����B���̔����Ȃ̂��A�V�C�̘a����w�ł́g�����̎��R�h���Ȃ�Ƃ��m�ۂ������Ƃ����ӎ�����s�������炢������B��c�ɂ��Ă͑Ӗ��̔���Ƃ�Ȃ��B����ȉ䂪�Ԃ����e�ɋ����Ă����������w�ȋy�ы�����̊e�ʂɐ[�����ӂ��Ă���B
�@���������Ȃ��ŁA��w�J�����b�l��Ɗw�Ȏ�ÁE���J�u���̎d���ɂ��ẮA�����̐ӔC��^�����āA���Ȃ�̃G�l���M�[���X�������i�Ɩ{�l�͎v���Ă���j�B�O�҂́A�Ƃ��Ɂu�ړ���w�v�ɂ��āA��҂́u�n��ɂ�����l�Ԕ��B�v�Ɋւ���A�����J�V���|�W�E���i1999�N�`2000�N�j�J�Âɂ��Ăł���B
�@����������ʂ��āu�J���ꂽ��w�v�u�n��Ƒ�w�̏o��v���e�[�}�Ƃ���d���ł���B���̗̈�́A�Љ���U�̃X�^�b�t�Ƃ��ē��R�S���ׂ������ł������B
�@���Ȃ�ɂ́A��w���J�����Ƃɂ��Ă̂����̎����E��������݂Ă����v���������Ă���B���Ƃ��ΐl�Ԕ��B�w�Ȃ̘A���V���|�W�E���ɂ��ẮA�w���I�v�T���Ɂu�܂̎��_�v�������Ă���B�[���ɘ_�c���[�܂����킯�ł͂Ȃ����A�S���҂Ƃ��Ắu�Ђ����Ɂg�܂̒���h�Ƃ��čl���Ă����v�i���Q�y�[�W�j���Ƃł������B�Ƃ��ɑ�w���J���Ƃ����ꍇ�̑o�������̊W�Â���A��w����n��ւƂ��������������łȂ��A�n�悩��̑�w�ւ̗���A�n��Ƒ�w�̑��݂̎Q���E�𗬂̉\���A��Nj����Ă��������ƍl���Ă����B
�@���̉ߒ��ŁA���猤���̃t�B�[���h�Â���A�������K�|�C���g�Â���A�s���ɂ��Q�X�g�u�t�l�b�g���[�N�A��w�ɂƂ��ẴR�~���j�e�C�E�X�^�b�t�̍\�z�A����ȉۑ���Ђ����ɖ͍����Ă�������ł���B��������̉��̒i�K�ɂ͓��B���Ȃ������B���J�V���|�W�E���̋L�^��ǂݕԂ��ƁA���܂��܂ȉ\���������Ă���B�������̎��_�ŁA�a����w�ł̎��̎d���͏I�����邱�ƂƂȂ����B
�@�Ō�ɁA�����̋����E�E���̊F�l�ɂ��炽�߂Č���\�������܂��B�Ƃ��ɉ䂪�ԂőӖ��Ȏ�������������ĉ����������Ƃ�Y��܂���B�����ɁA���l�E���ʂȘa���̊w���E���Ɛ��Ɋ��ӂ��܂��B�����E�w�����闧��ɂ���Ȃ���A�悭�l���Ă݂�ƁA�t�ɋ������A�h���������A��܂��ꂽ���Ƃ����Ȃ�����܂���ł����B�������̂V�N�Ԃ́A�Љ�番��Ŏd���������Ƃ�����������Əd�Ȃ�A�c�O�łȂ�܂���B��w�Ŋw���Ƃ��������ĎЉ�I�Ɋ��Ă����ꂪ�e�Ղɓ����Ȃ������́A�����Ƃ��Ď₵�����Ƃł��B�������ɏ�肱���Ă����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B
![]()
19�C�Ō�̃v���[�~�u�n�������A�n��ׂ�v
�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a����w�l�Ԕ��B�w�ȁi�c�j���уv���[�~�W�A�Q�O�O�Q�N�P���j
�@
�@�v���[�~�Ƃ����̘a����w�Ǝ��̃��j�[�N�ȂP�N�[�~�ł��B�P�X�X�T�N�t�A�O�C�̑�w����a���ɕ��C���āA�͂��߂Ă��̔N�̐V�����̃v���[�~��S�����܂����B�U�N�O�ł��B
�@����܂ł̑�w�J���L�������̏펯�ł́A�T�_���b�_���P�C�Q�N�ŏI���āA�������b�ɂR�C�S�N�[�~�ɎQ�����Ă����A���邢�͑�w�@�̐��I�ȃ[�~�ɂ����ށA�Ƃ����l���������ʂł����B���ł����̑�w�ł͂����ł��傤�B
�@�������A�a���ł̓[�~�Ƃ����A�܂��P�N�̃v���[�~�B������A�X�T�N�����́u�[�~�v�̃C���[�W���܂������ς���āA���������ē��f���܂����B���I�ȕ�����ǂ݂����A�������b�ɂ��ăe�[�}�����ڂ�����������������A�Ƃ����[�~�̂��������������Ȃ��A�݂ȂP�N���ł�����B�����g�̃[�~�E�C���[�W��]��������K�v������A���āA�ǂ��i�߂Ă������A�v���߂��炵��������v���o���܂��B
�@�Q�������[�~�E�����o�[�͂�����߂āA�S�������̑������߂āA�Ƃ����o�����n�܂��āA�Ȃ�Ƃ��������͋C�Ńv���[�~���X�^�[�g�ł����Ƃ��͂ق��Ƃ������̂ł��B�w���Ƌ����́A�܂��w���̒��ԑ��݂́A���S�̂Ԃ������Ɖ����̂Ȃ��g�Θb�h�������Â������Ă����܂����B�w���ɂ�鎩��I�ȃ[�~�^�c���������ɋO���ɏ��܂����B�a���̊w�������͈ĊO�Ƃ����������Ƃ��D���ȂȂ��Ɗ��S�������邱�Ƃ�����܂����B�w���̊F����ɂƂ��Ă��i���炭�j�����������Ǝv���܂����A�����ɂƂ��ẮA����܂łɂȂ��Y�ꂪ�����u�[�~�v�̂P�N�B���߂ĒS�������X�T�c�v���[�~�E�����o�[�̏��X������́A���ł���������ƋL���ɂ����₩�ł��B
�@�a���ɗ��č��N�łV�N�ځA�v���[�~�͂S��ڂł��B���āA���N�̂O�P�c�v���[�~�́A���݂��U��Ԃ��Ă݂āA�ǂ�ȕ]���Ȃ̂ł��傤�B
�@�v���[�~�ւ̌Ăт����̃e�[�}�́A�g�n��h���L�C���[�h�ɂ��Ă��܂����B���N�x�́u�n��Ɛ��U�w�K�v�ł����B���N�́u�n�������A�n��ׂ�v���e�[�}�Ɍf���܂����B�����āA���ƈ�g����h���e�[�}�ɂ��܂����B
�@�ŏ��̃v���[�~�̂P�X�X�T�N�́A�ĕ��ɂ�鏭���\�s�������N�������N�ł��B����܂Ŗ��S��������҂������A�ۉ��Ȃ�����ɖڂ���������Ȃ�������܂����B�v���[�~�L�u�\���l�ʼn��ꍇ�h�������X�����{�́A�������N��������A�ٔ��������͋C�̂Ȃ��ł̗��ł����B����A���N�����ăe����������̉���s���A����͂��ł����������ْ��̂Ȃ��ɂ���̂����m��܂���B
�@�g�n��h���e�[�}�ɂ��Ă����̂́A�������̊S������̒n��Ƌ���E���U�w�K�ɂ��邱�Ƃɉ����āA���Z�������I���đ�w�ɓ����Ă����w�������́u�n��v�o���������قǏ��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�ƁA�n�抈���E�s���g�D�ւ̎Q���o�����n��Ƃ��������łȂ��A���Ƃ��Ղ���m��Ȃ���ΔN���s���֏o��@����Ȃ��A�}�`�̃I�W�T�������Ƃ̕t���������Ȃ���Ύ��̈��݂������m��Ȃ��A�܂������̖v�n��l�Ԃ��Ƃ����Ƃ���ɂ���܂��B����͎푈�̂Ȃ��ʼn߂����Ă����w�����ɐӔC������̂łȂ��A�ނ��댻����{�́u�n��v���ꎩ�̂����Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃł��傤�B�����炱���A�Ȃ�Ƃ��v���[�~�̎��g�݂ŁA�u�n����Ĕ����v�������Ƃ����v��������܂����B
�@�����ɂ܂��A���B�w�ȃv���[�~�̃e�[�}�̂Ȃ��ɁA����������ڂ��O�ɓ]���āu�n��v���l���鎋�_����͂����Ă������낤�A�Ƃ������Ƃ�����܂��B
�@�n��̃e�[�}�́A����̃e�[�}�ƌ��т��āA���ӎ���ʔ������N����Ƃ��낪����悤�ł��B�������[�~�E�����o�[���S���ʼn���ɍs���킯�ł͂���܂���B�n��́A����Ώ����ȉF���ł�����A�����Ȗ������Ă��܂��B�q�ǂ��E����E�����A���邢�͕����E���E�S�~�Ȃǂ��߂����Ă��܂��܂̖�肪�����Ă��܂��B�����̂ւ̑f�p�Ȗ��S���o���ɂ��āA���N�������ł������悤�ɁA����܂ł̃v���[�~�ł��A�R�`�S�̃O���[�v���g�D����Ă��܂����B�܂��n��͉��ꂾ���łȂ��A��肾���Ē��c�����āA�Ȃ��Ȃ��ʔ����n��Ȃ̂ł��B�������A����̃e�[�}���ЂƂ���邱�Ƃɂ���āA��肪���̓I�ɂȂ�A������l���Ă������_������I�ɂȂ�悤�Ɏv���܂��B�v���[�~�Ƃ��Ă͂����e�[�}�ɏo����Ă����ƌ�����ł��傤�B
�@���N�̃v���[�~�o���̖`���ɁA�w���̊F����ɂ������̊��҂�\�����܂����B
�P�C�[�~�̉^�c�͊w������̂ƂȂ�B�^�c�ɕK�v�Ȗ������݂�Ȃŕ��S���Ă����B�[�~���@���o�[��
�@��l�K����̖�����S���B���悵�āA��������Ăق����B
�Q�C�[�~���Ԃ̉��̃l�b�g���[�N��n���Ă��������B���Ȃ����l�ɐ������������Ă����B
�R�C�ɂ��₩�Ɋy�����i�߂Ă������B�R���p�⍇�h����悵���������悤�B
�S�C�~�j�E�R�~�̔��s�B����A�K���O��̋L�^�ⓖ���̉ۑ���A�܂��[�~�E�e�O���[�v�́@�������f��
�@���Ăق����B
�T�C�Ō�ɏ[���������W������B�ҏW�ψ���ɂ���Ėʔ����ҏW���A�ŏI�I�ɂ͈�����A�e��
�@�̃��|�[�g���݂�Ȃŋ��L�������B
�@���̂T�_�́A����܂ł̃v���[�~�ł��厖�ɂ��Ă����|�C���g�ł����A���N�͂ǂ��������̂ł��傤�B���܁A���̕W���o���オ��܂����B���ꂼ��S�����������o�[�̓w�͂ɂ���āA�R���p�����h���A�~�j�R�~�����ꗷ�s���A�����čŏI���W�������ł����킯�ł��B�~�j�R�~�͊Ԓf�͂��������A�Ƃ��ɗ͍�����������A���{���h�́A�����ҁE���тɓˑR���]�͂��đ����A�������ɂ�������炸�A�[���������e�ł����B�܂��܂��̃v���[�~�ƌ�����ł��傤�B
�@�������A�w���̊F���g���悭�m���Ă���悤�ɁA���x���[�������������Ԃ����������Ƃ������ł��ˁB���܂������Ȃ��ȁA�ƐS�z�����ꎞ��������܂����B�����͂肠���ċ���������ׂ�A�݂�Ȃ����������Ƃ�����܂����ˁB
�@�����A�Ȃ�Ƃ����悤�A�ƊF����œw�͂������Ƃ��m���Ă��܂��B���̌��Ē����̈ꎞ���ɁA�^�P�V�̎�b���݂�ȂŏK�������̎��Ԃ����̐Ȃ��猩�Ă��āA����͂������A�Ɗ������Ȃ�܂����B�v���[�~�́A�܂��Ɋw���̎�̓I�ȓw�͂ł�݂��������A�Ǝv���܂����B11������12���ɂ����āA�e�O���[�v����A�܂�����O���[�v����̕��������ŁA�����I�����}���Ă���ȁA�Ƃ�������������܂����B���N�̃v���[�~�́A��͂�A�܂��܂��̏o���オ��A�ƌ������Ƃ��o���܂��傤
�@�������͂��ߕW�ҏW�ψ���̑��S���̊F����A����J���܂ł����B���ɂƂ��Ă͍Ō�̃v���[�~�A�Q�����Ă��������A�L���B���܂ł��Y��Ȃ��ł��傤�B�i�Q�O�O�Q�N�P���j
![]()
20�C�Q�l�F�a����w�E�v���[�~�ق��t�C�[���h���[�N�L�^�i�ʐ^�@1995�`2002�j����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W