記述を書き直すことの意義
反復… | 物事を深く、細かく見るために重要なこと |
| 書き直さなければ、洞察ができない。 |
|
振り返ることの段階
↓反省…立ち止まり、振り返る
↓内省…内なるものを、振り返る
↓省察…内なるもので、隠されているものを汲み取る
↓洞察…内なるものの背後にある最も重要な点を見抜く
|
通常、反省をするときには、視点がある。目的がある。欲求がある。
例:困った子がいる。どうすればよいのか。
誰がそれを困ったと思っているのか。誰が困っているのかというのも問題。
外のものを見るのに比べ、自分の内なるものを見ることには抵抗がある。
自分の内面は、自分にとってあまりにも親しいものであるため、距離をとることが難しい。
自分にとっては分かりきっていると思っているものでも、隠されたものがある。
自分を見つめるためには立ち止まらなければならない。
セルフ・カウンセリングでは、自分の内面の受止めなおしをして洞察をする。
|
記述と叙述
● | 記述
評価を下さずに、現象を忠実に記述する。(現象学)
意識の流れを具体的に書くこと。
|
● | 叙述
物事を順を追って述べること。「歴史叙述」、「物語叙述」というような言葉の使い方をする。
叙述には一定の視点が働く。そのため、省略や強調が入る。
|
● | 論述
叙述をある一定の理論に基づいて書くこと。
|
|
心のセリフ
心のセリフ=思ったこと=内言
…洞察する際に重要な視点となる
|
心とは何か
気(潜在的な意識)気が持続性をもつと、気持ちになる。
気持ち(潜在的な意識が持続的になる)気持ちが持続性をもつと、心になる。
心(感情)心が一定の方向へ向くと、志となる。
志(意志・意欲)
|
意識とは
自分の心は自分が分かっている。その理解可能性をもっている。
ヨーロッパの学問では、内面を意識と捉えている。
意識の志向(指向)性
意識…私たちは“何か”を意識する。何かについての意識である。
例:私は彼女を意識する。私→彼女
空間的に見れば、意識には選択性(評価性)があり、
時間的に見れば、意識には変化性がある
「私は、世界中の中から、あなた(それ)を選び取っている。」
→もうその時点で選択性(評価性)がある。そして、その選択性は私たちの関心事に従って
刻々と変化する。よって、私たちが意識していることは、きわめて主観的である。
|
意識=対象関係…意識とは、何かについての関係である。
感情=対象感情…感情とは、何かについての感情である。
欲求=対象欲求…欲求とは、何かについての欲求である。
|
|
|
感性(感じ方の傾向性) |
―文化的次元― |
意欲 |
|
|
感情(人に対して抱くもの) |
―社会的次元― |
欲望 |
欲求 |
欲求(身体的なもの) |
―自然的次元― |
衝動(本能) |
|
|
人間は理性で動いているのではない。感情で動いている。
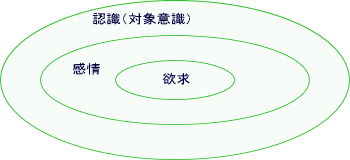
欲求が満たされれば、肯定感情
満たされなければ、否定感情をもつ。
|
|
条件超越的反省について
道徳的反省…自分のもつ規範に基づく反省
規範に合致していれば、善
規範に合致していなければ、悪 |
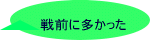
|
|
技術的反省…自分のもつ目的に基づく反省
目的を達成できれば、善―上手、巧い、成功
目的を達成できなければ、悪―下手、拙い、失敗 |
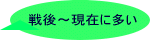
|
|
条件超越的反省…規範や目的を超えて、事実を事実として認識できるかという反省。
欲求から離れて、事実を事実として認識できるかという反省
特定の評価を超えて事実を理解することを目指す反省である。
自分も他者も受容が可能になる反省。
→それが授業改善に役立つのか?
→直接役立たなくていい。
結果として役立つ。
他者との関係にのみ、自己は認識される。(2歳すぎくらいからもてる能力)
この意識にも評価が加わるので、ここでは自己価値意識と呼ぶ。
他者との関係からモノサシをを取り入れ、そこから外れないように、自己を否定せざるを得なくて済むように、
自分を肯定できるように努力して、自己を形成する。
自分を無自覚的に肯定していれば、そのモノサシから外れたことを否定する。
コメントについて
…注釈でもない。発問でもない
[受けとめる]→[問いかける]→[教える(述べ伝える)]
“引き出す”ということが必要。子どもがすでに意識していることを言語化する。
しかし、不安が強い人ほど、受けとめることが大事。
現代の子どもは、不安で、落ちついていないため、受け止めが大事
それは、一人一人に対するレスポンス([応答])である。
そのためには一人一人の子どもを受け止められる準備が必要である。
その出発点として、自己理解が必要。自己理解の深さの分だけ、他者理解ができる。
→事実を事実として受け止められる力。認識受容力。
すでにこどもが意識していることを、言語化し、引き出すという感覚。
|

