*社会教育・公民館研究ページ(小林)→■
<目 次>
1,社会教育施設の新しいイメージ (月刊社会教育1995年4月号)
2,これからの公民館の展望をどうえがくか
-(1)第五世代の公民館論、可能性の追求(月刊社会教育1996年12月号)
-(2)第5世代の公民館論・改訂版(1996年論文に加筆) 2005年
*月刊社会教育編集部編『公民館60年・人と地域を結ぶ社会教育』( 国土社刊)所収
3,公民館施設論の系譜をさぐる (月刊社会教育2002年 4月号)
4,「これからの公民館-新しい時代への挑戦」(国土社、1999年)総論→■
5,公民館・施設空間論をめぐって(南の風1640~1741号、2006年)→■
6、『現代公民館の創造―公民館50年の歩みと展望』日本社会教育学会特別年報
序章 公民館研究の潮流と課題 (東洋館 1999年)
7、公民館の地域史研究と国際的視野からみる特質と課題(2001年)
*小林・佐藤一子編『世界の社会教育施設と公民館』(エイデル)第Ⅱ部・序章・終章
8、拾遺「三多摩テーゼ」記 →■ (南の風3413~3435号)、2014~15年
▼東京都「新しい公民館像をめざして」 (三多摩テーゼ、1973~74年、060428santama)

1,【月刊社会教育】1995年4月号・所収
社会教育施設の新しいイメージ
ー生涯学習時代におけるー
「施設」概念は発展する
施設という言葉は本来あまり魅力的なものではない。官から民に「施し設ける」という意味をもっていた。物的営造物というより、上から下に与える精神的教化をむしろ主要な内容としていた時期がある。少なくとも戦前においてはそうであった。これが新しい概念に脱皮するのは、戦後の教育改革期、社会教育では公民館構想の提起や教育基本法(第七条)の立法過程においてである(一九四六~四七年)。
教育基本法から社会教育法の成立(一九四九年)にいたる経過のなかで、社会教育施設の概念は大きく転換し、少なくとも法制的には次のような意味内容が確定していったといえよう。すなわち、?施設の公共的な性格、?行政の「条件整備」任務の主要な柱、?物的営造物(館)としての概念、である。さらに施設の機能を充全に営むためには、?必要な職員の配置とその専門性、?住民参加による審議機関の設置、が必要とされた。初期の公民館構想(いわゆる寺中構想)から社会教育法(第五章)に成文化された公民館にかんする諸条項の流れを見ていけば明らかである。
しかしながら、社会教育法制の施設規定はいくつもの不充分な点を残している。法制の理念は豊かであるとしても、実質は貧しい、のである。たとえば公民館をはじめとする社会教育施設はー図書館法や博物館法にもある程度共通する問題点であるがー、自治体が公共的に設置する原則は明らかであるとしても、その義務設置の規定はなく、また設置基準の水準は低く、とくに専門的職員の配置について法制は充分の条項を用意していない。
歴史的には、むしろその後の地域における社会教育施設の実際の展開のなかで、施設の「実質」は形づくられてきた。たとえば自治体の施策や計画において、施設職員の実践的な取組みのなかで、あるいは施設づくりの住民運動のなかで、施設や職員の在り方が模索され、その基準や内容が実践的に追求されてきた。この実質化への努力によって、施設は「施し設け」られるものでなく、いわば「創り出さ」れてきたのである。戦後社会教育の研究・実践・運動のなかで「施設」概念の実質は、まさに変化し発展してきたのだ。そして生涯学習時代といわれる今日またそうでなければなるまい。
施設・理論の地域的創造と運動
戦後教育改革からすでに五〇年ちかく、この間に紆余曲折とさまざまの地域格差を内包しつつ、各地の自治体で多くの社会教育施設が設置されてきた。すくなくとも公民館について言えば、その設置数(紙数の関係で省略、詳細は社会教育推進全国協議会編『社会教育・生涯学習ハンドブック』一九九五年版、エイデル研究所、など参照のこと)は、とっくに義務教育の中学校の総数を超え、小学校一〇校あたり公民館七・三館の規模までに達している(文部省統計)。国の公民館設置の国庫補助はこれまで決して多額ではなかった。したがって公民館の全国的普及については、主に地方自治体の施策によって、それも市町村の行財政努力に負うところが大であった。
しかし問題は、その量的拡大の内実、そしてその質的な充実がどうか、ということであろう。たとえば公民館は大都市部において空白地帯が多く、図書館は逆に町村部に空白が多い。また博物館は最近ある種のブームに近い設置の動きがあるが、地域・住民の生活に根ざした公共性豊かな施設づくりの方向とは言えない実態がある。一九八〇年代以降の行政改革政策の影響をうけて、総じてこれら施設の職員体制は、とくに専門職制においてむしろ弱体化している地域も少なくない。施設が増加しても職員は増えない。単なる量的拡大を喜べない状況がある。
しかし今日に至るこのような社会教育施設の量的な普及は、法制の理念を基礎としつつ、「施設」が地域・自治体のなかに定着し、その必要性が認識され、支持されてきたことを示している。とくに一九七〇年代に各地で躍動した公民館づくり・図書館づくり(あるいは最近の博物館づくり)住民運動の取り組みはそのことを実証している。それぞれの自治体における施設づくりの経過やその後の展開は、地域的にきわめて多様であり、地域格差を含む反面、個性的かつ自治的な側面をもっている。日本の社会教育施設は、したがって(国家的に画一的なものでなく)本質的に地域的な施設であり、自治的な性格のものであると言うことができよう。
もともと社会教育法は「市町村主義」「自治」「参加」の理念をうたっている。しかしこれらの理念はそのまま地域の社会教育・施設の実態として現実化したのではない。法の理念に基づいて自覚的に実践し運動的に取り組む自治的な努力がなければ実態化しない。そして地域的・自治的な施設像の形成、その具体化についても、施設についての理論化の努力が必要であり、それを実現していこうとする実践と運動の蓄積が不可欠であった。それらの一つの到達点として、社会教育施設の在り方の追求、いわゆる「テーゼ」づくり(施設原則の共有化)の努力があり、運動があった。
たとえば、?公民館にかんしては、長野県飯田・下伊那主事会「公民館主事の性格と役割」(下伊那テーゼ、一九六五年)、東京都社会教育部「新しい公民館像をめざして」(三多摩テーゼ、一九七三年)など、?図書館にかんしては、日本図書館協会「中小都市における公共図書館の運営」(中小レポート、一九六三年)、同協会「市民の図書館」(一九七〇年)など、?博物館にかんしては、伊藤寿朗・博物館問題研究会「中小・地域博物館構想」(第三世代の博物館、一九七三年、一九八六年)など、があげられよう。
これらは、それぞれの施設の実践・運動の蓄積を確かめ、そこに理論的な光をあてながら問題を整理し、施設と職員の新しい在り方への課題提起を試みるという点で共通する。そしてこの理論・実践の共有化の試みが、さらに新しい施設づくりの実践と運動を発展させ、それがまたテーゼの実質を創り出していくという循環を生み出してきた。(資料の詳細については、横山宏・小林文人編『公民館史資料集成』エイデル研究所、一九八六年、前掲『社会教育・生涯学習ハンドブック』など参照のこと。)
1980年代の転換、そして90年代はー
振り返ってみると、テーゼづくりや施設づくりの住民運動が活発に展開された時期からすでに二〇年前後が経過したことになる。しかしその後、社会教育施設をめぐる状況は一九八〇年代以降大きく転換した。上述してきたような七〇年代を躍動期とすれば、八〇年代はむしろ低迷・停滞期と言わざるを得ない実態がすすんできた。それはどのようなことか。 一つには、七〇年代の後半から進行する「地方財政危機」「都市経営」論を背景とする地域社会教育施設(とくに公民館)の「合理化」「職員削減・嘱託化」の動向である。かって公民館の地域配置が全国的に注目され評価されてきた北九州市(旧八幡市)、福岡市、西宮市、鶴岡市などに典型的にあらわれた(社会教育推進全国協議会編『公民館合理化の動向ーこの憂うべき状況をどう克服するか』一九七七年、に詳しい)。しかしこの段階では、社会教育施設の公共的設置ないし行政の公的条件整備任務、つまり社会教育法制が求める原則は当然のこととして認識されていた。
二つには一九八〇年代に入って国家政策として積極的に推進される「行政改革」の“嵐”である。第二次臨時行政調査会の提言(最終答申、一九八三年)や「地方行革大綱」(一九八五年)に典型的に示されるように、社会教育施設の民営化あるいは民間委託、職員の嘱託化・ボランティア化、受益者負担の導入などが激しく唱導された。ここでは戦後教育改革期以来の社会教育行政の基本任務、公的セクターによる施設設置・職員の配置、それ自体が問題とされるようになる。そして、東京二三区をはじめ主として大都市部から、社会教育施設「委託」の動向が顕著になるのである。
三つには、八〇年代後半の臨時教育審議会「教育改革」答申(一九八四~八七年)による「生涯学習」政策の展開がある。「生涯学習体制」への移行を目玉としたこの教育改革の考え方は、その根っこにおいて深く「行政改革」と連動するものであった。すなわち従来の公共的な社会教育の体制を見直して、民間的(企業的)な生涯学習市場の形成をはかり、広域の生涯学習情報センター(コンピューター・ネットワーク)を重点的に打ち出すことにより、地域の公的社会教育施設の比重を後退させるものであった。一九九〇年「生涯学習振興整備法」の施行はその具体的な法制化といえる。しかし「民間事業者の能力を活用」(同法第五条)することをうたったこの法律も、バブル経済崩壊により、その「基準」(同法第六条)さえもまだ策定に至らない。
そして四つには、八〇年代の全般的な住民運動の停滞がある。七〇年代の社会教育施設づくりや事業・運営への住民参加の諸運動は、地域のなかのさまざまな住民運動のエネルギーと結びあっていた。もちろん八〇年代そして九〇年代の新しい地域の運動がネットワーク的に胎動してきていることは確かであるが、広汎な運動的な拡がりが地域のなかで低調になってきたことがあり、それが公的社会教育にかかわる住民運動にも複雑に波及している。そしてあと一つ、社会教育職員の自治体内の、また自治体をこえる集団的な連帯の取り組みや労働運動もまた、転換期のなかで必ずしも迫力を発揮し得ていない。
いわゆる生涯学習時代において、あらためて「学習権」思想を起点として、かっての社会教育にかかわる住民運動が提起してきたエネルギーを新しい視点から再生していくことが問われている。
生涯学習時代ーいま面白いときだ
上述してきたような生涯学習政策の問題性からすれば、単純な「生涯学習」の賛美にならないことは当然である。しかもこの間、日本型生涯学習ともいうべき行政主導・上意下達の政策浸透、精神主義的な“心がまえ”としての生涯学習論、社会教育行政の安易な組み替え、そして公的条件整備の軽視、が横行してきた。
しかし、このことがまた単純な生涯学習の否定論になってはならないと思う。いま、人間本来の豊かな生存に不可欠な生涯にわたる学習と文化の創造を、「学習権」の理念に立脚して実現していく大事なチャンスでもあろう。また、日本の社会教育が体質的にもつ“固さ”“狭さ”などの弱点を克服する重要な契機ではないか。ユネスコをはじめとする国際的な生涯教育の潮流(有給教育休暇制度、リカレント教育、識字教育実践等を含めて)に学ぶベき点も少なくない。まして国レベルだけではなく、全国の自治体がおそらく六割をこえる規模で何らかの生涯学習政策や計画を模索している現実にたって、その本来のあるべき方向を積極的に提起していくことは、理論的にも実践的にも重要な課題といわなければならない。
その意味で、いま面白い時代なのだ。他方で週休二日制、学校週五日制がすすめられ、必要な条件整備が伴わない問題点があるとしても、客観的にみて地域の社会教育と施設への期待は大きく高まっている。農村でも都市でも、産業や環境や福祉や保健など、地域のなかにさまざまの新しい社会問題が噴出している。住民のくらしのなかで「持続可能な社会をめざして」などの運動がさまざま取り組まれている。そのような地域の諸課題や運動と密着して、地域・自治体の生涯学習、そしてその土台としての社会教育を活発に展開させていく方向をみつめれば、いま面白いときだ、さあ、社会教育の出番だ、地域の社会教育施設がネットワークを組みながら、広く新しい視野で、面白い活動を組み立てるときだ、と言うべきだろう。
新しい模索ー多元的に開かれた施設へ
冒頭に述べたように「施設」概念は時代とともに発展してきた。そしていま、旧来の社会教育施設から、地域の現代的な課題に敏感に対応しつつ、どのような新しい施設へ脱皮していくか。狭く立てこもる発想から広く開かれた施設へ、一元的な発想から多元的なチャンネルをもって、固く生真面目な施設から楽しく面白い活動へ、変化に着実に挑戦する姿勢を大事にする方向へ、などをキィワードとして模索がはじまる必要があろう。そしてその基本に、地域とくらしに生きる住民の学習権の公的保障、の理念が重要であろう。
主として、公民館およびそれに類似する社会教育施設(たとえば社会教育センター、文化センター、青年館、女性センターなど)をイメージしながら、いくつかの具体的な課題を取り上げてみよう。
(1)事業論の拡がりを。 これまでの伝統的な社会教育事業の枠組みを再検討する必要があるのではないだろうか。狭い意味での「学習」の範囲を解き放つ発想に挑戦してみたい。たとえば地域の環境・リサイクルの問題や、福祉や保健や、地域づくりに取り組む住民運動など、切実な生活問題と地域課題と切りむすぶ視点をもって。「文化」事業の考え方も広く地域文化の創造と市民協同のネットワークに公的施設として参加する姿勢で。
(2)関連する行政・施設の連携を。 公民館をはじめとする地域社会教育施設こそが、他の関連する行政あるいは施設の相互連携の結節点になりうるのではないか。従来ともすると公民館など施設・機関の独自性あるいは専門性論が、公的サービスの豊かな連携論を断ち切ってきた面がある。むしろ公的サービスを社会教育の視点から横につないでいく役割を積極的に果たすことによって、公民館など地域社会教育施設の独自性、専門性が発揮されることになる。その意味で総合的な施設のイーメジをあらためて再発見する必要があろう。
(3)地域の集会施設、あるいは集落の共同施設(いわゆる自治公民館等)とのネットワークを。 一般行政系列の集会施設、コミュニティ施設、集落規模の施設は、社会教育的施設として密接な関連をもっている。これまで、これら施設と社会教育施設がいかに異なるか、という論議が先行して、どのように類似性をもつか、いかに関連・協同の可能性があるかなど、実態に即した検討が不充分ではなかったろうか。
(4)地域的社会的に不利益な人々にとっての優先施設。 民間企業の生涯学習市場形成を意図する政策は、学習・文化の商品化をもたらし、所詮「社会的強者」に利する生涯学習になりかねない。地域の公的社会教育施設こそが、障害者、高齢者、被差別住民、外国籍住民など少数者を含めて、あらゆる人々の学習権保障の立場を優先する必要があろう。
(5)地域の学校・大学を開く活動への参加を。 学校を改革し地域と住民に開放していく努力が始まっている。公教育としての学校は本来的に地域の社会教育施設としての性格をもっているのではないか。阪神大震災のなかで学校施設が果たした役割を想起しても、学校施設の存在は大きく、日常時における地域活動の拠点としてあらためて学校が再発見され、公民館等との連携・協力が真剣に論議されるべきだろう。
(6)職業訓練・職業能力開発機関と社会教育施設の結合を模索したい。労働省系統の職業能力開発機関は、国際的常識では間違いなくすぐれて「成人教育」「継続教育」の施設である。現行制度のもとでは社会教育施設との不幸な断絶が実態であるが、長期の展望をもちつつ、地方自治体レベルでの両施設の結合の方途を模索していく必要があろう。
このような課題に挑戦する施設だからこそ、その仕事を担う社会教育職員の役割は重く、大きい。 (こばやし・ぶんじん 和光大学)
2-(1),【月刊社会教育】1996年12月号・所収
これからの公民館の展望をどうえがくか
ー第五世代の公民館論、問題提起としてー
公民館半世紀の蓄積をみるー三つの論点
五〇年の歴史をきざんできた公民館、現時点にたってこれからの展望をどうえがくか、まさに大きなテーマを与えられたわけであるが、編集部で用意された枚数はわずかである。引き受けたことを後悔しつつ、しかし意を決して、非力ではあるが一つの問題提起として要点のみ書きしるすことにする。まずはじめに、この問題を考えていく上で私なりにいま重要と考える視点を三つほど述べてみたい。紙数の関係で文献出典などは省略させていただく。
第一に、公民館の基本的な性格とその評価について。公民館はこれまで法制上もまた実態としても、地域・自治体の総合的な社会教育施設として設置されてきた。しかし施設・職員の体制はまことに貧弱な水準からの出発であった。歴史的には農村的地域性に依拠し、総合的であるが故に多面的かつ“あいまい”な側面をもたされてきた。しかもそれが地域と民衆の側から創出されるというより、官製的に設置され、いわば上から与えられるかたちでの公民館が多かった。
それだけに公民館への批判は、その農村的保守性、総合的あいまい性、行政主導の体質、などについて噴出してきた。最近では、「社会教育終焉論」や臨時教育審議会・教育改革(生涯学習)論では「公民館の歴史的役割は終わった」と公言する論議(一九八七年)もあった。たしかに厳しい批判には謙虚に耳を傾けるべきであろう。しかしこれらの批判は、公民館の実態・実践の拡がりをトータルに認識していないのではないか、五〇年の矛盾にみちた歩み、そのなかでの創造のプロセス、そして公民館制度のもつ内面的可能性、を発見しようとする姿勢において欠けるところがあると思われる。 公民館にとっていまや農村型・都市型という二分論はあまり生産的とは思われないし、なによりも公民館自体が五〇年の歩みのなかで“換骨奪胎”“脱皮”を繰り返しながら、厳しい状況のなかで“発達”してきている事実にもっと注目すべきであろう。その上で、公民館が本来独自にもつ地域の総合的な社会教育施設・機関としての性格と、その現代的な意味を明らかにしていく必要があるのだ。
第二は、以上とも関連して、公民館の施設機能の多様性と多元性、さまざまの構想を許容する自治性の問題について。多様・多元を否定的にとらえるか、それとも積極的にその意義を最発見するか。地域総合の社会教育施設としては、多様かつ自治の機能をもつことは、あいまい性や地域的格差の側面をともなうが、むしろ本来的にきわめて重要な特性と考えるべきであろう。
近年はむしろ各種の地域施設のなかで公民館の社会教育施設としての専門化が求められる傾向がある。また「急激な社会変化」にともなう高度化、情報化、国際化などの要請に対応して、あるいは「生涯学習」社会の登場にともなって、専門化、高度化をめざす公民館イメージが一面的に追求される動きもある。なかには地域施設としての特性や自治性を放棄して、公民館のインテリジェント施設化や民間委託化、営利事業化が主張されようとしている。
公民館は「地域」社会教育施設である。専門的施設への志向がありうるとしても、なによりもそこでは地域の多様な人々が集まり、地域住民のさまざまの(学習活動に限定されない)活動が自由かつ多様に展開される、そういう可能性を排除してはならないだろう。
公民館は住民の自治の空間である。あえて公民館の初期構想(寺中構想、一九四六年)に遡れば、出発の時点で公民館設置「次官通牒」という形式をとったにもかかわらず、自ら官製的な流れを否定し、その後地域からのさまざまの多様な公民館構想を可能にしてきた。この半世紀、全国各地でなんと多くの公民館構想・活動が胎動してきたことか。公民館の歴史はまさに地域的、自治的、多様なバリエイションをもって綴られてきた。地域自治的な公民館構想の展開については、本誌一九九五年一二月号拙稿「公民館の五〇年」で力説したつもりである。
第三は、公民館とその制度の“発達論”の視点である。戦後史とともに、公民館はよちよち歩きの幼児から、ひとまずは一人前の成人に発達してきたと言えるだろう。もちろん地域史による差異はある。全国一七五〇〇をこえる公民館のなかには、虚弱児もいればまだ思春期の悩み多き公民館もある。しかし病没した公民館はきわめて少ない。地域的事情に左右されながらも、総体として公民館は案外とたくましく発達してきた。厳しい状況のもと、停滞や挫折もある。しかしそれぞれの発達段階において、新しい骨格や血脈を自己形成しながら、今日の公民館の理論や条件が形づくられてきた。
公民館の自己発達史ー主要なキーワード
人が内面的な可能性をもって発達するように、歴史的にみれば公民館もまた明らかに世代的に発達してきた。この発達論は、かって横山宏氏との共編『公民館史資料集成』(エイデル、一九八六年)を編んだときから、いつも実感してきたことである。最近の公民館をめぐる厳しい現実(第三セクター委託化、職員削減、受益者負担など)を強調するあまり、公民館の停滞・後退が悲観的に指摘されるとき、私はいつもその内面的な発達可能性、その“再発見”を主張してきた。 かりに世代論的に公民館の自己発達史をたどってみると、どうなるか。その誕生から今日まで、紆余曲折を経ながら、いわば第四世代から第五世代の段階を展望するところまで到達したと言えるのではないだろうか。その発達の歩みのなかで、模索を繰り返しながら、骨となり肉となる細胞やエネルギーを生みだし、体内に自己変革的に取りこみながら、公民館の歴史が創りだされてきた。仮設的にその発達史と大凡の時期、主な特徴(キーワード)をあげてみることにしよう。
(1)第一世代「初期公民館」時代(前史を含みほぼ一九四六年から四九年社会教育法成立まで、主なキーワード・住民自治、地域づくり、自治・集落公民館、など)
(2)第二世代「公民館近代化」の時期(社会教育法制定から一九七〇年代初頭、主なキーワード・公立公民館、教育委員会制度、施設条件整備、公民館主事集団、など)
(3)第三世代「住民参加型公民館」の動き(一九七〇年代から八〇年代半ば、主なキーワード・学習権保障、学級講座自主編成、公民館づくり住民運動、など)
(4)第四世代「生涯学習・行政改革下公民館」の時期(八〇年代から九〇年代へ、主なキーワード・委託合理化、受益者負担、ボランティア・ネットワーク、など)
わずかの紙数では細かな説明を加える余裕がないが、戦後五〇年、公民館が時代と状況に格闘しながら、人間の生きる歩みにも似て、世代的な発達の道程をたどってきた歩みをよみとってみたい。とくに第三世代が住民参加・運動に支えられて活気あふれる躍進がみられたのにたいし、第四世代の公民館は一方で生涯学習の要請があり他方で行政改革の厳しい状況のもと停滞を強いられた時期であった。もちろんこの時期区分も、提示した主要な特徴も、あくまで便宜的なものであって、ここでは一つの典型的な歩みを示したにすぎない。 地域・自治体の公民館史はおそらくそれぞれ固有の歩みをたどってきたに違いない。たとえば東京などでは、第一世代の歴史をまったく欠落している自治体が少なくないし、逆に戦後二七年間アメリカ占領下にあった沖縄では、おくれて第一世代の特徴である自治(区・あざ)公民館を始動させ、それが現在でも集落レベルの主要な形態として機能している。ちなみに沖縄における本格的な公立公民館の登場は、上記の第三世代の時期、つまり本土復帰(一九七二年)以降のことであった。しかし地域史的な違いにもかかわらず、全国各地の自治体・公民館が、それぞれの自己発達の歩みをたどってきたことは確かなことであろう。
ところで、第一世代から第四世代の諸特徴・キーワードは、歴史的に創出され、そして世代的に継承(挫折もある)され、公民館の発達の実質を形づくってきた。いまこれらを理念型(マックス・ウエーバー)的に構成すれば、五〇年の歳月のなかをあゆんできた日本の公民館のある典型をえがきだすことになるし、また第五世代の公民館を模索するステップにもなろう。
第五世代の公民館論
ー21世紀「地域」創造の視点にたってー
公民館は図書館等と比較して相対的に法制上の位置づけが弱く、また国家政策上でも冷遇されてきた経過がある。それを理論的に補正し、制度上も公的機関としての位置づけを確立していくために、たとえば公民館の教育機関化、公民館主事専門職化、その基準法制構築などの諸研究が重ねられてきた。私もその作業に参加してきた。
しかしこれまでの公民館研究は、その貧弱な体制を強化するという問題意識から、どちらかといえば制度論に傾斜しがちであった。「教育機関」「教育専門職」化についての論議はたしかに重要な理論的課題を鋭く提起したが、公民館の地域社会教育機関としての本来の機能、その豊かな拡がりをかえってせまく限定し、「教育」「学習」のみの問題として細く閉じこめてきたきらいはないだろうか。もっと公民館の事業・内容論を広く「地域」の視点から解き放って、実践的具体的に幅ひろく追求していく必要があるだろうし、さまざまの住民の、多様な生活や文化や地域の課題にかかわって、多元的に公民館の役割を考えていく必要があるだろう。
鋭い議論はときに視野をせまくする。たとえば自治公民館やコミュニィティ・センター、あるいはボランティア・ネットワークの問題などは、教育機関化や教育専門職化の論議のなかからはむしろ否定的にとらえられる側面があった。しかしその積極的な役割について、あらためて地域創造と公民館論の構築のなかに正当に復権させていくべきではないか。
これまでの公民館研究のせまさを克服し、新しい展望を創りだす必要がある。第五世代の公民館論としては、どのような方向が模索されるべきか。前節に続けてみると、次のように言えないだろうか。
(5) 第五世代「地域創造型公民館」(九〇年代後半から二〇〇〇年に向けて、キーワード・事業論再構築、住民活動・文化協同運動への参加、自治体生涯学習計画の中核、など)
その公民館構想を具体的に実現していく上では、どのような実践的な課題が考えられるか。問題提起として次の一〇点を取りだしてみたい。紙数の関係で項目のみの提起に止まることをお許しいただきたい。(なお部分的な説明は本誌一九九五年四月号拙稿「社会教育施設の新しいイメージ」参照)
Ⅰ、公民館「学習」の枠組みを解き放つ。環境、福祉、保健、平和、人権など切実な生活課題、地域課と結びつける。
Ⅱ、「文化」活動を公民館事業の重要な一環とする。音楽、芸能、祭りなど楽しい自己解放的なプログラムを重視する。
Ⅲ、子どもと若者の参加、公民館活動の主体的担い手としての位置付け。プログラム、運営審議会参加、たまり場保障。
Ⅳ、自治意識に根ざすボランティア・ネットワークの組織化と積極的奨励。各種事業・活動へのスタッフ集団の編成。
Ⅴ、地域住民の自治組織活動、自治・集落公民館、さらに地域コミュニィティ・センターなどとのネットワークの形成。
Ⅵ、学校の地域開放、大学公開講座など、学校を地域に開く活動への参加。地域運営委員会、地域教育会議などの奨励。
Ⅶ、関連する行政・施設との連携。学校をふくめて福祉、保健 医療、環境その他の行政サービスの連結点としての役割。
Ⅷ、社会的不利益者、被差別少数者に開かれる施設。障害者、外国人住民、高齢者などの学習・文化活動機会の保障。
Ⅸ、公民館館長・主事などの職員集団の共同・連帯の力量こそが新しい公民館の展望をひらく原動力である。公民館運営審議会や諸運営委員、ボランティア・スタッフとの協力。
Ⅹ、自治体生涯学習(社会教育)計画のなかに公民館をしっかりと位置づける。その際住民の認識と支持が不可欠だ。
すでに与えられた紙幅はこえてしまった。上記「一〇の課題」はやや一般的であって、具体的にはそれぞれの地域・自治体の固有の状況のなかで、発達論的な視点から、たとえば地域的な公民館「一〇の課題」を個別に検討してほいしのである。そのための課題提起となれば有り難い。(和光大学)
【月刊社会教育】1996年12月号(同号)
公民館の可能性の追求
ー三つの「提起」を読んでー 小林文人
自治体制度としての公民館の“発達”
八月中旬に前記「問題提起」を書いたあと、全国集会(埼玉)に参加、九月初旬は沖縄に1週間滞在し、その帰路、北九州市で開かれていた公民館史研究会(第一〇回)に参加した。沖縄では「県民投票」(九月八日)を前にして、各地の公立公民館では(また集落の公民館でも)、コンサートなどいろんな集いが開かれていることが報じられていた。公民館は“生きている”という実感であった。
しかし北九州では、いま公民館が「消える」「終末期のはじまり」という報告を聞いた。当局の「市民福祉センター」構想に公民館が制度的に吸収されようとしているのだ。一九五〇年代に日本一とうたわれた旧八幡市公民館、その時代から一すじに公民館を生きてきた小野隆雄さんの報告だけに、その怒り、嘆きは切々と胸をうつものがあった。
北九州市の公民館制度改悪の施策(事業団委託)は一九七六年から進行してきた。前記・第四世代の公民館「委託合理化」はすでに七〇年代から始まっているわけだ。公民館創設から二〇年あまりかけて蓄積してきたものを、その後の二〇年で取り崩してきたような経過が透けて見える。かって公民館活動の中から育ち、そして公民館を支えてきた住民たちも、この間に姿を消していったのだろうか。
他方、手塚報告によれば、いま信州・松本では、公民館が「実に面白い」という。「公民館を中心に住民運動のネットワークが身近な地域に着実に広がって」いる。しかも松本市各地区の公民館の整備拡充(現在二二館、将来二九館)は、地域「福祉ひろば」構想と結合することによって具体化しようとしている。北九州とは対照的に異なる。この違いはどこからくるのだろう。
松本市ではこの二〇年あまり前から「主事集団の組織化と地区公民館整備」の努力が重ねられてきた経過がある。自治体の計画と施策のなかに公民館制度がしっかりと根をおろし、公民館を支持する住民もまた着実な広がりを見せてきている。「松本らしさ」一〇点がこのことを実証している。
自治体における公民館制度の創設とその“発達”について、プロセスは地域的に多様に違うが、その歴史的な意義は共通して重要である。渡辺報告の場合は、かっての「枚方テーゼ」(一九六三年)を発信した自治体からの問題提起である。周知のように、枚方市ではテーゼ当時まだ公民館は設置されていなかった。それだけに一九八二年(と記憶している)、自治体として初めて公民館制度が創設されたことはやはり画期的なことであった。それから今日まで、複数館体制で公民館が整備され、多彩な活動が展開されてきたこと、その発達史については多くの人が注目しているところであろう。
あらためて公民館の独自性を問う
渡辺報告は、公民館以外の施設の可能性、施設利用の自由と開放性、固い運営、専門職とはなにか、貸館の意義など、総じて公民館中心主義の狭さについて辛口のコメントを提起された。傾聴すべきである。「営利事業に貸すこと」など論議すべき点はあるが、しかし公民館が住民にとって自由かつ柔軟に開かれ、住民の自主活動や主体性を基本的に尊重していこうとする姿勢については共感する。
もし公民館が、固い運営や官僚主義的な管理体制に毒されているのであれば、これを改革していく努力が求められなければならない。だがその現実を否定するあまり、公民館制度それ自体を消極的にみる見方は短絡的であろう。他方で、住民の自主活動や主体的なエネルギーの発展のために、それに参加する方向で、公民館として、多彩で面白い企画や主催事業が積極的に取り組まれることは必要であろう。公民館だからこそ出来る独自の役割を追求していきたい。そのなかで職員が果たす役割、その専門的な力量もまた期待されるところが大きい筈だ。ただ「専門職」論が単に制度論のレベルだけで狭く閉ざされてしまう問題点については前述した。
かって公民館万能論がいわれたことがある。公民館はたしかに万能ではない。最近、公的サービス見直し論とも関連して公民館無用論がいわれた。しかし公民館は地域と住民にとって明らかに有用である。その独自な役割と可能性は五〇年の蓄積のなかから実証できる。いわゆるコミュニティ・センターの役割を否定するものではないが、単に「気軽に便利に使える」コミセン的利用にとどまらない、公民館としての積極的機能を、地域とのかかわりで、多彩に多元的に創出していく必要があろう。
基本理念として、あらためて「枚方テーゼ」やユネスコ「学習権宣言」(一九八五年)を想起しておきたい。
公民館の人的体制の協同
遠藤報告からは、重要な課題を二つ提起していただいた。一つは公民館と地域との具体的なかかわり、とくに生活・労働の場面に、また学習から疎外されている人々に、どのように接近しうるか、その多様な可能性について、の問いかけである。たしかに第五世代の公民館実践は、「労働」との接近という大きな宿題を含めて、新しい地域状況のたしかな認識のもとに、そのような課題への挑戦が求められている。事実、意欲的な自治体、公民館では、さまざま実践的模索が始まっている。たとえば障害者への取組みや外国籍住民の学習権保障の試みなど。それらをどのように交流し、共有し、発展させていくか、注目されるところである。
あと一つは公民館をめぐる職員体制、住民の学習援助体制の再評価についてであった。遠藤報告は、住民の学習活動をささえる社会教育労働の担い手についての関心から、渡辺報告とは対照的に、社会教育専門職員あるいは指導員等の役割、その位置づけ直しについての問題提起であった。
言葉をかえれば、公民館をめぐる人的な体制をどう考えるか、という問いでもあろう。紙数の関係で本論ではこの点についてほとんど触れることができなかったが、学習者としての住民と、援助者としての職員というこれまでの二分法を、もっと重層的に再構築してみる必要があるのではないか、と考えている。つまり職員の構成が事実として多様化し(管理層、専門職員、事務職員、非常勤指導員、パート職員等)、また住民もまた学習・文化活動への参加の形態からいって一様ではなく(リーダー層、ボランティア、学習者等)、さらにその中間に、両者の特性をあわせもつ専門スタッフ(公民館運営審議会委員、各種運営委員、実行委員、住民・嘱託職員等)が躍動的に登場してきている。それぞれの独自の役割と協同的な関係の構築によって、公民館の人的な体制が新しい構図で機能し始めている。総体的にみれば公民館の機能としての「学習権保障」協同体の可能性をもっているとも言えよう。もちろん、住民委託「指導員」「嘱託職員」の問題は(「委託合理化」の)矛盾的な側面を含むが、積極的な意味でとらえれば、公民館五〇年の歩み、その蓄積が創りだした新しい状況とみることも出来るのではないだろうか。
説明不足であるが、与えられた紙数をすでに超えた。私の拙論を読んでいただき、傾聴すべきコメントをいただいた三人の方に御礼を申しあげ、また次の機会をまちたい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2-(2) これからの公民館の展望をどうえがくか
-第5世代の公民館論(改訂版)
*「月刊社会教育」1996年12月号・論文に加筆 2005年
月刊社会教育編集部編『公民館60年・人と地域を結ぶ社会教育』( 国土社)所収
○これからの公民館の展望をどうえがくかー第5世代の公民館論、問題提起としてー
1、公民館半世紀の蓄積をみるー三つの論点
2、公民館の自己発達史ー主要なキーワード
3、第五世代の公民館論ー二一世紀「地域」創造の視点にたって
*以上の本文(上掲)のあとに次の4、5が続く-加筆分
4、地域の再生と内発的エネルギーの形成ー拠点としての公民館
なぜいま地域創造なのか。ふりかえってみると公民館五〇年の歩みは、戦後日本「地域」とのたえざる格闘であったといえるだろう。この半世紀の間に公民館をとりまく地域は大きく変動し、そこに依拠する公民館は苦しい転換を強いられてきた。戦後復興期に続く激しい都市化過程、高度経済成長期における伝統的な地域基盤の喪失、過疎過密の地域問題と格差、さらに競争・市場原理経済による地域産業崩壊や生活不安など、これら諸状況に直面して公民館の取り組むべき課題が問われてきた。この間つねに地域は変容・解体の方向をたどり、公民館は自らの地域的基盤を喪失し続けてきた歴史でもあったのである。
地域の崩壊が激しく、地域の諸課題が錯綜をきわめるなか、公民館によってはそういう地域変貌からむしろ遊離し、あるいは地域との関わりを放棄して、個別化し多様化する住民個々の必要に対応するかたちで事業や活動を編成していく動きがみられた。皮肉なことに生涯学習施策の展開のなかでこういう地域遊離型公民館が顕著になっていく傾向があった。あらためて生涯学習のあり方を地域の視点から問い直す必要があろう。
個々の住民は、みな地域のなかに生きている。住民の暮らしは地域の状況と深く関連している。公民館が住民の立場にたつのであれば、地域の状況や変化・発展に無関心ではあり得ないはずであろう。解体傾向にある地域を再生し、住民(子ども、女性、老人、障害者、外国籍住民等)の生活の安定と豊かさにつながる地域を再創造していく視点が求められる。そのような地域再創造の主体としての住民の活力、そして地域にとっての内発的エネルギーの再生に寄与していく公民館の役割こそが期待されるのだ。
それだけに、これまでの公民館五〇年の歳月のなかでは「地域活動」援助、「地域課題」発見、「地域連帯」事業、各種「地域集会」企画、「集落(自治)公民館」援助、「地域づくり」運動、などさまざまの取り組みが重ねられてきた。公民館半世紀の地域史のなかには、全国各地それぞれの展開において、なかに曲折を含みつつ、地域実践的営為が数多く蓄積されてきた。しかしその価値に光があてられないまま、歴史のなかに埋没しあるいは風化してしまった事例も少なくない。いま地域が大きく変貌し、その展望を描き難い状況があるだけに、あらためて地域の歴史に目を向け、その地下水脈を掘り、歴史を媒介としつつ、これからの住民エネルギーの再生と発展を模索していく必要があるだろう。公民館は、そのような地域再生と創造の拠点として、具体的な役割は何かを自ら問い続けていくことが期待されている。
あと一つ関連して取りあげておきたい問題は、公民館五〇年史における「農村型公民館から都市型公民館へ」という類型的な公民館論についてである。農村型公民館から脱皮し都市型公民館へという方向と、そのことによる近代的教育機関としての確立の可能性がやや安易に語られすぎるのではないか。たとえば「三多摩テーゼ」(一九七三年)による都市型公民館イメージがそうである。その背景には農村的地域が解体し広汎な都市化が進行してきた地域状況が伏線になっている。たしかに地域は変貌してきたが、すべて都市に移行するのではなく、また地域そのものが解消してしまうのでもない。農村は変わりつつ新しい農村的地域へ脱皮していく道程があり、他方、巨大に変貌した都市部においても新しい都市的な地域状況が胎動していく事実がある。そこに生きる住民にとっての厳しい地域課題がたえず新しい質をもって現出してくることを直視しておく必要がある。前者(農村型公民館)には地域があり、後者(都市型公民館)には地域がない、とは言えない。また後者に整備された教育機関としての公民館が求められるように、前者にも教育機関としての条件整備が課題となってくる。いま都市部にこそ公民館の地域的な取り組みが新たな視点から構築され、都市状況に対応する地域創造型公民館(公民館がない都市部には地域創造型市民活動やそれを支援する施設)への挑戦が期待されるのではないか。
5、地域創造型公民館における住民の主体性と職員の役割
公民館運営を担う職員集団、それを支える利用者としての住民集団、という関係構図はいま一つの転換点にたっている。二分論的構図から脱皮すべきではないか。公民館活動の主体である住民は、公民館運営においても(単なる利用者にとどまらず)どのように積極的な運営主体でありうるのか、これに公的施設である公民館の管理にあたる職員集団はどのような関わりをもつのか、住民と職員の双方をつなぐ公民館運営の集団的な組織論をどのように構築しうるか、さらに運営審議会委員や各種企画・実行委員などの住民リーダーあるいは講師・助言者などの専門家集団との関係を躍動的にどう創っていくか、などの興味深い課題に挑戦する状況がうまれている。
一つには、何よりも公民館活動に関わる住民の参加が多様な拡がりをもち、それぞれの主体的な意欲や力量が一段とレベルアップしてきている条件があげられる。もちろん地域的な違いはあろうが、各種統計や実践報告等を分析していけば、この事実は明らかであり、戦後五〇年の公民館活動と多彩な課題に取り組む非営利市民活動の拡大と蓄積を象徴する動きといえよう。
他方で、職員集団の状況は(第四世代=行政改革下公民館の時期を経過して)複雑な構成となり、専門職による安定的な主事集団形成という理念型からは逸れた現実が増大してきている。非専門職配置、短期の人事異動、定数削減、減量経営、委託・嘱託化、パート職員の導入等の一連の行政施策は、この間の公民館を支える職員体制を劣化してきた。しかし同時に住民的視点にたつ嘱託職員等による多彩な努力が、ボランテイアの積極的参加も加わって、公民館運営を活性化させている実践も新しく胎動している。基本的課題として公民館主事の専任・専門職化と複数化の課題は主張され続けねばならないが、理念追求のみでなく、このような公民館職場をめぐる現実的状況の認識にたって具体的な対応を考えていく姿勢もいま求められている。
紙数も尽きたが、まとめにかえて、公民館をめぐる住民と職員の新しい関係構図を創り出していく視点を5点ほど提起して、本稿を閉じることにする。
第一は、地域創造型公民館の活動・運営の基本的主体は住民であり、従来の利用者としての受動的位置づけから脱皮し、新しいスタイルの参加・参画の形態を構築していく必要がある。第二に、職員は住民の主体的活動に寄り添い伴奏し、これを支援し援助していく立場からの条件整備、資料提供、専門的助言にあたる。第三に、職員の構成は専門的力量をもった熟達主事を中核としつつ、当然に事務職や経験年数の短い職員、あるいは嘱託・派遣・パートの職員等を含み、また単一の施設だけでなく隣接・関連施設の職員をも含んで柔軟に集団的ネットワークを組織していくことができないか。第四に、言うまでもなく住民の構成も多様であり、そのなかで障害者・外国籍住民等の社会的民族的少数者の参加を位置づけ、高齢者、勤労者、若者とくに子どもの参加も積極的に求めていく必要がある。この点についてはこの間各地に多彩な実践事例が生まれていることは周知のことであろう。第五に、公民館の事業や活動の企画・運営には、住民と職員の両者が協働して取り組むことを原則とし、課題・テーマにそって、両者による“スタッフ集団”(仮称)を機能的に組織し具体的な活動を担っていく方向を考えていく。そのなかではもちろん職員が果たすべき固有の役割が大きい。同時に、住民の側の主体的な取り組み、とくにボランティヤ、公民館運営審議会委員や各種運営委員さらに講師・助言者等の専門家集団のそれぞれの役割を期待しつつ、多彩な取り組みを創出することはできないだろうか。
公民館の実際の運営・活動の形態は、地域の状況と公民館のおかれている諸条件にしたがって一様ではないであろう。しかし地域創造へ向けた共同のまなざしと地域内発的なエネルギーが蓄積されていけば、公民館は新しい可能性をもって甦ることになるに違いない。
3,【月刊社会教育】2002年4月号・所収
公民館施設論の系譜をさぐる
1,はじめにー模索・挑戦の歩み
これまで、公民館の学習論や運営論は多彩に展開されてきたが、その施設論・空間論は貧弱だ、と言われてきた。たしかにそうだろう。日本社会教育学会が“総力”をあげて編集したと評価される『現代社会教育の創造』(一九八八年)や『現代公民館の創造』(一九九九年、いずれも学会特別年報、東洋館出版社刊)の頁をめくっても、このことは否定できないようだ。
しかし現実には、戦後半世紀の歳月のなかで全国的規模で公民館が普及定着し、実際にいま一万八千にちかい公民館が建築されてきているいう事実がある。そこには当然何らかの施設の設計があり、設備の整備があり、公民館という名の空間が物的営造物として機能してきている。理念ないし理論としての施設論は貧弱だとしても、事実としての施設空間は(皮肉にも)むしろ豊富に存在していると言わなければならない。
公民館の施設史は、しかしながら、そう単純ではない。戦後初期の社会的混迷と行財政的貧困、厳しい状況からの出発、新しい歩みにむけての模索、そして挑戦の連続であった。公民館それ自体も確定的な理論体系から出発したのでなく、自ら立地する地域の変貌過程とも重なって、曲折の歩みをたどってきた。徐々に提起されてくる施設の理論や施設計画は、現実の諸条件と多く矛盾し、理念と実際の施設空間とは大きく乖離する場合が少なくなかった。
このような公民館の施設としての展開過程、その事実のなかから施設論的な流れをたどってみると、何が見えてくるのだろう。そして今、どういう段階にあるのか、課題は何か、などについて、大づかみの検討を試みてみたい。
2,公民館・施設計画の胎動
図書館や博物館などと比較して、公民館の施設イメージは多様であり総合的であり、またその反面として、雑多であいまいな側面をもたされてきた。とくに公民館制度創設期の初期公民館は、地域復興の拠点して多面的かつ万能的な役割を期待された向きがあり、産業や福祉等にも関わる機能、たとえば「託児所、共同炊事場、共同作業場」「簡易な医療、衛生事業」等の事例も含んでいた(文部次官通牒「公民館の設置運営について」一九四六年)。なかには当時の失業・失職に対応する授産部活動、あるいは共同浴場、理髪部経営、託児保育活動などの例もみられた(鈴木健次郎「郷土自治建設と公民館」一九五〇年)。そういう中から、主要には社会教育に関わる総合的・専門的・地域的な施設として脱皮していく歩みが重ねられていくのである。
公民館の創設期、その施設モデルはあらかじめ鮮明なものが用意されたわけではない。施設計画を具体化する現実の条件は皆無に等しかった。地域のなかで雑多な機能を背負いながら、厳しい諸条件に規定されつつ、その中で挫折や停滞を含み、模索しながら自らの施設像を地域的に形成していくというような歩みであった。当時の具体的な状況を三つほどあげておこう。
一、戦後直後の経済困窮の時代では、公民館の施設はほとんど既施設の転用・併用・改築であった。たとえば、文部省表彰による選りすぐった「優良公民館の実態」(公民館運営双書3,一九五二年)収録十一事例のうち、新築はわずか二例(青森県大湊町、新潟県葛塚町)のみであった。初期公民館の多くは、旧青年学校、農村公会堂、役場集会所、料亭等の転用施設であって、既施設の枠組に拘束されて機能し始めるのである。
二、物的施設の条件が貧しい事情も反映して、施設に依拠しない公民館の運動論・機能論が一つの潮流となってきた。たとえば「全村これ公民館」「青空公民館」(福井県殿下村)の事例など。施設をもたない「看板公民館」の実態が多くみられた。寺中作雄も「…施設は単に公民館の一面に過ぎないのであって、設備は備はらなくとも魂がこもり町村民の支持があれば立派に公民館の名に値し…」と言っている(「公民館の建設」一九四六年)。 三、法制的基礎である社会教育法(一九四九年)は、公民館の目的(第二〇条)や事業(第二二条)の条項を定めているが、施設に関わる具体的な条件整備の規定は不十分であった。法制定から十年遅れて「公民館の設置及び運営に関する基準」(一九五九年)が設けられるが、その基準性は弱く、施設基準の水準はむしろ低劣であった。
公民館が何らかの施設理念に基づき、また自治体の施設計画に位置づいて、独自の営造物として姿を現し始めるのはどの時期からであろうか。寺中構想による初期公民館の時代は概して施設計画性が弱いのたいして、一九五〇年代後半、むしろ都市部の公民館構想の胎動のなかに体系性をもった公民館施設の先駆的な事例を見ることができるようだ。たとえば、市全域・中学校区単位に本格的な公民館設置を実現した旧八幡市(一九五一年、中央公民館の建設)、図書館構想と並列して独自の公民館を建設した東京都杉並区(一九五三年、杉並区公民館の読書会から原水爆禁止署名運動が始まる)などはその典型的なものであろう(横山宏・小林文人「公民館史資料集成」一九八六年、エイデル研究所、第4部参照)。
そして一九五五年前後の町村合併の時期を経て、六〇年代以降になると、地域によって本格的な公民館の建築が進み、「公民館の近代化」(施設のデラックス化、活動の構造化、職員の専門職集団化、公民館の教育機関化等、小川利夫「公民館論の再構成」一九六七年)の扉がようやく開かれ始める。自治体によって(もちろん格差を含む)固有の施設論をもった公民館計画が、地域的自治的に形成される段階を迎える。
3,公民館施設の十年発展説
公民館の構想も施設論も、初期創設期の原型がそのまま継承されていくわけではない。それらはむしろ時代の推移とともに、変化し発達していくものだ。その意味で公民館の原点と称される「寺中構想」(一九四六年)は、むしろ基点ないし起点といった方が適切だろう。公民館施設史の上でも、公民館初期構想から大きく脱皮し発展しつつ、一九六〇年代からとくに七〇年代の躍動的な展開がみられることになる。
主要な動きをあげてみよう。当時の文部省社会教育局は「進展する社会と公民館の運営」(一九六三年)を出し、日本社会教育学会は画期的な「現代公民館論」(年報第9集、一九六五年、いわゆる下伊那テーゼを含む)を刊行し、全国公民館連合会は全国的規模で「公民館のあるべき姿と今日的指標」(一九六七年、第2次報告・一九七〇年)をまとめている。いずれもその後の公民館の事業論あるいは職員論、そして施設論に関わって、それぞれの影響を与えたものである。
この時期には、とくに首都圏など都市部を中心に公民館の建設が進められる。文部統計上でも、町村合併後の弱小公民館(分館)整理統廃合による公民館総数減の傾向から、公民館本館の設置増を主軸とする施設総数増加の潮流が顕著となる。東京三多摩地区では、公民館関係者による「新しい公民館像をめざして」(一九七三~四年、いわゆる三多摩テーゼ)が作成され、全国的な注目を集めた。これをテキストに住民による公民館づくり運動が拡大していくという新しい動きにも波及していく。
このような状況を背景に、筆者は、公民館施設「一〇年発展説」を仮説的に提起したことがある(月刊社会教育一九七六年七月号「公民館三〇年の成果と課題」)。さらに数年後、浅野平八氏らから「三多摩の公民館づくり」について一文を求められ、そこでも一〇年発展説を書いた(「建築知識」一九八三年五月号)。紙数の関係で詳述できないが、概要を述べれば、次のようなことである。
一九四〇年代後半、初期公民館の時代は独自の施設論は未発であるが、一九五〇年代に入ると「優良公民館」のモデルが登場してくる。施設の中心には共通して大集会ができる講堂(ホール)とステージがおかれ、その周辺に和室、講座室などいくつかの付属の部屋を配置するというのが標準の型であった(小和田武紀「公民館図説」一九五四年、岩崎書店)。しかし六〇年代になると、共同学習の実践や小集団・サークル活動の流れを背景として、大集会機能というよりむしろ小集会室、学習室、あるいは青年サークル室といった小空間に力点がおかれ、視聴覚室、図書室などを備えた公民館が多くなってくる。六〇年代半ばには、体育・レクリェーションなどの諸活動、グループ・サークルの集団的活動、科学の系統的学習、という三つの活動空間を組み合わせた「公民館三階建論」が提起された(小川利夫「都市社会教育論の構想」三多摩の社会教育1,一九六四年)。
そして七〇年代、このような施設論の展開をふまえつつ、さらに新しい時代(都市化)状況と住民の学習文化要求の拡がりに応えるかたちで「三多摩テーゼ」が構想されることになる。すなわち、①出会い・交流のための「たまり場」空間、②住民・市民の自主的な集団活動の「拠点」、③現代的諸問題に迫る「大学」的な学び、④さらに多様な文化要求と文化創造の「ひろば」、という「公民館・四つの役割」論を立脚した施設論が画かれた。それまでの集会と教育・学習という二つの並立しがちな公民館機能論を(公民館三階建論を媒介としつつ)、いわば四つの機能論から現代的に再構成し発展させたものといえる。具体的な施設内容として、市民交流ロビー、ギャラリー、団体活動室、青年室、ホール、保育室、図書室、美術室、音楽室、実験実習室、視聴覚室等を含む「標準的施設・設備」(計約2,000㎡)が表示されている。七〇年代における公民館・施設論の一つの集約であり、また八〇年代以降にむけての課題提起でもあった。
三多摩テーゼの策定には筆者も参加した。今でも忘れがたい充実した作業の2年間であった。とくに付け加えておきたいことは、四つの役割、七つの運営原則、あるいは標準的施設・設備等の論議が、単なる机上の空論としてではなく、当時の三多摩各自治体公民館のいずれかの実践的な試みや施設の先駆的な事例を基礎にして、仮説化し具体的な“テーゼ”として提起されている点である。
4,地域はフィールド、公民館施設再創造の課題
すでに三多摩テーゼから四半世紀余を経過している。その後、これをまた新たな起点として、一九八〇年代、九〇年代、そして新世紀に向けての公民館施設論の再吟味、再創造が重ねられてきている(と見ておきたい)。一〇年発展説の「一〇年」という区切りの当否は別として、施設が変化し“発達”していくという事実は重要である。
一九八〇年代以降の公民館施設はその後どのように展開してきているか、いま詳細に示す余力がない。個別の施設・設備論の具体的な事例は別にして、この間の流れや方向、そして課題のいくつかあげて、まとめにかえることとする。三多摩テーゼの批判的検討とも関連して考えておきたい。
第一は、テーゼ以降、公民館施設利用の主権者というべき「住民の視点」が登場してきたことである。もちろん三多摩テーゼが住民の視点をもたなかったわけではないが、当時、テーゼ作成者に住民が参加する状況ではなく、その内容にも住民自治の立場が弱いことが指摘されてきた(拙稿「三多摩テーゼ二〇年」多摩社会教育館「三多摩における社会教育の歩み」Ⅶ、一九九四年)。その後、東村山市や茅ヶ崎市等にみられる「公民館づくり住民運動」や、住民参加による「公民館建設(改築)委員会」等の手法が一つの潮流となり、その拡がりのなかで「住民の視点」にたった施設・設備論・運営論が具体的に提起されてきている。
さらに今後は社会教育に関わるNPO活動との関係で、公民館の施設論を市民活動支援の観点からどう展開していくかという課題も見えてきている。
第二は、障害者にとっての公民館施設・設備が拡充され発展してきたことである。三多摩テーゼは、いわゆる「忘れられた人々」にとっての公民館論についてほとんど触れるところがなかったが、その後の障害者青年学級や喫茶コーナーの実践と運動は静かな流れとなって各地に鼓動し、施設論についても興味深い取り組みや提言(小林繁編著「学びあう障害」二〇〇一年、など一連の報告)がなされてきた。自治体の公民館施設計画としては、町田市では障害者青年学級等の“蓄積してきたものを大切に”“誰もが使いやすい公民館をめざして”「市民参画による新しい公民館」(公民館移転建設検討委員会報告書、一九九九年、同「実施計画」報告書、二〇〇〇年)が策定された。公民館五〇年(三多摩テーゼから二〇年)を経過した段階での一つの到達点といえよう。
障害者だけの問題ではなく、外国籍市民など社会的マイノリティにとっての公民館施設の在り方にについても今後問われるべきであろう。
第三は、子どもと若者にとっての公民館施設論を再生させていく課題である。三多摩テーゼは(若者のたまり場論は別として)子どもについては全く触れることろがない。しかし地域施設の重要な役割として、つねに子どもへの「まなざし」を欠落してはならないのではないか。ドイツの社会文化センターが多く地域の子ども施設としての側面を備えているところから学ぶところは多いし、また日本でもこの間「子どもの居場所」や「ひろば」「たまり場」づくりの運動が創意あふれる実践を拡げてきている(岡本恵子「“ばあん”という居場所」本誌、本年一月号)。地域に結びついた活動に取り組んできた公民館は児童館的な性格と施設論を内包する事例が少なくないことを想起しておきたい。
あと一つ、このようにみてくると、公民館は独立施設であると同時に、地域のなかの一施設として関連諸施設との有機的なネットワークを形成する中で、その施設論を新しく構築していく時代に入ったのではないか。図書館や博物館だけでなく、上記の児童施設や(これまでその異同が問われてきた)コミュニテイ施設や自治公民館、とくに地域の学校との相互関連などを積極的に追求していく必要があろう。新潟県聖籠町「住民が担う学校づくり」の一角に「地域交流ゾーン」が設けられているが、まさに学校と密着した公民館施設そのもの、「学校の森づくり」と合わせて印象的な風景となっていた(手島勇平「住民自ら担う中学校づくりへ」月刊社会教育2001年5月号)。
まさに地域は公民館のフイールド、公民館はまた地域の施設でなければならぬ。
4,「これからの公民館-新しい時代への挑戦」(国土社、1999年)総論→■
5,公民館・施設空間論をめぐって
(南の風1640~1741号、2006年)→■
6、『現代公民館の創造―公民館50年の歩みと展望』日本社会教育学会編
特別年報 (東洋館、1999年)
序章 公民館研究の潮流と課題
1,公民館制度の多様な展開
公民館50年の歩みは、まことに起伏に富み、曲折に充ちた歴史である。そして、これからの道程もまた新しく複雑な展開をたどるに違いない。公的機関として一定の法制的基礎をもちながら、これほどの多様性と変容性をもって動いてきた施設は他に類がないのではないか。その多様性は、一つは歴史的な展開過程のなかに、二つには地域的な定着過程のなかに、さらに三つに施設機能の実態のなかに、さまざまのバリエーションとしてみることができる。変転の歴史があり、格差の亀裂があり、停滞や混迷を含みつつ、またそれからの脱皮や改革の胎動もみられた。法制的に公民館制度自体の弱さや基準のあいまい性があり、その反面として地域的に自治的な、多様な取り組みや創造的な発展の努力が重ねられてきた。
このような多様かつ複雑な展開は、制度的な弱さとともに、また理論体系の未熟さの現れでもあろう。そこには克服すべき多くの課題が残されていると同時に、他方で、新たな発展と創造の可能性が秘められていることをも意味している。公民館50年の歴史と実体の多様性をふまえて、私たちは新しい未来への鍵を見出さねばならぬ。それもまた決して単純なかたちではないはずだ。公民館50年のなかで堆積し蓄積されてきたもの、それをどう捉えるか、それも一元的な見方では捉えきれない。多元的、複眼的な視点をもって腑分けしてみる必要がある。そうでなければ公民館の総合性や複合性といった固有の役割なり新たな可能性を画きだすことにはならないだろう。
周知のように、公民館制度は戦後教育改革に先がけて1946年の文部次官通牒に始まり、翌47年の教育基本法(第7条)への位置づけ、そして49年社会教育法による法制化(第5章)を重要なステップとして、まずは農村部や中小都市を中心に全国津々浦々への普及が始まった。それから半世紀を経過した現在、紆余曲折の道程を歩みながらも、全国の公民館総数は(類似施設までを含めれば)18,545館という水準(文部省社会教育調査報告書、1998年)にまで拡大してきた。しかもこの数値には、条例に基づかない数多くの自治(集落)公民館は含まれていない。
公的機関としての設置数は、義務教育機関である中学校総数をはるかに凌駕し、小学校総数との対比でも10校あたり7.6館という規模に達する。少なくとも統計的には、日本の代表的な公的社会教育機関としての実体をもち、その普及度は国際的にも注目される水準にあると言える。それだけに実質として公民館がどのような機能をはたし、また新しい時代に向けていかなる展望をもち得るか、そしてその理論体系をどう構築し得るか、等の課題に迫っていく必要がある。公民館50年の歳月は新たな理論化の作業を求めている。
2,公民館研究の潮流
公民館半世紀の歩みは、そのままわが国の戦後社会教育50年の歴史と重なっている。よくもわるくも日本の社会教育は公民館活動を中心に展開されてきた。固有の社会教育施設として、公民館に体質的に胚胎してきた特徴、たとえば地域施設としての性格、都市的というより農村的な構想、大学開放からの距離、労働組合運動との遮断、職業訓練機能の欠落、などの諸側面は、そのまま日本の社会教育が内包する歴史的な特質でもあった。
日本社会教育学会(1954年創立)の研究活動は、したがって創立当初から、公民館問題を抜きにしてはあり得なかった。学会創立の時点で、すでに公民館を設置する市町村数はほぼ80%に達し、公民館に関する文献・資料も相当数が世に出ていた頃である。だが、学会第1回研究大会以降のプログラムによると、また、それを反映する学会年報『日本の社会教育』(第1集、1955年)や、少し遅れて刊行される学会紀要(№1,1964年)所収の論文等を見ると、初期の段階では「公民館」そのものををテーマに掲げる研究発表や論文は意外に少ない。(1)
しかし当時の、たとえば小集団学習や青年運動や社会教育行政などの諸研究には、公民館問題がいわば共通分母的に介在していたと見ることができよう。それが1961年秋の第8回大会において、学会「宿題研究」として「公民館に関する研究」を本格的に取りあげる背景でもあり土台でもあった。このとき、公民館設置に関する文部次官通牒からすでに15年が経過していた。
周知のように、この宿題研究は4年後に学会年報第9集『現代公民館論』(1965年、小川利夫編)としてまとめられた。1960年代の急激な地域構造変化を背景として、新しい段階への日本の社会教育の質的な発展の課題が、公民館研究として追究されたと言えよう。公民館に関する「宿題研究」、その結実としての「年報」において、公民館の歴史研究も、その実態把握や理論的追究も、初めて起点をもつことができたし、また「公民館主事の性格と役割」(いわゆる下伊那テーゼ)についての9地点を結ぶ全国的シンポジウムも行われ、公民館にかかわる「共同思考」(同書「まえがき」)の初めての試みとして注目を集めてきたのである。
これを契機として、公民館に関する理論的かつ実践的研究は大きな拡がりを見せるようになる。学会では公民館についての研究発表・課題研究が多くなり、また、その後の学会の宿題研究「都市化と社会教育」「社会教育法制研究」「社会教育職員研究」「コミュニティと社会教育」「社会教育の計画と施設」等において、それぞれの課題との関連で、間断なく公民館問題が取り上げられてきた。その後、これらの蓄積を吟味し集成するかたちで、学会創立30年記念事業(1984~88年)が企画され、「社会教育研究30年の成果と課題」がまとめられた。(2)ここで公民館に関する研究成果や文献資料が総合的に検討され、この段階における研究総括的な作業がおこなわれた。
公民館研究の盛行の背景には、公民館実践や運動の活溌な展開があり、その過程で新たな公民館の法制や構想等が提起されてきたことが注目される。主要な動きをあげれば、全国公民館連絡協議会(当時)による「公民館単行法」の運動(1953~58年)、その後の全国公民館連合会の「公民館のあるべき姿と今日的指標」の提起(1967年)、また地域的なレベルからは、都市公民館の構想(「公民館三階建論」、1964~65年)、前記の「下伊那テーゼ」(1965年)、東京都「新しい公民館像をめざして」(いわゆる三多摩テーゼ、1973~74年)などがあり、いずれも全国的な規模でひろく論議されてきた。(3)
3,現実科学としての公民館研究
以上のような動きに刺激され、あるいはこれと連動して、1970年代はとくに自治体(市町村)の公民館実践が進展し、独自の公民館計画や構想が活溌に模索された時期であった。また公民館設置を求める住民運動が、東京三多摩地区など首都圏で大きな拡がりを見せた。公民館を「施し設け」られてきた客体としての住民が、この時期ようやく公民館設立運動の主体としてあざやかに登場してきた地域が少なからず現れた。(4)
初期公民館時代を経て、1950→60→70年代にいたる公民館の地域定着とその実践の推移を特徴的に言えば、行政の主導的役割としては、国(文部省)→都道府県→市町村へ、事業・活動の担い手としては、行政職員→公民館職員→住民(参加)へ、という比重の流れを指摘できるのではないだろうか。もちろん地域格差は大きいが、おおまかな動向としては、70年代において公民館における市町村と住民の果たす役割が相対的に増大してきたことは確かであろう。そこには市町村主義と住民主体主義ともいうべき、社会教育法が本来期待する構図が現実的に動きはじめている。地方分権・住民自治に根ざす公民館への潮流である。
公民館設置についての文部省統計では、70年代において全国の公民館総数が1万5千に達し、1981年統計では1万7千を超え、うち本館数が1万の大台に達する。量の増大だけでなく、質的に新しい公民館実践がこの時期に胎動をみせる。たとえば東京三多摩の場合、公民館保育室、若者のたまり場実践、障害者青年学級、講座の自主企画、住民参加による広報づくり、公民館運営審議会委員の準公選、利用者懇談会・市民の集い、など多彩な取り組みが始まっている。(5)その意味で70年代には、公民館の躍進というにふさわしい状況がみられた。70年代の公民館研究の活溌な展開も、地域・自治体のこのような実践的な動きを背景にしていた。
しかし1980年代以降になると、公民館をとりまく状況は大きく変化する。国策としての行財政改革や生涯学習体系への移行、また社会教育終焉論(6)などの影響をうけて、公民館の委託・合理化、コミュニティ・センター化、職員体制の縮小・嘱託化、受益者負担論、などの厳しい動きが公民館を痛撃する。生涯学習体系移行を方向づけた臨時教育審議会(1984~87年)内部の論議では、公民館の「歴史的使命は終わった」(7)とする意見が出された。このような公的社会教育の「見直し」路線を背景として、この時期、公民館の停滞状況は深まる。
1980年代から90年代にかけては、全国的にいわば「肥大」した公民館の実体を背景に、行政改革ならびに教育改革(生涯学習体系移行)の二つの「改革」論議が並行し、それに挟撃されて公民館のあり方が問い直される時期となった。公的条件整備を基調とする公民館論から、営利的「民間事業者」との関係や、さらには「非営利・市民活動」(NPO)としての「民間」との関係が新たな課題として提起されてきた。1998年3月成立の「特定非営利活動促進法」は「社会教育の推進」(同法第2条別表)を掲げ、NPO活動と公民館の基本的なあり方をどう考えていくか、がこれからの大きな研究課題とされている。
公民館に関する研究は、つねにこのような現実の政策動向と、地域の公民館の実態・実践と無関係ではあり得ない。変転極まりない現実の状況を認識していく必要から、ともすれば状況に左右され、現実の後追い的な研究を強いられる一面もないではない。しかし厳しい現実認識を基礎に、ときに状況と対決しながら、公民館の理論形成を追究し、たえざるその再構築の努力がこの間営々と重ねられてきたこともまた確かである。その意味で現実科学としての「公民館学」形成に向けての道程を歩み続けてきたとも言えよう。
4,公民館研究の領域と争点
しかし近接の施設である図書館や博物館が、それぞれの「学」の体系を標榜し追究してきたのに対し、公民館については真正面から「公民館学」を掲げる研究はほとんどない。個別に「学」的な主張が皆無ではないが、少なくとも体系的には展開されてこなかった。それは「社会教育学」形成の歩みのなかに公民館研究が不離一体のものとして位置づけられてきたことによるのであろうが、同時に、やはり公民館研究における理論的体系化の努力がいまなお不充分であり、体系的な「公民館学」の形成としてはなお多くの課題を残している証左であろう。
これまで公民館に関する研究・報告や記録は決して貧弱とは言えない。問題は、それらがどのように理論的体系を構成し得るかである。この点に関しては、前述した学会30周年記念『現代社会教育の創造』が多彩な公民館研究を検討し、一応の整理して、次の6項目の柱を提示している。
すなわち、(1)歴史研究(戦前的系譜を含む)、(2)公民館法制・組織論、(3)公民館の計画と施設研究、(4)公民館の事業・運営論、(5)公民館主事論(社会教育職員の項)、(6)自治(集落)公民館研究、である。さらに、関連領域としての地域福祉と公民館の関係が、研究課題として掲げられている。
ここには公民館に関する研究領域の拡がりと蓄積が、全体を俯瞰するかたちで整理されている。前述した学会年報第9集『現代公民館論』が本格的な公民館研究の起点であり、そしてこの学会30周年記念『現代社会教育の創造』は、それからほぼ四半世紀を経過した時点での中間総括とみることが出来よう。しかしこれら各領域について、どのように体系的理論化が深められてきたかについては、さらに充分に吟味されなければならない課題である。
振り返ってみると、これまでの公民館研究のなかでは、いくつもの注目すべき理論的な論争が展開されてきた。同時にこれと関わって、実践的にも対峙的な方法の模索や検討が重ねられてきた。理論的な論争と実践的な模索とは、ともに交錯しながら、公民館の基本的な性格や機能に関わる重要な争点を提起し、その論議のジグザグの過程をくぐりつつ、公民館理論の深化が追究されてきた。学会レベルの論争的な試みは、そのすべてを覆うものではないが、その論議の主要な流れを創り出してきた。
その意味で、いま公民館論争史を綴る必要を痛感する。公民館50年の歩みはそれを可能にする充分な歳月と言うべきであろう。試みに公民館発達史に焦点をあてて、例示的に争点として提起され論議されてきた項目を想起してみると、課題は次々と噴出し、われわれはすでに多くの“争点の蓄積”をもっていることに気付く。(紙数の関係で文献省略)
1,公民館の戦前的な系譜をどう見るか。「歴史的イメージ」(小川利夫)と しての公民館と、その歴史的実像との関連をどう理解するか。
2,公民館設置についての次官通牒ないし寺中構想の形成過程。いわゆる「二 つの次官通牒」(朱膳寺春三)をめぐる問題。
3,文部省の公民館構想とアメリカ占領軍の対日教育政策との関係。関連し て占領下沖縄における公民館制度の定着過程の経過と要因分析。
5,一般行政下における初期公民館と教育行政下への公民館制度編入の問題。
6,公民館・寺中構想とその定着過程にみる公民館の地域構想との異同。た とえば原水爆反対署名運動を取り組んだ杉並公民館「安井構想」の位置。
7,公民館法制化、公民館単行法運動をめぐる争点。
8,公民館学習論としての共同学習・系統的学習等にかかわる論議。
9,全公連「公民館のあるべき姿と今日的指標」をめぐる運動と評価。
10,公民館とコミュニティセンターの関係をめぐる競合と矛盾の問題、など。
もちろんこれに尽きるわけではないだろう。発達史だけでなく、公民館研究の諸領域に関してもさらに深めるべき争点・課題は少なくない。しかし、これら研究争点の論議が単発的に終わる場合も少なくなく、理論的体系化に結びつくような論争と蓄積を充分もち得ないまま、今日まで経過してきている状況も否定しがたい。
5,公民館をめぐる論争、その蓄積
ここで公民館をめぐるこれまでの論議・論争を総括的に検討する余力はないが、公民館の基本的な性格と機能の問題にかかわって、学会等における主要な論争の流れを大きく整理してみるとどうなるか。これらの争点をさらに丁寧に深めていけば、公民館の基本的なあり方にかかわる理論体系の形成に寄与することになろう。おそらく本書の関連章でも論争の内容は取りあげられるであろうが、ここではまず序章としてその扉を開けることにする。
第一は、公民館創設期からはじまる初期論争である。公民館の機能論と施設論、あるいは地域振興の運動論と社会教育の専門的機関論についての論議が展開された。公民館の機能論ないし運動論は、その初期構想(寺中構想)から胚胎し、社会教育法制定後の法制化された公共機関しての公民館のあり方にもかかわって、たとえば「公民館万能論」についての論議が活溌であった。(8)「青空公民館」といわれたように施設自体が貧困であった当時の現実的条件も背景にあって、初期創設期の公民館論は施設中心でなく、農村を基盤とする生活全般にわたる万能的な機能(たとえば産業復興、自治振興、授産、福祉、社交娯楽など)が期待されたのである。それに対して社会教育施設としての公民館の、その固有の専門的役割と必要な条件整備を主張する立場が次第に台頭してくる。いわば運動論的公民館像と社会教育機関としての公民館像の二つの考え方である。直ちに真正面から論争が闘わされたというかたちではなかったにせよ、当時の「公民館人」意識の底流に、対抗しつつ深く滞留してきた「論争」の側面をもっていた。そしてその後も公民館の基本的なあり方をめぐる争点として、地域総合的機能論と社会教育専門的機関論の論議は、ときに姿をかえつつ、なお公民館論議の基層に流れている。
第二は、いわゆる公民館「近代化」論争である。初期公民館の農村的地域基盤が大きく変貌し、都市化・工業化・賃労働者化の状況が進行し、公民館にかかわる一定の行政的整備もすすむなかでの近代的な公民館のあり方が論議された。かっての農村型から、1960年代地域変貌と都市化状況を背景とする都市型公民館への探求でもあった。学会レベルの論争だけでなく、新しい地域状況に対応する公民館像を求めて、文部省「進展する社会と公民館の運営」(1963)や全国公民館連合会「公民館のあるべき姿と今日的指標」(1967)が出され、とくに後者については各地方公民館関係者による広範な論議が拡がった(9)時期であった。いずれも農村型公民館からの脱皮、その意味での公民館「近代化」を志向する努力がみられたのである。
公民館「近代化」論争には、小川利夫(「現代化」論争と言っている)の果たした大きな役割を忘れてはならない。(10)具体的には(1)前述「公民館三階建論」の提起、(2)自治公民館方式の批判、あわせて市民会館・公民館方式をめぐる論争、(3)前述「公民館主事の性格と役割」(下伊那テーゼ)や職員不当配転問題等をめぐる公民館主事論、(4)公民館「近代化」五つの指標をめぐる論争、等において常に重要な問題提起者であり、積極的な論客であった。この時期の「近代化」論争がその後の公民館理論及び実践の発展にとって大きなステップになったことは確かである。
しかし小川の活溌な問題提起に対して、双方向性をもった論争が重層的に蓄積されたかという点ではどうであろうか。たとえば、いま住民自治とその協同性の観点から、あらためて注目されている自治(集落)公民館の問題については、上記(2)自治公民館論争があらためて吟味される必要があると思われるが、(11)宇佐川満や倉吉(朝倉秋富)・久美浜(友松賢)の側からの本格的な反論や論争は返されていない。また(4)公民館近代化・五つの指標論に対する小林文人との論争は、(12)、宇佐川満を含めて再論があり、また学会年報『都市化と社会教育』(1969)所収論文でもコメントが加えられたが、それ以上の展開はみられなかった。
6,公民館研究における制度論と機能論
公民館問題をめぐる論争の第三の大きな展開は、1980年代以降の行財政改革下における公民館「合理化」問題と、それに続く生涯学習体制への移行による公民館制度見直し・転換政策をめぐっての論議である。日本の生涯学習政策の導入は、新自由主義路線による公的セクターの縮小・民間活力導入(行政改革)政策と連動して展開するという不幸な出発であって、その具体的な施策は公民館の公共的体制を積極的には評価せず、むしろ痛撃してきたのである。生涯学習政策の導入とともに公民館振興策は消極的となり制度的な見直しが求められるという、何とも皮肉な経過であった。これに対抗して、たとえば社会教育の公的条件整備研究が公民館を含む「基準法制」提起を試み、あるいは自治体によっては公民館の公共的地域配置を重視した生涯学習計画化が推進されるなどの取り組みがみられた。(13)
公民館「合理化」問題は、すでに1970年代後半から、とくに大都市財政困窮を背景として北九州・福岡などで強行された経過がある。しかし1980年代後半以降になると個別自治体問題ではなく、社会教育ないし生涯学習の公共的体制そのものの転換が企図され、その後さらに「生涯学習振興整備法」(1990年)策定に至り、さらには1998年以降の地方分権・規制緩和策による社会教育法改正の動きなどとも連動してくるのである。
このような状況を背景に、公民館の社会教育機関としての公共性、その専門性と独自性、必要な条件整備のあり方が理論的な課題として論議されたのは当然のことであった。また同時に、新たな生涯学習の推進にとって、公民館が地域社会教育施設として担う固有の公共的役割を明確にし、住民の生涯にわたる学習権保障の立場からの公民館機能のあり方が追究されてきた。
以上のように公民館をめぐる論争的な潮流を振りかえってみると、社会教育機関としての公民館の制度的なあり方が一貫して課題となってきたことが分かる。もともと公民館が依拠する法制自体が強固なものでなく、おかれている実態も貧弱な条件からの出発であり、自治体間には多くの格差を含み、しかも政策の動向が変転きわまりない状況のなかで、社会教育機関としての公民館の制度的確立とその理論的体系化がひたすら究明されてきたと言えよう。関連して人的条件としての公民館主事の専門職化問題もまた当然の理論的課題であった。これら教育機関としての公民館の制度論を深める課題については誰しも異論はあり得ないだろう。
言うまでもなく、公民館問題への制度論的なアプローチは、それが果たす役割の機能論的なアプローチと不可分の関係にある。いかなる制度がよりよい機能をもたらし、あるべき機能のためにどのような制度が求められか、両者は深く関係している。しかし、公民館をめぐる論争の流れを振りかえってみると、その初期段階から、制度のあり方と機能のあり方が対峙的に、相互背反的に論議されてきたという問題がある。地域・総合的な公民館の役割と社会教育の専門的機関としての公民館制度は、ほんらい対立的な関係にはないだろう。この点は、いわゆる公民館主事論争(14)についても言えることであって、制度的に社会教育専門職化が追究さなければならないことは当然であるが、その具体的な機能、役割について、公民館主事は学校教師などの教育専門職とむしろ大きく異なるところがあり、コミュニティ・ワーカーに求められる役割と類似性が大きいこともまた否定し得ないのではないか。
社会教育機関としての公民館の制度的確立は、フォーマルな教育機関としての学校や教員の教育専門職としての制度的位置づけが一つモデルになり得る。しかし制度としての社会教育機関論の主張が、機能としての、多様かつ複合的な、地域的かつ総合的な、いわばノン・フォーマルな教育活動やあるいはイン・フォーマルな生活的な学習を排除することにはならないだろう。
専門職集団としての公民館主事の体制を制度論的に求めることと、機能論的な観点から、ボランティアや参加スタッフあるいは講師や各種委員などとの多様なネットワークを立論していくこととは矛盾しないはずである。
公民館をめぐる論争史にみられる制度論と機能論の二つの潮流が、具体的課題を通して論議を深め、調和的に結合していく視点が必要なのではないか。
7,公民館学の形成に向けて
公民館50年を振りかえると、社会と地域の大きな転換期に、公民館の新たな方向が模索され、論議・論争が積極的に展開されてきたことが興味深い。いま21世紀に向けて新しい時代への胎動期に、公民館の公共的な条件整備水準は停滞し職員集団の体制も明らかに退潮傾向にある。NPO法成立に象徴されるように自立的なボランティ集団や協同的なネットワークの拡がりなど、いわゆる市民活動は活溌に動いている。この時点において公民館の新たな脱皮と次なる飛躍に向けて、いま新たな研究的論議・論争が期待される。
これまでの公民館研究の諸領域は、前述した学会30周年記念特別年報の総括にみられるように一応の体系をもっている。しかし大まかな傾向として、公民館の理念・思想史的研究、政策・法制・制度論的研究、主事・職員・専門職論研究等に傾斜がかかり、他方で、事業・経営論、方法・技術論、施設・設備論などの具体的な研究諸領域については相対的に蓄積が弱い。この問題は図書館学と対比してみると、かなり鮮明である。総じて基礎理論には強い?が、実践科学的な技術・方法の学としては弱いとも言える。今後の公民館学の形成に向けて克服すべき課題であろう。
あと一つ、公民館の国際比較研究を深めていく必要がある。公民館は特殊日本的な地域社会教育施設として、むしろその意味で閉鎖的な枠組のなかに公民館研究は閉じこめられてきた面がある。しかし視野を広げてみれば、民族と文化の違いを超え、地域=教育・学習・文化=施設として、公民館はある普遍的な共通性を有していのではないか。欧米的な比較だけではなく、とくに東アジア諸国でいま日本の公民館にたいする関心が増大している事実はきわめて示唆的である。本書では紙数の関係から、国際比較についての諸研究は割愛されたが、これからの大きな課題であろう。 ( 小林 文人 )
〔注〕
(1)日本社会教育学会「20年のあゆみ」1974、ほか年報・紀要など
(2)日本社会教育学会編『現代社会教育の創造ー社会教育研究30年の成果と課題』1988、東洋館
(3)横山宏・小林文人編『公民館史資料集成』1986、エイデル研究所
とくに三、四、五各部の「拡充」「展開」「改革構想」所収資料
(4)社会教育推進全国協議会編『社会教育ハンドブック』1979、総合労働研 究所、福尾武彦・千野陽一編『公民館入門』1979、草土文化、など
(5)1970年代の、東京都立立川(現在、多摩)社会教育会館セミナー記録、 東京都公民館連絡協議会「東京のこうみんかん」、社会教育推進全国協議 会三多摩支部「三多摩の社会教育」所収の記録、等
(6)松下圭一『社会教育の終焉』1986、筑摩書房
(7)高梨昌「生涯学習社会で何が、どう変わるか」『季刊臨教審のすべて』2 号、1986年4月臨増号、エイデル研究所、45頁
(8)鈴木健次郎『郷土自治建設と公民館』1950、地方自治問題研究所、林克 馬『公民館の体験と構想』1950、社会教育連合会、前掲(3)解説、一、二 部の収録資料、回想(日高幸男「公民館万能論の時代」)など
(9)前掲(3)、小林文人「公民館のあるべき姿と今日的指標・批判」『月刊社会教育』1967年12月号、
(10)小川利夫社会教育論集第六巻『公民館と社会教育実践ー地域 社会教育 論』1999、亜紀書房、第二章・都市化と公民館「現代化」論争
(11)宇佐川萬編『現代の公民館』1964、生活科学調査会、小川利夫他「公民 館の現代的性格」(1~4)、『月刊社会教育』1965年6~9月号、ほか
(12)小川利夫「公民館論の再構成」日本社会事業大学編『戦後日本の社会事 業』1967、勁草書房、小林文人「社会教育行政・近代化をめぐる問題」日 本社会教育学会・部会『都市化と社会教育』第2集、1968、所収論文
(13)社会教育推進全国協議会『公民館合理化をめぐる動向』1977、をはじめ とする行政改革・生涯学習政策の動向に関する社会教育推進全国協議会の 一連の資料、小林文人・藤岡貞彦編『生涯学習計画と社会教育の条件整備』 1989、エイデル研究所、小林「自治体生涯学習計画の動き」(1)(2)『季刊 教育法』84~85号、1991年、エイデル研究所、など
(14)大橋謙策「公民館主事の原点を問う」『月刊社会教育』1984年6月号、
佐藤進の反論(同8月号)、前掲(10)第三章第二節
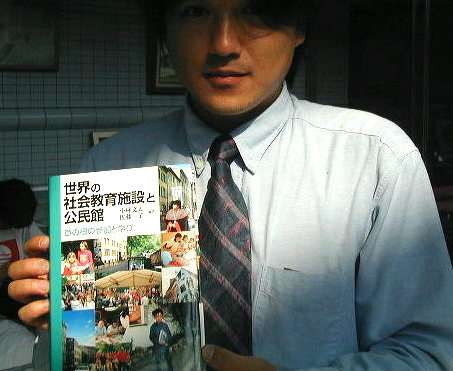
7,公民館の地域性研究と国際的視野からみる特質と課題
-小林文人・佐藤一子共編『世界の社会教育施設よ公民館-草の根の参加と学び』
(エイデル研究所、2001年)第Ⅱ部「公民館の地域史研究」序章・終章-
(1) 序章-日本の公民館、半世紀の歩みをどうみるか
―地域史にみる日本的特質―
1,はじめに―公民館の半世紀・森のひろがり
日本の公民館制度が、第二次大戦後・教育改革のなかで誕生して(「公民館の設置運営について」文部次官通牒、1946年)、すで50余年が経過している(巻末・年表参照)。本書所収の飯田市や川崎市などでは公民館(あるいは市民館)の「五十年史」が刊行され、また他の自治体でも「公民館史」が数多くまとめられる時代となった。人生の歩みにも似た歴史のドラマがさまざま記録されている。
半世紀を超える歴史は決して短いものではない。ここに至る歩みと蓄積を経て、公民館の総数は現在18,000館前後に達している(後掲・別表)。この数は義務教育機関である中学校数をはるかに凌駕し、小学校数との比較でも10校あたり7.5館の水準にまで普及をみた。国際的にみても、類似の地域学習文化施設としては、少なくとも統計的には他に例をみない高い普及水準と言えよう。
これらの公立公民館に加えて、地域の住民自治組織の性格をもつ「集落公民館」(あるいは「自治公民館」、本書所収の地域史では「分館」という場合もある、全国約5万館以上と推定)(1)の拡がりもまた無視できない。なかには形骸化したものも含まれるが、沖縄などに典型的に見られるように、集落レベルでまさに草の根の公民館活動が活発に展開してきている。これらもまた日本の公民館史の一側面であり、その実像を把握しておく必要がある。
公民館の構想は、第二次大戦後の民主化過程と教育改革のなかで登場し、戦後史の時代状況のなかで形成されてきた。それは一面で、戦前的な古い思想からも無縁ではなかったが、その基本理念は明らかに戦後民主主義による新しい創造であった(2)。しかし、公民館の誕生は、戦後初期の混乱期における苦難のスタートであった。公民館の制度が産声をあげた当時、その初期構想を提起した寺中作雄の表現をもってすれば、「この有様を荒涼と言うのであろうか、…目に映る状景は赤黒く焼けただれた一面の焦土、…焼トタンの向うに白雲の峰が湧き、崩れ壁のくぼみに夏草の花がそよいでいる」(同『公民館の建設』1946年)という風景であった。それだけに公民館を拠点に、荒れた郷土を復興しようという呼びかけは全国的に広く浸透していったのであろう。
その3年後に、公民館に法的基礎を与える社会教育法(1949年)が成立する。同じく寺中は「今日生まれた社会教育法は全くまだ骨組もかたまらない腺病質の、見るからにひ弱い初生児の格好で生まれたのであるから、その成長が危ぶまれる」(同『社会教育法の解説』序、1949年)と憂慮している。公民館はまさに戦後荒廃のなかのゼロからのスタートであり、法制的基盤はまことに脆弱であり、もちろん財政的にもまったく不備な条件であった。しかし公民館が果たすべき独自の役割についての時代的な要請と熱い期待はなみなみならぬものがあったのである。
それからの半世紀。産み落とされた小さな赤ん坊は、厳しい道を歩みながら、今日までに大きく育ち、歳月を重ねていま五十路の坂を歩いている。当初は、たどたどしい歩みにすぎなかったものが、雑草のたくましさをもって成長し、樹木となり、群落を形成し、いま広大な森のひろがりをもつに至った。統計的に義務教育機関とならぶ水準にあるという点からすれば、そう言えるだろう。
公民館の森に分け入って、その形成過程と内面の実相を調べてみると、どんな風景が見えてくるのだろう。森のひろがりのなかには、さまざまの表情があり、格差もあるだろう。活気あふれる樹木群がある一方で、なかには精気を失った枯木のような公民館があるのかも知れない。地域的には未設置の空白地もみられる。
公民館の制度史・発達史の“森”を全体的に描写する試みはこれまでにも取り組まれてきた。本編ではそれに重ねて、地域史の視点から公民館の歩みと特徴を解明してみようとする。個別の地域の歩みを細かく掘りさげることによって、何が見えてくるか。歴史の真実は細部に宿るという。公民館史の全体的な記述からは窺いしれない地域的な事実を通してわれわれは何を発見し得るか。地域の視点から“森”をとらえようという試みである。
上述の国際比較の作業にこの地域史的な探求を加えて、つまり比較的かつ歴史的に、日本の公民館の特質と可能性を立体的に明らかにしていきたいと考えている。
2,公民館の地域史―多様な展開
全国各地の公民館は、それぞれの地域史をもっている。そのすべてをここに取りあげることはもちろん出来ないが、典型的なものを抽出して、可能な限りでの地域的発達史を収録しようとというのが本編の試みである。しかし当然いくつもの難問があった。いったい「典型」をどう画くか。「地域」の範囲をどう考えるか。また時代をどう区分するか、など。しかも与えられた紙数には限度がある。
われわれは未だ日本の公民館発達史における「典型」理論を構築し得ていない。しかし、その課題にせまる視座をもちつつ、さしあたり次のような手順で収録すべき地域事例を選び出すしてみた。(1)全国的な拡がりを確保するために、北海道から九州までの主要ブロックを単位として選ぶ。とくに戦後27年間にわたってアメリカ占領下にあった沖縄の特異な事例を重視する。(2)単位市町村の公民館史を基本とするが、必要に応じて市町村をこえる地区(たとえば埼玉・入間、東京・三多摩など)の拡がりも取りあげる。(3)時期的には戦後初期からの歴史をもち、しかも半世紀を経て現在も(相対的に)活発な活動を展開している公民館史に注目する。(4)それぞれの事例の典型的な特徴に焦点をあてる。(5)同時に公民館の主要な歩みについて、充分な視野の拡がりをもって包括的かつ実証的に地域史をえがく。
各公民館史の記述は、したがって地域個性的であり、取りあげる内容と方法にも地域的な差異があり精粗もあり得る。結果として選び出した地域史は13事例となったが(目次参照)、しかし当初予定した地域(15事例)をすべて収録できたわけでもなく、その意味では事例の「典型」性について課題を残していることは言うまでもない。
まず、本書に収録された13事例の公民館発達史を見ていくと、なによりも地域的に実に多様な展開をたどってきていることに驚かされる。言うまでもなく公民館制度の発端は、同じ構想(公民館の初期構想、「寺中」構想)に根ざし、また同一の法制(社会教育法)に基礎をおいているにもかかわらず、さまざまの発達史が織りなされてきている。公民館それぞれの個性的な歩みと実像が地域的に形づくられてきた。
公民館地域史の多様性について、はじめに特徴的な点をいつくかあげてみる。
1)この半世紀、公民館は全国的に広く普及し定着してきたというものの、自治体によっては公民館制度それ自体が成立しなかったところも存在する。1997年文部統計では、288自治体(8.2%)がまったく公民館を設置していない。概して大都市部に空白が多く、練馬区を除く東京二三区や横浜あるいは大阪や京都など、旧六大都市では公民館制度の定着は弱い。
欧米近代の成人教育制度がむしろ都市部から胎動したのに対し、日本の公民館制度はなぜ大都市部で定着してこなかったのか。日本近代史における社会的市民的運動の未成熟、公民館初期構想のいわゆる「農村的性格」、その後の「都市型公民館」への脱皮の歩み等を含めて、この点の分析は重要である。本書では、大都市部の公民館「非定着」事例は取り上げていないが、大都市部の事例として自治体独自の「市民館」制度を形成してきた川崎市、また当初から「文化活動を軸とした都市型公民館」に挑戦してきた貝塚市からの報告を収録している。
2)各自治体の公民館制度・体制の形成過程がきわめて多様である。単独館か地域配置の体制か、複数館の場合、本館―地区館あるいは校区レベルの公民館設置の状況、上述した集落公民館(分館)の位置づけなど、市町村ごとの多様な特徴がみられる。(3)あわせて行政機構内部の公民館の格づけ、図書館・博物館や学校など教育法制上では同じ「教育機関」とされている諸施設との相互関係など、決して一様ではない。また「組織公民館」(相模原市)、「校区公民館」(大分市)、「学区公民館」(横須賀市、(4)ただし本書には収録していない)等の独自の呼称をもった公民館の地域史もあった。
さらに最近の自治体行財政「改革」が加速するなかで、第三セクター等による公民館の「委託」形態も現れてきている。広島市では「ひとまちネットワーク」を設立し(1996年)、ここに教育委員会所管の公民館65館の管理運営が委託されている。(5)このような「民間委託」形態は、すでに早く北九州市「教育文化事業団」への大規模な公民館委託(1976年)から始まっているが、公的セクター見直し論とともに今後増える傾向にあるだろう。この「民間委託」の実相はいかなるものか。また欧米の民衆運動的な背景をもつ成人教育機関の委託や、たとえばアソシアシオン(仏)や社会文化運動(独)等の展開とその中での施設づくりと比較して、どのような異同をもつのか、吟味を要するところである。
3)地域における公民館設置の年代は半世紀余の経過のなかで多様である。言うまでもなく現在設置されている公民館がすべて半世紀の歴史をもつわけではない。本書収録の地域史では初期公民館からの歩みが比較的多く記述されているが、全般的には初期からの蓄積をもつ公民館はむしろ少数であって、その後の1950~60年代の、また公民館の発足が遅れた都市部・近郊部ではむしろ1970年代以降の設置が多い。本書収録の東京三多摩地域や埼玉入間地域の事例はその典型的な歩みである。重要なことは設立された時代状況によって、公民館が依って立つ基本理念・思想は一様でなく、当然ながら初期公民館構想からの変容・脱皮と、その後の新しい展開が見られるところに注目しておく必要がある。
なかでも特異な事例は上述した戦後沖縄の公民館史である。沖縄は1945年から1972年までアメリカ占領下にあり、その極東戦略と文化政策に拘束されるかたちで社会教育・文化政策は推移してきた。占領下にあってはアメリカ直営の大型公民館とも言うべき「琉米文化会館」と沖縄土着の集落自治的な「字(あざ)公民館」という二重の構図があった。本土型の公立公民館が読谷村等に設置され始めるのは、ようやく本土復帰前後(1970年、読谷村)のことである。その後の沖縄の公民館の歩みは、アメリカ占領下に胚胎した集落公民館と復帰後の公立中央公民館の複合的な展開という特徴をもっている。(6)
4)公民館の施設・設備および職員体制等の具体的な条件整備がきわめて多様である。本書に収録された各地の公民館の展開過程をみても、同一水準の公民館はないと言って過言ではない。一つには、公民館の条件整備に関する国の基準法制(文部省「公民館の設置及び運営に関する基準」1959年)が充分に整備されず、また拘束性が弱いこと、二つには、自治体社会教育計画や公民館に関わる地域住民運動による地域的な要因が多様に作用してきたこと、三つには、具体的に自治体行政施策や財政条件によって公民館の条件整備は流動的に左右されてきたこと、による。これを自治体ごとに見れば、それぞれ固有の経過と条件のなかで公民館の条件整備は歴史的に蓄積され、ときに停滞しつつあるいは発展しつつ、それらの過程を経て多様な実態が形成されてきたという点で共通している。そして反面、公民館の条件整備は抜きがたい地域格差を内包することとなり、それが固定化してきた歴史でもあった。
5)公民館とそれに関わる住民の関係性において多様な歩みが見られた。公民館の初期構想においては、公民館は「公民の館」であり、住民自身による「われわれの為の、われわれの力による、われわれの文化施設」であって、それこそが「公民館の本質」であるとされた。具体的に公民館運営組織として住民の直接選挙を原則とする「公民館委員会」制度や、住民主体による専門部組織(教養部、図書部、産業部、集会部等)の編成が唱導された(寺中『公民館の建設』前掲)。周知のように社会教育法では、この発想を継承して公民館運営審議会制度が法定化され、また住民参加による各種事業・活動が展開されてきた。
しかし各地の公民館の地域史を見ると、実際の公民館と住民の関係性は法制理念とかけ離れた場合が少なくなかった。その後の近代化過程と施設的な条件整備にともなって住民の直接的な参加は後退するという傾向も見られた。もちろんそれだけではない。「教育機関」としての公民館の上から下への流れが支配的になる一方で、住民の側からの主体的な参画や活動が積極的に取り組まれ、さらには公民館そのものを住民運動によって創出していく地域も、とくに1970年代・都市近郊部において、少なからず見られたのである。
3,公民館構想の地域的な形成と発展
公民館の地域史にみるさまざまな展開とその“多様性”にやや執着したのは、次のような理由からである。
日本の公民館にたいする一般的理解は、国際比較からみて、国家法制に基礎をおき公設公営を基本型とする固定的画一的な形態、ということであろう。同じく自治体レベルでも条例・規則上に規定され、その条文も自治分権的というより相似形式の内容が多く、名称、組織、事業等きわめて類似性がたかい。公民館は、全国的な拡がりをもちながら、むしろ多様性に欠けるという認識が少なくないのである。
社会教育法は民法第34条による法人立公民館の設置の規定を用意している(同法第21条2項)。しかしその数は全国でわずか8館に過ぎず、その圧倒的部分が市町村が設置する公立公民館である。また「公民館に類似する施設は何人もこれを設置することができる」(同第42条1項)の条項にしても、集落を基盤とするいわゆる集落・自治公民館の形態を除いて、それ以外の多様な(たとえばNPO的団体による)設置を生み出す規定としては機能していない、というのが現実の姿である。
このような公民館の設立形態における制度的な固定性、公民館イメージの画一性については、たしかに否定し得ないものがある。ここであらためて日本の公民館の制度について、その主要な特徴を整理しておこう。
(1)国家実定法に基づく法制上の教育機関(社会教育法、地方教育行政の組織及び運営に
関する法律等)
(2)条例に基づく地方自治体・市町村による設置(社会教育法第21条、第24条等)
(3)市町村内の一定区域を対象とする地域施設(社会教育法第20条、公民館の設置及び運営
に関する基準第2条等)
(4)実際生活に即する教育、学術、文化に関する総合的な機能(社会教育法第20条、第22条等)
(5)館長諮問機関としての公民館運営審議会(社会教育法第29条等)
(6)職員規定とくに専門職規定の法的未整備(社会教育法第27条、公民館の設置及び運営に関
する基準第5条等、教育公務員特例法第2条等)
(7)財政補助、施設・設備等に関する基準の不備(社会教育法第35条、公民館の設置及び運営
に関する基準第5条等)
(8)公民館に類似する施設設置の自由(社会教育法第42条)
基本的に国家・自治体法制に基礎をおく制度的な固定性は明確である。しかし他方では、このような法制に依拠することによって、国際的にみて類例のない高い水準の普及定着を達成してきた、そのこともまた否定し得ない。法制上に位置づくことによる制度的な画一性と普及性、この両側面を前提としつつ、しかし実際の公民館の発達史を地域史的にたどってみると、同一制度のなかで実に多様な展開がみられる事実をも確かめておきたいのである。
本書に収録した事例から、公民館の地域史がそれぞれ個別の条件のなかでさまざまの定着過程をたどっていること、そこには地域個性的な公民館づくりが展開してきたこと、さらには(後述するように)不備な状況を克服していく運動もまた地域的に果敢に取り組まれてきたこと、を知ることが出来る。
まず公民館「構想」について、その地域的な展開について見ておこう。公民館構想という場合、まずその初期構想としての前記・寺中構想が想起される。寺中構想はたしかに公民館の原点であり、初心である。しかしながら、その後に設置されてきた公民館がすべて寺中等による初期構想を忠実に継承してきたかといえば、決してそうではない。むしろ公民館構想自体が地域的かつ時代的に変容し発展してきている。その多様性こそが日本の公民館制度の重要な特徴でもある。
公民館の初期構想では「多方面の機能をもった文化施設」であって、社会教育機関、社交娯楽機関、自治振興機関、産業振興機関、青年養成機関、その他地域的に必要な機能、それらの「総合された町村振興の中心機関」とされた(前掲、寺中『公民館の建設』)。せまく社会教育機関に閉じこもらない総合的な機能論である。主に「町村」つまり農村に向けての地域振興機関としての構想が提示された。本書では、その地域的な事例として、たとえば「村勢振興委員会」による福岡県庄内町公民館や、当時の「リアルな生活要求」に取り組んだ岐阜県苗木町公民館等の事例が収録されている。
この農村地域性・総合性・地域振興型の初期公民館が、まず第一の主要な流れとなっていく。公民館発達史のいわば源流と言ってよい。しかし1949年社会教育法成立以降になると、社会教育機関としての公民館の考え方が次第に明確になってくる。併行して教育委員会制度の施行があり、教育行政の枠組みに位置づく「教育機関」としての公民館論が意識されるようになる。他方で都市部においても、都市的地域性に立脚した公民館活動が各地で胎動していく。1950年代には明らかに都市型公民館の模索が始まっている。先述したように、文化活動を軸とした貝塚市公民館、映画と集会そして成人学校を開設した川崎市公民館、さらに本書には収録していないが、多彩な定期講座と各種文化事業で注目を集めた旧八幡市公民館(北九州市)、国際的視野からの教養講座と原水爆禁止署名運動につながる読書会等を組織した東京・杉並区公民館、(7)あるいは市民大学構想を積極的に提示してきた国立市公民館等の事例が、それぞれ都市型公民館への展望を示すものとして注目されてきた。
これらには農民啓蒙型の初期公民館とは異なる都市市民の学習・文化活動への新しい志向がみられる。たとえば市民の国際的視野と社会科学的教養の育成、そして平和運動への取り組みにも関わった杉並公民館(館長・安井郁)「安井構想」は、明らかに初期公民館「寺中構想」とは異なるところがあった。
公民館のあり方をめぐる構想は、時代の変化とともに地域的に新しく形成され創造されてきた歴史であった。公民館の地域史はこのことを語りかけている。
4,公民館発達史の多元的な流れ
初期の農村型公民館を第一の潮流と考えれば、市民大学構想に象徴されるような都市型公民館への流れ、公民館近代化・教育機関化への動きは第二の潮流ということができる。
その社会的背景としては、言うまでもなく1960年代の経済高度成長とそれに伴う激しい農村の構造変化、都市化・工業化・過密化など都市地域への変貌過程があった。
この時代の急激な地域変貌は、当然に初期公民館のあり方、それがめざす地域づくり論、総合的機能論を問い直すものであった。同時に総合的機能論の反面としての「あいまい性」からの脱皮が課題とされた。また貧弱な条件整備の改善、職員体制の拡充と職員論の深化、とくに専門職化に向けての課題提起など、総じて近代的「教育機関」論の構築が求められたのである。
1960年代の地域変貌とそれを背景とする公民館近代化の流れのなかで、新しい公民館像や職員像の探求が重ねられてきた。たとえば長野県飯田・下伊那郡主事会による「公民館主事の性格と役割」(1965年、下伊那テーゼ)、全国公民館連合会「公民館のあるべき姿と今日的指標」(1967年)等の努力があり、さらに1970年代に入ると、東京三多摩における「新しい公民館像をめざして」(三多摩テーゼ)の構想へと展開していくことなる。
ところで、このような1970年代に至る公民館近代化、(8)都市型公民館への脱皮の流れが、公民館発達史の新しい潮流となったことは疑いないが、しかし日本のすべての公民館が一様に同じような道程をたどったわけではない。公民館の地域史は一元的ではなく、いわば多元的な脱皮の動きを示している。農村部の公民館は農村それ自体の変貌過程に苦悶しつつ自己脱皮の努力を重ねる必要があったし、都市化過程に投げ込まれた公民館としては、都市化地域としての新しい地域創造への取り組みが求められてきた。
そういう意味では、地域振興・地域づくりをめざす公民館の構想自体が否定され、いわゆる脱地域的な都市型公民館へ一面的に転換していったと解すべきではないだろう。むしろ地域それぞれの変貌過程に対応しつつ、新しい地域社会教育機関としての公民館に脱皮していく動きそれ自体に着目しておく必要がある。公民館にとって「変貌する地域」との格闘はいずれの地域でも共通の課題であり、「地域」への取り組みは、初期公民館から現段階の公民館を貫く永続的なテーマとなってきた。
本書収録の公民館地域史のなかでは、たとえば農山村部の厳しい自然環境、主産業である農業の衰退、それに連動する過疎化・高齢化の進行という「三重苦」と闘いつづけてきた岩手県沢内村「地域づくりと公民館」や、同じく過疎化にあえぎながら地域の生産課題、生活課題に取り組んできた北海道置戸町「地域社会発展と公民館」の歩みなどは、その典型的な事例と言えよう。類型的に都市型公民館への歩みをたどったわけではない。
地域に真正面から関わる公民館の取り組みはさまざまである。地域の状況に対応した地域個性的な公民館実践の軌跡が多様にみられる。本書収録の地域史から、興味深い特徴的な動きを5事例ほど拾いあげてみる。
1)定型的(フォーマル)な学校形態の事業開設。たとえば「公民館に付設して開設された定時制の貝塚女子高等学院」、あるいは旧青年学校廃止後の在村勤労青年にたいする「青年学園」「補習学校」等の学校教育型事業をおこなった下伊那郡下の公民館、同じく「青年講座」「青年学級」開設に取り組んできた十日町市公民館の事例など。
2)地場産業の活性化と生産教育の推進。地域の森林資源を見直す講座・研究会や、施設(地域産業開発センター、森林工芸館、共同工房等)づくりを通して、工芸品「白い器・オケクラフト」開発に参画してきた北海道置戸町公民館の事例。関連分野での「仕事づくり」に波及効果があり、現在、クラフト製作に従事している職人は15名を数えるという。
3)文化協同運動と市民ネットワークを支える公民館。全国的規模での人形劇運動(カーニバル、フェスティバル)と市民実行委員会の拠点的役割を担い、底辺からこれを支えてきた飯田市公民館と主事集団の事例。
4)民族差別に取り組む川崎「ふれあい館」の活動。公設公営の川崎「市民館」に併行して、在日韓国・朝鮮人を主体とする社会福祉法人「青丘社」に運営委託された公設民営の公民館的施設「ふれあい館」の事例。近年の外国籍住民を対象とする識字実践事業とともに、民族共生を促進する施設のあり方として注目される。
5)住民自治組織の性格をもつ集落公民館の機能。とくに沖縄ではアメリカ占領下において公立公民館の設置が遅れ、集落自治公民館を主体とする独自の活動が自生的に胎動し定着してきた。復帰後すでに四半世紀を経過した現在でも、いわば沖縄型・集落公民館として独自の展開をみせている。本書ではその典型としての読谷村の事例が収録されている。
これら事例の詳細はそれぞれの報告本文を参照していただきたい。地場産業への取り組みや集落自治活動の事例など、初期公民館の総合的な機能論を母体としている側面もみられる。いずれも時代的な状況と地域的課題に向き合って、諸条件と格闘しながらの公民館の可能性の探求である。地域振興・農村型公民館から近代的都市型公民館への潮流という類型的な流れに一元化されるのではなく、地域独自の挑戦と実践の試みが分岐し発展し、全体としての公民館発達史の多元的な流れを創り出してきていることに注目しておきたい。
公民館地域史の特徴的な事例はこれにとどまらないが、仮にここに注目した五つのポイント、すなわちフォーマルな学校型事業、地場産業への取り組み、文化協同運動支援、多民族共生、集落自治活動等の視点は、世界の類似地域施設や社会文化センターなどと対話していく上での共通のキーワードとなるのではないか。
5,公民館をめぐる運動的な展開
さて公民館と市民・住民の運動、総じて民衆運動との関係についてどのように捉えておけばいいのだろう。一般的に公民館は、官から民へ「施し設け」られてきた施設であって、民衆レベルの下からの運動によって創り出される歴史をもっていない、その意味で民衆運動的基盤は稀薄である、とするのが大方の理解であろう。しかし戦後の公民館発達史をたどっていくと、設置主体はたしかに市町村(社会教育法第22条)であるが、現実の展開過程のなかで市民・住民の参加と運動が多様に織りなされてきた。公民館はむしろ国家・自治体行政の枠組みと下からの諸運動のはざまに位置して、実態としては複雑な対応を迫られてきた場合が多かった。全く行政機構に従属するポジションに安住する場合は別として、民衆の要求や運動との関係において一定の役割を果たそうとする場合、公民館は矛盾の接点としてときに呻吟し苦悩する場面も少なくなかった。公民館地域史の事例は、この点で興味深い事実を多く含んでいる。
国際比較の視点で見た場合、欧米の成人教育・継続教育の歴史が主要には近代在野の民衆教育運動のなかから胚胎し、いわば非国家的伝統を形成しつつ運動的基盤をもって形成されてきたのに対し、日本の社会教育は国家装置として上から制度化され、公民館制度もまた国家法制上に位置づけれることによって(広範な制度普及を実現しつつ)民衆運動からは基本的に遊離しあるいはその基盤を欠落してきたと考えられている。(9)
たしかに、概括的にはこのような把握が可能であろう。このことを前提としながらも、しかし地域史の事例からは、公民館をめぐって逆に多くの運動的な展開がみられることも見過ごしてはならない。少なくとも次の3つの流れを指摘しておく必要があろう。
第1は、初期公民館の創設時にみられる青年層を中心とする住民側の対応と運動的な取り組みについてである。もちろん官設的な設置事例も少なくないのであるが、本書に収録された初期公民館の事例には、なんらかのかたちで住民による公民館設立にかかわる積極的な動きが記録されている。たとえば、青年読書会の動き(北海道置戸)、地域名望家層と青年団運動(入間地域、相模原、岐阜県苗木)、青年、婦人、文化団体による設置要望(貝塚)、青年団を中心とする全村的な運動(福岡県庄内)など。この段階ではとくに青年層のイニシャチブが特徴的である。
第2は、とくに1960年代から70年代における上述の都市型公民館に向けてのさまざまの住民運動の展開である。施設・設備等の条件整備改善をめざす取り組み、職員体制の拡充と専門職化への志向(次項)、学級・講座や事業編成における住民参加の挑戦、公民館づくりの住民運動、社会教育・公民館にかかわる日常的な住民活動(考える会、市民の会等)など、多岐にわたる運動がみられた。(10)本書では、東京三多摩、埼玉県入間、神奈川県相模原、川崎、貝塚、長野県飯田等の報告のなかにそれらの片鱗が記録されている。とくに住民運動による公民館の設立運動、あるいは増改築運動(東京都東大和市「公民館を求めた青年たち」、川崎市「住民運動と市民館建設」など)の拡がりはこの時期の特徴と言えよう。
第3は、1980年代からとくに1990年代以降にみられる市民活動それ自体にみられる積極的な学習・文化運動の拡がり、非営利の市民ネットワーク活動、それらを軸とする地域創造の運動的な取り組みであろう。この点についての地域事例は、公民館地域史を主要なテーマとしている本書の直接的な課題ではないが、入間地域、貝塚、置戸等の報告のなかに展望として触れられている。さらに今世紀の新しい潮流として、今後の公民館のあり方を考える上で重要な意味をもつ動向と考えられる。
しかし、以上のような公民館をめぐる運動的な取り組みは、欧米諸国の歴史に見られる労働組合運動、協同組合運動や、さらには民衆教育普及運動、広範な市民文化運動等との重層的な関係を生み出すには至っていない。たとえば社会教育法(旧)第30条公民館運営審議会の委員委嘱条項のなかに「労働」が含まれていたが、現実の公民館実践と労働組合運動が出会う事例はほとんどなかったと言ってよい。公民館をめぐる運動的な展開は、主として地域レベルの地縁的な集団や住民運動とのかかわりに終始してきたというのが実態である。いま新しい課題として、特定非営利活動促進法(NPO法)制定(1998年3月)を契機とする公民館と各種市民活動との連携・協同の方向が模索されているという段階であろう。
さしあたり公民館は「地域」の市民・住民諸運動と積極的に出会うことによって、地域自治的な実質を創りあげていく可能性をもつ。民間諸運動・活動が追求し蓄積してきたものが、公民館の公的体制のなかに運動的に取り入れられ、具体化されてきた側面もまた興味深いものがある。住民要求・運動に基礎をおく公民館の自治的な制度化の試みである。公民館のこれまでの実践事例としては、たとえば公民館運営審議会委員の準公選(保谷市等)、公民館保育室制度の創設(国立市等)、障害者青年学級の開設(町田市等)、公民館職員の専門職化(旧田無市等)、住民主体の公民館専門部組織と町内自治公民館の助成(松本市)等はまさに自治体独自の制度化であった(いづれも本書に収録されず)。このような取り組みが自治体として固有の公民館制度を自治的に創出していくことになる。
6,公民館職員の拡充と専門職化・職能集団形成の課題
日本で公民館制度が創設されて以来、今日まで一貫して問われてきた課題は職員問題であった。とくに公民館主事の集団化と専門職化は積年の課題となってきた。すでに初期公民館の段階から主事の身分保障と専門職位置づけが要望されてきたが、社会教育法が制定されてもこの問題の改善に結びつかず、公民館関係者による抜本的な公民館単行法策定の運動が展開される経過もあった(1952~58年)。法制化運動のなかで悲願として盛り込まれたのは、公民館の「市町村による義務設置」とならんで「職員の必置性と専門職化」である。しかし周知のように単行法策定は実現しなかった。結果的には関係者の見果てぬ夢と終わり、1959年の社会教育法大改正と公民館設置運営に関する「基準」に収斂するところ(近畿公民館主事会は「パンを求めて石を与えられた」と批判)となり、(11)職員制度改善の課題は法制的には未整備のまま今日に至っている。
現実に公民館の職員体制がきわめて不備であることは、統計的に一目瞭然である。公民館の施設数にたいする職員数の比率、職員集団の構成、その実態をみると、公民館は果たして「教育機関」の実質を備えているかどうかきわめて疑わしい。総数1万7,819館にのぼる公民館数にたいして、職員総数は5万2,324人であるが、その4分の3は兼任・非常勤の職員であって、専任職員は1万3,751人(26.3%)、1館あたりの職員数は(総数で平均2.94人であるが)専任職員に限ればわずか0.77人にすぎない。この数字は公民館本館に限定すると少し改善されるが、それでも1館あたり1名強の配置にとどまる。「指導系職員」と目される公民館主事の比率はそのうちの54.6%という水準である(文部省「社会教育調査報告書」1998年、別表参照)。すなわち統計的に公民館本館といえども1館に専任職員はわずか1名強しか配置されず、半数ちかくの公民館は専門的職員をもたない計算になる。地域的にはもちろん格差を含むが、この平均値は公民館の人的条件とくに専門職体制がいかに低劣な水準にあるかを示している。
日本の公民館は施設の量的配置こそ高い水準にあるが、その質的人的体制はこの統計から明らかなように、きわめて貧しいのである。多くの公民館がこの貧弱な体制にこれまで呻吟してきた。活動が活発な公民館であればあるほど、その苦悩は深いものがあった。それだけに自治体による改善、改革の努力がさまざま取り組まれてきた。本書収録の地域史から、注目すべき事例をいくつか拾いあげておこう。
一つは、自治体における公民館職員の専門職制度化の試みである。貝塚市では厳しい財政事情のなか公民館専門職員配置を「教育委員会要綱」として自治体独自に制度化し(1985年)、それに基づく職員採用をおこなっている。埼玉県入間地区の報告によれば、上福岡市、富士見市、鶴ヶ島市では自治体条例・規則をもって公民館主事の教育専門職員としての位置づけを定めている。とくに鶴ヶ島市では大規模な公民館職員の異動問題があり、職員側は公平委員会に提訴するかたちでこれを争い(不当配転闘争)、公民館職員の専門制を行政内部に位置づけさせる結果をもたらしている(1989年)。これらは国家法制の不備を補う自治体法制の試みであり、また職員集団と住民運動の成果という側面も合わせもっている。文字通り自治体における公民館主事専門職化の典型的な事例である。
二つには、自治体レベル公民館職員集団の組織化の努力がみられる。概して公民館職員の職場は単独ないし少数体制の場合が多く、また労働条件も厳しいものがある。それだけに自治体内各公民館を横につなぐ「主事会」(飯田市)など職員集団の自覚的組織化によって、相互研修、情報交流、諸問題の克服、連帯感の形成等がはかられてきた。同じような職員集団化の事例として、相模原市、貝塚市、埼玉県入間地区からの報告が興味深い。
三つには、自治体をこえる公民館職員集団の形成と日本社会教育学会や社会教育運動体等への参加による研修・研究の取り組みである。具体的には近畿公民館主事会あるいは阪南主事会(貝塚)、飯田・下伊那公民館主事会(飯田)、入間郡市公民館連絡協議会(入間地域)、東京都(三多摩)公民館連絡協議会等の活動が注目される。職場内・自治体内そして自治体をこえる職員集団の組織化が、公民館職員としての専門的力量と連帯意識の形成の上で重要な役割を果たしてきた。
このような地域をこえ全国的な拡がりをもつ職員集団への参加は、社会教育・公民館職員の専門職化運動として重要であり、同時に専門職相互のいわゆる「職能集団」形成への展望を含んでいると言えよう。しかし他方では、公民館職員にたいする自治体人事管理の強化や、行政改革による職員体制縮小の動きがあり、公民館主事の専門職化もその職能集団化への展望も、いまなお道遠しの感がある。日本の公民館は五十年の年輪を重ねながら、専門的職員集団の形成とその社会的認知という点では必ずしも成功せず、残念ながらなお多くの課題を残していると言わざるを得ない。
7,公民館の内面的発展のエネルギー ―まとめとして
全国各地の公民館の地域史を精査していけば、さらに多様な個別事例がさまざま展開されてきているに違いない。そのような事例に細かく留意しながら、いわば地域の視点から公民館の発達史をみていくと、これまでの一般的、概括的な認識だけでは捉えきれない新たな歩みも見えてくるだろうし、瑣末に見える実践に新しい光をあてることも可能になってくるだろう。そのような地域史的な事実を基礎に全体的な公民館発達史を再構成していく作業があらためて求められているように思われる。
上述してきたように、本論ではこれまでの日本の公民館発達史の類型的な把握に対して、地域史をベースにしたいくつかの視点を提起してみた。すなわち、国家法制に基づく画一的な公民館史に対する多様な地域発達史論、公民館構想の時代的地域的な変容・発展論、農村型から都市型へといった一元的な把握から多元的な分岐論、運動的背景をもたない公設公営施設における参加・運動論、低劣な職員体制に抗する職員集団の組織化と自治体レベルの専門職化論、などである。もちろんここで公民館史にかかわるこれまでの全体的・一般的な理解をすべて否定するものではない。むしろそれらを前提とした上での問題提起である。地域史的な視点をもつことによって、日本の公民館の歴史的な展開過程をさらに精緻かつ多彩に画き出すことが出来るのではないかと考えるのである。
各地から本書に寄せられた公民館地域史を比較分析する作業を通して、あらためて次のことを教えられた。
1)公民館の制度史・発達史についての既存の理論枠からでなく、地域の公民館の歩みに関わる具体的な事実を重視し、事実に則して分析をすすめること。2)公民館の全体史につながる共通部分より、むしろ地域独自の個性的な展開を掘り起こすこと。3)公民館に関する国家法制と並んで、地域・自治体の法制化、自治的制度化の側面に注目すること。4)そこに潜在的かつ顕在的に動いている模索・脱皮・変革・発展の内面的エネルギーを発見すること。そして当然のことであるが、5)それぞれの自治体と公民館において、自らの地域史を記述する作業の重要性、などである。
公民館の地域史は、その内容において、またそれを綴るエネルギーにおいて、公民館自体の自己変革と内面的発展の可能性を示唆するところが少なくない。
いま公民館が大きな転換期にあり、新しい時代状況のなかで独自の変革と発展を期待されていることは誰しも疑いないところであろう。その際、時代の波に埋没し、上からの政策に翻弄され、主体性を失って放浪していくか、あるいは地域に立脚し市民の期待に応えて自らの脱皮をめざすか、主体的に変革を志向し自己発展をとげる方向でチャレンジしていくか、大きな分岐点に立っている。後者の、公民館の内なる自己変革のエネルギーとその可能性については、これまで述べてきた公民館地域史の記述のなかから多くのことを読み取ることができるように思われる。
公民館をめぐる状況の新しい要因としては、1980年代に始動し1990年代に拡大する生涯学習政策の展開がやはり大きい。我が国の生涯学習施策は、国家主導で打ち出され、しかも新自由主義による行政改革・公的セクター見直し路線と連動するという不幸な出発であった。単純な評価は避けなければならないが、公民館に関しては大きな展開をもたらす要因にはなっていない。生涯学習振興整備法(1990年)との関係についても、この法の「振興」「整備」自体が公民館にとってはほとんど実質的な意味をもたないものであった。むしろ公民館に関して生涯学習政策は概して冷淡であり、論者によっては「公民館の歴史的役割は終わった」(12)とする見解さえ喧伝される経過があった。本来は地域における生涯学習機関としての公民館こそ中核的に位置づけられるべきであったし、事実、公民館は独自の役割を担う大きな可能性を秘めているのである。
しかしこの10年、生涯学習振興策が契機となって、これまでにない「おとなの学び」や市民活動の新たな通路が拡大されてきたことも確かである。すなわち、民間教育文化産業はもちろん、大学開放、放送大学、関連行政事業、これに加えて今後は職業能力開発の拡大が予想される。さらにNPO等の市民ネットワークによる社会参加の志向をもったさまざまな学習・文化活動・市民活動が胎動しつつある。
このような動きのなかで、地域社会教育施設としての公民館がどのように独自性を主張し得るか、協力連携のネットワークのなかでいかなる役割を果たし得るか、が問われることになる。これまでの蓄積を活かしつつ、同時に自らの新たな脱皮と自己変革が期待されるのである。
公民館のこれまでの歩み、とくにその地域発達史は、多くの課題をかかえながら、この点についての実践的蓄積とその内面的なエネルギーを豊かに内包している。
【注】
(1)小林文人『これからの公民館』国土社、1999年、p40、
関連して小林 ML「公民館の風」 1999年10月、№3~5。
(2)横山宏・小林文人編『公民館史資料集成』エイデル研究所、1986年、第1部および特論。
(3)上野景三「公民館の地域定着過程」日本社会教育学会編『現代公民館の創造』東洋館、
1999年(以下『創造』という)。
(4)横須賀市公民館活動連絡協議会「学区公民館の分析と提言」(学区公民館発足25周年
記念、1986年)。
(5)小池源吾「社会教育施設の第三セクター化と公民館」、前掲『創造』所収。
(6)小林文人・平良研一編『民衆と社会教育ー戦後沖縄社会教育史研究』エイデル研究所、
1988年。
(7)前掲(2)『公民館史資料集成』第4部、小林「杉並区立公民館の歴史を掘る」東京都立多摩
社会教育会館『戦後における東京の社会教育のあゆみ』通巻Ⅹ、1997年。
(8)小川利夫「公民館論の再構成」日本社会事業大学編『戦後日本の社会事業』勁草書房。
(9)たとえば、世界教育史研究会編(梅根悟監修)『世界教育史大系』36、37(社会教育史Ⅰ,Ⅱ)
講談社、1974~75年、主として欧米諸国の項、参照。
(10)小林文人「東京三多摩における社会教育をめぐる住民運動ー1970年代を中心にして」
前掲(7)『戦後三多摩における社会教育の歩み』Ⅸ、1997年、所収。
(11)前掲(2)『公民館史資料集成』第3部、解説pp38~41。
(12)松下圭一『社会教育の終焉』筑摩書房、1986年、高梨昌『臨教審と生涯学習』
エイデル研究所、1987年、第2章など参照。
(2) 終章-国際的視野からみる公民館の課題と可能性-まとめにかえて
はじめに―脱皮・発展の課題
公民館という施設は、まさに日本的な土壌のなかから生まれ、きわめて土着的な性格をもっている、その意味で特殊日本的な制度であると言われてきた。日本的な施設としての独自性が強調されてきた向きがある。しかし本書のように国際比較の視点をもって各国の事情を調べていくと、公民館に類似する施設がさまざまの国・地域において存在し、それぞれの歴史をくぐり固有の役割を担いつつ、社会的公共的に機能してきていることが分る。国際的に共通する地域の学習文化活動と、そのなかで施設のもつ意義と役割を確かめることができた思いである。
そのような共通認識の上で、あらためて国際的な視野から考えると、いったい日本の公民館はどのような施設なのか。いかなる特質をもち、またどんな課題、展望をもっているのか、検討を深めていく必要がある。
類似の学習文化施設といっても、国・地域によってすべて一様ではない。公民館自体も(地域史研究の項で明らかにしたように)多様な側面をもち、地域的にも独自な展開をとげてきている。単純な比較はむしろ慎むべきであろう。公民館の国際比較論は、これから継続的に取り組むべき大きな研究課題というほかない。本書は世界の社会教育施設を日本の公民館との関係で総覧した初めての試みであるが、ここで総括的に考察、分析する段階には到達していない。しかし本書の終わりに、不充分であるがまとめにかえて、今後に向けていくつかの仮説的な提起を試みることにしよう。
公民館の歩みはすでに半世紀を経過し、その施設としての性格・特徴はほぼ明らかである。五十年余の歳月は、公民館を地域に広く普及し定着させてきたが、反面、その過程で公民館のイメージの固定化、組織や機能の画一化、制度的な硬直化もまた“定着”してきたように思われる。公民館のもついわば硬い構造の蓄積とともに、意欲的な公民館実践にみられる、みずみずしく柔らかな発展的要素を逆に喪失してきた側面もあったのかもしれない。制度的な定着と機能的な発展の間の矛盾の問題、この課題をどう乗りこえていくか。海外各地のさまざまな事例、とくに地域・草の根にさまざま動いている諸施設の個性的かつ躍動的な動きを通して考えさせられてきたことであった。
いま厳しい時代に直面して、公民館がこれからどのように新しく発展していくかが問われている。施設の制度的な普及定着を基盤としながら、しかしその固定的な体質から脱皮し、時代が求める役割に創造的にチャレンジしていくことができるかどうか。自己変革の方向をどう模索していくか。国際的な視野から考えてみると、何が見えてくるのだろう。
1、公共性の問い直し
国際比較からみて、日本の公民館の主要な特徴は、何よりも国家実定法上の基礎をもつ公共的機関としての制度的位置づけである。公民館の設置主体は「市町村」であり、公立公営を基本型とする公民館の設置運営が半世紀にわたって蓄積されてきた。自治体など行政機関は必要な条件整備(教育基本法第10条)・環境醸成(社会教育法第3条)に努める責務が法的に規定されてきた。
しかし公民館の公共的条件整備の歩みはむしろ厳しい道程であった。法的「基準」性は不備であったし、政策的な比重も弱く、行財政的条件は概して低水準に止まり、とくに(物的施設条件に比べて)人的条件としての職員体制整備・専門職化は遅々として進んでこなかった。その現実があるだけに、公民館をめぐる公共的条件整備の課題が、研究的にも運動的にも、一貫して追及され主張されてきたのである。
このような法制上の位置づけにより、公民館設置は義務教育機関と並ぶ水準に到達したが、その実相はどうか。この間、公民館の公的条件整備は拡充されず、もともと低劣な職員体制水準はむしろ相対的に低下してきた経過がある。公民館統計にみる高い設置水準も単純には評価できない側面がある。
このような状況のもとで国及び自治体行政による「公共的条件整備」について、いまあらためて「公共」性概念を問い直してみる必要がある。行政セクターによる公的設置と公費による条件整備という意味での「公共」性とともに、施設のあり方として、広く社会的に開かれ多くの市民の参加を差別なく保障していくという意味での「公共」性の視点を考えてみたい。行政的公共性だけでなく、後者の社会的公共性の観点からみれば、公民館はいまどのような状況にあるのだろう。
社会的公共性の思想は、国際的な施設の動向のなかから多くを教えられる。行政的公共性はむしろ社会的公共性の手段なのではないか。社会的に開放されすべての参加と活動が保障されるといいう意味でのパブリックな施設を実現していくために、どのような行政的条件整備が求められるのかが問題となる。公共的条件整備の課題とともに、社会的な拡がりをもった「公共」的機関としての公民館のイメージをふくらましていく必要がある。
2、社会的な運動との出会い
前節と関連して、施設に関わる市民運動・社会運動との関係性が問われることになる。官製的な施設として誕生した公民館は、この点においてとくに欧米の諸施設の歴史的背景と際立ったコントラストをみせる。欧米の近代化過程のなかで胚胎する学習文化諸施設が多く民衆運動的背景をもって登場してきたのに対して、日本の公民館の場合、そのような運動的な要素を欠落して制度化された。起点となる公民館初期構想(寺中構想)は、民主主義の訓練と地域づくり運動を唱導しながら、構想自体は官側から文部「次官通牒」として打ち出された。そして今日まで設置されてきた1万8千前後の公民館も、地域の社会運動的基盤に依拠して創設される事例は少ない。
産業革命以降の歴史的な系譜をふむ労働組合運動、協同組合運動、セツルメント運動等、あるいは現代の市民運動、社会文化運動、各種住民運動等、総じて社会運動体と公民館制度はほとんど接点をもつことがなかった。具体的な公民館事業や運営審議会の構成等においては、非運動的な性格がつよい社会教育関係団体との対応が主となってきた。このような非運動的な体質は、地域課題、現代的課題に取り組む地域諸運動体との疎遠な関係に受け継がれている。この体質をこれからどう克服していくか。
しかし本書に収録された公民館の地域史事例では、現実の展開過程のなかでさまざまの運動的な展開が織りなされてきた事実が少なからず報告されていた。上記の社会運動体との直接的な関係としてではなく、公民館の設置や運営に関わるいわば内部的な参加や運動であるが、脱皮や変革に向けてのエネルギーが潜在的・内発的に胎動してきた歩みを知ることができる。
この問題に関連しては、とくに非営利市民組織(NPO)と公民館がこれからどのような関係を創造していくかが興味あるところである。いまその出会いは始まったばかりだが、公民館の歴史的体質を変革していく大きな契機となることが期待される。
3、多様・多元的な設置運営
冒頭・序論の佐藤一子論文において、施設の設置運営主体(プロヴァイダー)として四類型が紹介されている。国際的な動向に見られる学習文化施設の多様な拡がり、多元的な設置形態を前提にしてのことだろう。
日本の公民館の場合、その第1類型である公共機関による設置運営が圧倒的多数を占める。公民館のような地域施設の運営や機能は、地域の諸課題や市民の諸要求に応えて、多様、多彩、多元的な性格をもつことが期待される。公民館の地域史研究においても、画一的な全体史では見えない、地域的に個性的な多様な試みが注目された。しかし、公民館の設置主体についていえば、ほとんど一元的なのである。
それは言うまでもなく、社会教育法第21条「公民館は、市町村が設置する」に依拠している。同時に、社会教育法は市町村以外の設置形態を二つ用意している。一つは民法第34条の法人による設置であり、あと一つは「公民館に類似する施設は何人もこれを設置することができる」(同法第42条)とする規定である。しかし法人立公民館は実体がほとんどなく、類似公民館については多様な実体があるにもかかわらず、その積極的な意義についての注目はこれまで少なかった。上述の類型論でいえば、集落自治公民館は第2(ないし第3)の類型と考えることができよう。
本書に収録されている公民館地域史のなかでは、この点に関連して、沖縄の字公民館や全国各地の自治公民館、分館等、さらに公設民営の形態で運営されている川崎「ふれあい館」の存在等が、多様・多元的な設置運営の事例として興味をひく。また、本書の事例としては取りあげていないが、第三セクター等への公民館「委託」問題についても、公共的条件整備の後退という側面を把握しつつ、今後の委託の具体的な形態を吟味していく必要があろう。NPO・市民団体への新しい委託形態もこれから出現するのではないか。
4、施設の総合性と具体的な展開
海外の類似施設と比較して、公民館の機能的特徴は、教育・学習・文化を基軸にしたコミュニティ施設、その意味での総合的な施設ということであろう。その歴史的形成過程や地域的条件によって、具体的な形態は異なるにしても、公民館が総合的な性格と機能をもっている点に独自性があることは疑いない。
総合的な機能を果たしていくためには、施設としてそれに見合う体制と力量が求められる。しかし公民館の実質的条件は必ずしも“総合”的ではない。とくに法制上の「教育機関」としての条件は、ヨーロッパの市民大学、成人教育センターなどと比較してきわめて低劣というほかない。結果として「ごった煮」「あいまい」施設と揶揄されてきた経過があった。この状況をどのように克服していくか課題であろう。
単独の公民館が、それぞれ独立して総合的施設であろうとする短絡的な発想から脱却する必要があるのではないか。その意味で自治体内外の公民館相互のネットワークが重要であろうし、図書館・博物館・青少年施設・福祉施設等との連携・協力による総合的な体制づくりと、そのなかでの公民館の独自の総合調整の役割が期待されることになる。
とくに学校教育との提携と役割分担の視点が重要であろう。地域の学校の開放、そして大学の公開講座・地域セミナ―等との連携によって、公民館が自ら開設する学級講座に加えて「私の大学」(三多摩テーゼ)としての実質を総合的かつ立体的に実現していく可能性を考えることができるのではないか。
5、職員体制と人的ネットワーク
公民館創設からすでに半世紀余、しかし公民館を支える職員制度は法制的に未整備に終わり、公的機関としてはきわめて貧しい人的体制のまま低迷して今日に至っている。職員不在の、施設だけの公民館という実態もみられる。国際比較からみて、残念ながらこの点が日本の公民館として無視できない特徴となってきた。
もともと公的な職員体制が不備であるため、これを克服しようとする理論的かつ運動的課題は、正規職員の拡充と専門職化に向けられてきた。このこと自体は間違いないことであろう。しかしその結果、正規職員以外の(嘱託、非常勤等)職員の拡充や、これを支えるボランティアや市民ネットワークの形成などについては中心的課題になってこなかった。むしろ正規職員体制の阻害要因として、嘱託職員やボランティアの存在が否定的に捉えられる傾向もみられた。
海外諸施設において事情は一様ではないが、多様な勤務条件をもったスタッフが、それぞれの立場と専門性を基礎に協働し、意欲と情熱にみちた表情で仕事を楽しんでいる情景が少なくない。誇りと自信をもった人々によって支えられる施設は輝いてみえる。
いまあらためて公民館を支える人的な体制を、正規職員だけではなく、講師・指導者・
各種スタッフ・企画準備委員・ボランティアなどを含めて、全体的なネットワークとして多彩に編成していく視点が重要である。その中での職員の役割を問う必要があろう。
以上、国際的視野からみた日本・公民館の特質を5点ほどあげ、考えてみたい課題について仮説的な検討を試みた。すなわち、1)公共的機関としての位置づけ、2)運動的要素の欠落、3)設置主体の一元化、4)施設の総合的性格、5)職員と人的体制、についてである。もちろん世界と日本の厳密な比較分析に基づくわけではなく、不充分の謗りを免れないが、今後さらに批判的に深められ、公民館の新しい歩みを展望する手がかりとなれば幸せである。
8,三多摩テーゼ20年、拾遺「三多摩テーゼ」記 ほか→■
*社会教育・公民館研究ページ→■
トップページへ